2009年10月26日
『国家の罠』 佐藤優 (新潮文庫)
先日、最高裁で有罪が確定した元外務省主任分析官、佐藤優氏の手記である。
本書は右から左までさまざまな立場の人に絶賛されたベストセラーであり、今さら感があるが、読むタイミングを逃していたので(みんなが読んでいる本を手にとるのは若干抵抗があるのである)、有罪が確定した機会に読んでみた。
面白いとは聞いていたが聞きしに勝る面白さで、密度の高い文章が550頁つづくのに二日で読みきった。その後も佐藤氏の本を読みつづけ、合間に手塚治虫の漫画でクールダウンするというのが最近の読書事情だった。
主要な本を一通り読みおえたので、ここでまとめて感想を書いておきたい(一つのテーマでまとめて感想を書くことについて、キャンペーンをやらせて いるのではないかと「書評空間」事務局に苦情があったそうだが、まったくの誤解である。テーマを決めて感想を書くのは1998年以来ネットでつづけている わたしの流儀なので御容赦いただきたい。選書の方針については拙サイトの10月24日付エディトリアルに述べたので、興味のある方は読んでほしい。)
著者は同志社大神学部と同大学院を卒業後、外務省にノンキャリアで入省し、崩壊前後のソ連で情報収集に成果をあげたが、本省にもどって北方領土返 還交渉にあたった後、鈴木宗男事件に連座して逮捕されている。容疑は背任と偽計業務妨害だったが、著者は「国策捜査」による冤罪だとした。「国策捜査」と いう言葉は本書によって広まったといってよい。
本書は基本的に弁明の書なので、背任容疑の対象となったロシア情報の収拾活動の実態や偽計業務妨害容疑の対象となった北方領土の現状、さらには外務省やロシア政界の内情まで踏みこんで語っており、興味が尽きない。
著者はソ連=ロシアの情報収集で抜群の成果をあげ「異能の外交官」とか「外務省のラスプーチン」と呼ばれるようになるが、この情報収集が世界的な レベルなのである。ソ連時代からクレムリンの奥深に出入できる人脈を作りあげ、八月クーデターではゴルバチョフの生存情報を世界で最も早くつかんでいる。 エリツィン政権になるとモスクワ大学で教鞭をとるようになり、エリツィン元大統領の最側近三人のうち二人の信頼を勝ちえて執務室の奥のプライベートルーム にまで出入できるようになっている。ソ連崩壊の引金となったリトアニア独立の際には独立派が立て籠もったバリケードの内側と外側の橋渡しをし、独立後、リ トアニア政府から独立に貢献した64人の外国人の一人として勲章を授与されている。
驚くべき話が次から次へと出てくるが、思想レベルに昇華されているので自慢話臭さはない。後に出た本を読むとわかる、そもそも本書に書かれている見聞はほんの一部にすぎず、これでも抑えに抑えて書いているのだ。
本書の中核部分は512日におよんだ拘置所生活と、そこでくりひろげられた取調検事との攻防である。容疑者と検事の攻防というと『罪と罰』を連想するが、ラスコーリニコフはどう見ても西村検事の方だ。
わたしは「国策捜査」は著者の造語と思いこんでいたが、実際は特捜部の内部用語のようである。逮捕の当日、著者に「本件は国策捜査だから逃げられない」と言いわたしたのは取調にあたった西村尚芳検事だったのである。
「国策捜査」について著者と西村検事は迫真の議論を展開するが、西村検事の見解はこうだ。
「あなたを捕まえた理由は簡単。鈴木宗男に繋げる事件を作るため。国策捜査は『時代のけじめ』をつけるために必要なんです。時代を転換するために、何か象徴的な事件を作り出して、それを断罪するのです」
国策捜査=国家による冤罪と受けとる人が多いと思うが、西村検事によればそれは違う。
「冤罪なんか作らない。だいたい国策捜査の対象になる人は、その道の第一人者なんだ。ちょっとした運命の歯車が違ったんで塀の中に落ちただけで、歯 車がきちんと嚙み合っていれば、社会的成功者として賞賛されていたんだ。そういう人たちは、世間一般の基準からするとどこかで無理をしている。だから揺さ ぶれば必ず何かでてくる。そこに引っかけていくのが僕たちの仕事なんだ」
揺さぶれば出てくるということは揺さぶらなければ出てこないということでもある。公訴権の濫用だけでも問題なのに、著者によれば特捜部の検事自身 が政治的濫用を認めているわけだ。本当にこんなことを言ったのだとしたら恐ろしいことである(名誉棄損で告訴されていないところをみると、実際にそういう 発言があったのだろう)。
西村検事は国策捜査は時代を変えるために必要と述べているが、これはあくまで著者との応酬の中で作り上げられていった理屈であって、特捜部全体の コンセンサスではないだろう。第三者的にみれば特捜検事は政権トップによる政敵つぶしの片棒をかつがされているわけで、時代を変えるためという名分は後知 恵か、汚れ仕事から目をそらすための自己弁護にすぎないのではないか。
西村検事は著者との関係を保つために、通常では考えられないさまざまな便宜を供与したようである。検事としてやりすぎではないかと思うが、特捜部 は西村検事の判断を支持しつづけ、一審では公判もまかせている(筋の悪い事件なので引き受け手がいなかったのかもしれないが)。一段落したところで水戸地 検に栄転しているが、自由に腕をふるわせ仕事を評価してくれる上司をもった西村検事を著者は「うらやましい」と書いている。
文庫のための「あとがき」では、オランダ大使に転出後、外国生活をつづけて逮捕をまぬがれた東郷和彦元欧亜局長が5年ぶりに帰国し、二審で著者の 側に立った証言をおこなった経緯が記されている。それはそれで結構なことだが、東郷氏は祖父の代からの外交官でキャリア組だから、ノンキャリアの著者とは 外務省のあつかいが違うことも押さえておいた方がいい。
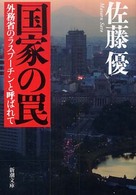
0 件のコメント:
コメントを投稿