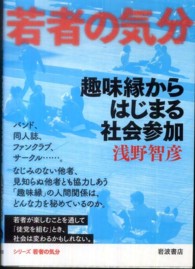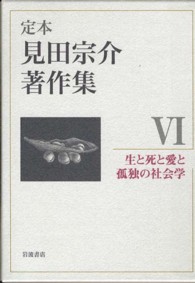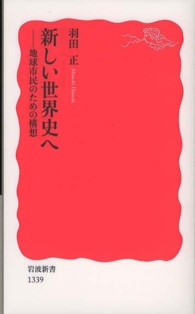2011年12月28日
『哲学の歴史 03 神との対話』中川純男編(中央公論新社)
中公版『哲学の歴史』の第三巻である。このシリーズは通史だが各巻とも単独の本として読むことができるし、ゆるい論集なので興味のある章だけ読むのでもかまわないだろう。
本巻はキリスト教神学の基礎となった2世紀のアレクサンドリアの哲学からルネサンス直前の14世紀のマイスター・エックハルトまでの1400年間 をあつかう。中世というくくりになるが、年代的に長大なだけでなく、ギリシア哲学を継承し西欧近代に伝えたビザンチンとイスラムの哲学、さらにはユダヤ思 想までカバーしている。これだけ多彩な思想の営みを一冊に詰めこむのは無茶であるが、従来の哲学史だとまったく無視するか、ふれても普遍論争に言及する程 度だったことを考えると、中世の巻を設けてくれただけでもありがたい。
このシリーズは編集がゆるく執筆者を選んだらまかせきりという印象があるが、本巻はその傾向が特に強く出たように思う。後半ではラテン・アヴェロ エス主義が台風の目となり、トマス・アクィナスやボナヴェントラ、ヘンリクスらをあつかった章ではラテン・アヴェロエス主義が仮想の論敵として大きく取り あげられているが、当のラテン・アヴェロエス主義を論じた章ではラテン・アヴェロエス主義などというものは存在しない、実態はソルボンヌ内部の派閥争い だったとしているのだ。執筆者間の連絡がなんとかならなかったのだろうか。
他にも不満はあるが、一般向けの本がすくない分野だけに貴重な本であることは間違いない。
「� アレクサンドリアの神学」
ユダヤ思想家のピロン(フィロン)と初期ギリシア教父のクレメンス、オリゲネスのさんにんをとりあげている。
ピロンは活動期がキリスト教の成立時期と重なるために注目され、35タイトルの著作がほぼすべて今日に伝えられているということである。
ピロンは聖書の比喩的解釈の先鞭をつけ、ギリシア哲学との折衷をはかったことがキリスト教神学に大きな影響をあたえた。律法をノモイと訳し、「ノ モイに従う人はコスモポリテース(世界市民)である」と自然法的に解して普遍化をはかるなどである。「創世記」については一日目に範例となるイデア界が、 二日目以降に可感的世界が創造されたとというプラトンに準拠した二段階創造説を提唱しているが、面白いのは二つの資料の不一致を二段階説で辻褄をあわせて いることである。「創世記」には「人間は神の像になぞらえかたどられた」と「ヤハウェ神は地の塵から人間を造った」という二つの人間創造説があり、今日で は起源の異なる二つの文書をいっしょにしたためだとわかっているが、ピロンは一の日に創造された像(エイコーン)は 形をもたないイデアだとして神人同形論を回避し、可視的世界の人間はイデアの影(神の影の影)で神から隔たっているために堕罪の可能性があるとする。もっ ともイデア=神の思考だと明言してしまうと神の一性に抵触するので、比喩にとどめる。神の思考という発想はアウグスティヌスにも継承されるという。
クレメンスはキリスト教徒のための最初の学校をパンタイノスが設立したことが知られているが、主著の『雑録集』は「綴れ織り」という意味で「高齢 から来る忘却への薬」としてさまざまな著作からの断片を記録している。仏陀に関するキリスト教文献最初の言及を含むということである。
オリゲネスはエウセビオス『教会史』第6巻など伝記資料がたくさん残っている。アレクサンドリアの主教とまずくなってカイサリアに移住し学園を開 いたが、没後、異端宣告を受けたために著作が散逸し、ラテン語訳の形でしか残っていない。ところが蔵書の方はカイサレイア主教バンピロスによって図書館が 建てられ保存されたという。七十人訳の校訂をおこない、さまざまな翻訳を一覧できる『六欄対訳聖書』を刊行したことも功績とされている。
『ケルソス論駁』で復活批判に反論したが、コリント書15:42を根拠に復活した肉体は復活前と異なるとする。「朽ちるものとして播かれ、朽ちないものとして甦る」というわけだ。
「� アウグスティヌス」
どこかで読んだ話ばかりで新味はない。
ドナトゥス派との論争の条でキルクムケリオネスという暴力的な土地を失った下層民集団が無法を働くとあるが、映画「アレクサンドリア」に登場した「修道兵士」のようなものかなと思った。
もう一方の論敵のペラギウス派はギリシア的教養に通じたローマの富裕層が基盤だった。アウグスティヌスはペラギウス派には容赦なかったが、ドナトゥス派にはずいぶん寛容である。ドナトゥス派にある種の共感を抱いていたのだろう。
『三位一体論』についてはかなり立ち入った紹介がある。いつか読んでみたい。
「� 継承される古代」
前半では自由七科に代表されるギリシア的教養を中世世界に伝えたボエティウスとカッシオドルス、後半では神学をいきなり高みに押しあげた偽ディオ ニュシオス・アレオパギテスとエリウゲナを紹介しているが、後者について「古代の継承」というのはどうだろう。この章は二つにわけるべきだったのではない か。
ボエティウスはギリシア語を理解できなくなった同胞の教育は政治家の義務と任じて、東ゴート王国の宰相という激務のかたわら、自由七科の教科書を編纂し、アリストテレスの論理学書と『エイサゴーゲー』をラテン語に訳し、注解をくわえた。
ボエティウスというと『哲学の慰め』が名高いが、カロリング・ルネサンスで評価されるまでは埋没していたという。
カッシオドルスはボエティウスの地位を襲い、学問的にもボエティウスの衣鉢をついだが、神学と世俗的学問(自由七科)の両立を提唱し、引退後は故 郷のスキュラケウムに隠修士のための修道院と世俗的学問のための修道院ウィウァリウムの二つを建設した。後者には膨大な蔵書を納めた図書館を設けた。写本 工房もあったらしく、ウィウァリウムの蔵書は後に教皇のラテラノ宮の図書室に移管され、各地の各地の修道院に貸与されたり贈与され、広く流布したという。
偽ディオニュシオス・アレオパギテスとエリウゲナはそれぞれ独立の章をたててもおかしくない大物だが、百科事典的なコンパクトな記述で終わっている。
「� アンセルムス」
最初のスコラ哲学者と呼ばれている人だが、北イタリアの貴族の家に生まれ、父親に修道院入りを反対されて出奔し、フランスの修道院にはいったという激しいところもあった。
神の存在証明で知られているが、同時代人からも批判が出ていたという。あれが証明になっているとはとても思えないが、20世紀になってからカール・バルトとハーツホーンが再評価しているそうである。どう再評価したのか、知りたいところだ。
「� ビザンティンの哲学」
坂口ふみの『<個>の誕生』でであった名前や学説、議論に再会して懐かしかった。ここに書かれているのはほんのさわりだけだけれども、ビザンチンの神学は深い。
「� 一二世紀の哲学」
12世紀ルネサンスをアベラルドゥスを中心に描いている。アベラルドゥスとは『アベラールとエロイーズ』のあのアベラールである(最近、岩波文庫から新訳が出た)。
アベラールといえば普遍論争だが、普遍的な物の実在を否定したために語と対象が対応する理由の説明に苦しみ、ストア派のレクトンに近いstatusという概念を編みだすが、十分発展させることなく撤退してしまったという。
アベラールの神学についてはかなり詳しい紹介がある。アンセルムスと対立的にとらえる従来の説は誤りで、著者はアベラールが軸足を置くのはアンセルムスの論理学的神学だとする。サン=ヴィクトル学派のフーゴーとの影響関係などもおもしろい。
アベラールは頭はめっぽういいが性格的に問題のある人だった。教え子のエロイーズを妊娠させてしまったこともそうだが、恩師を片っ端からバカ呼ば わりしているようなところがあり、敵が多いのも当然である。異端審問にかけられたのだって神学的内容よりも性格がまねいた面があったようだ。
こんなにおもしろい神学者はいない。誰か映画化しないものか。