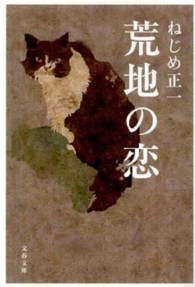「国木田独歩はビジュアル好きのすぐれた編集者だった」
古書ファンには女性が少ない。古書フェアなどでうつむき加減に、しかし内心は人にとられてなるものかと闘争心を燃やしつつ手を動かしているのは決まって男 性だ。ところが、これまで男性専科だった古書界で話題を集めている女性がいる。『古書の森逍遥』という本を出したばかりの黒岩比佐子である。ノンフィク ション作家の彼女は、執筆の途上で必要に迫られ古書を手にとるうちに、おもしろさに魅せられはまっていったという。
彼女のコレクションを解説した『古書の森逍遥』については後述するとして、まず取りあげたいのは、古書の知識を活かして知られざる事実を明らかにし た、『編集者国木田独歩の時代』という彼女の著書である。独歩が有能な編集者であったという、ほとんど忘れかけられている事実に光を当てた驚愕の書だ。
国木田独歩と言えば、だれもが浮かべるのは「武蔵野」。自然主義文学を代表するこの有名な小説のせいで、独歩といえば小説一筋で生きたような印象が 強いが、実は彼はグラフ誌の編集者として、時代を先取りするような仕事をたくさん成し遂げていた。『家庭画報』という、いまも読み継がれている婦人雑誌を 創刊したのは彼である。版元は変ったものの、明治期にスタートしたものがいまもその名前でつづいている事実には、自然主義文学者だけに収まらない彼の顔が 想像できるだろう。
20代の独歩は新聞社に勤めたり雑誌に寄稿したりしているが、鳴かず飛ばずと言った感じが強い。27歳で発表した「今の武蔵野」(のちに「武蔵野」 に改題)も評判にならず、結婚して子供もいる身なのに、生活は困窮をきわめている。ところが31歳で『東洋画報』の編集長に抜擢されてから、身辺がにわか に活気づいてくる。それまでの仕事は活字が中心だったが、今度の『東洋画報』は写真や挿画で見せるグラフ誌である。そこに彼の才覚が開花したのだった。
グラフ誌の成長をうながしたのは皮肉にも戦争である。日清戦争で大本営に写真班が設けられ、写真が積極的に使われるようになるが、当時はまだ戦況の 記録ではなく、作戦を練る資料として活用するのが主だった。現在わたしたちがあたり前のように接している空撮やコンピュータグラフィックスが軍事目的で開 発されたことを見ても、戦争と写真が手をとりあって進んできた一面が明らかだが、戦争が外国との戦いになりふつうの人々が異国に出征するようになったと き、写真が人々の視覚的な好奇心や興味を満たす役割をも担っていくようになったのは必然だっただろう。
『東洋画報』は6号目から『近事画報』と名を変え、版元も変って、グラフ誌らしい体裁を整えていく。そのあたりのいきさつは本書に詳しいが、興味深 い事柄として著者はふたつのことを挙げている。ひとつは『近事画報』の2号から全国各地で写真を撮って編集部に送る「特別通信員」制度がはじまっているこ と、3号に「満韓最新全図」の折り込み付録と、朝鮮で撮影された写真が多数掲載されていることである。日露戦争の開戦は翌1904年だが、独歩は戦争の気 配を察してビジュアルなページ構成で読者の興味を惹きつけたのだった。
戦争の火ぶたが切って落されると、戦争雑誌の創刊ラッシュが起きる。近事画報社にとっては日露戦争は「経営を軌道に乗せる千載一遇のチャンス」と なったのだが、「そこでの独歩の動きは素早かった」。画家を戦地に派遣して臨時増刊『戦時画報』を出すことを発表。この臨時増刊号は月3回発行されて本誌 のペースを上回り、日露戦争中はずっと『近事画報』が『戦時画報』と名を変えて出しつづけられる。「戦時」をビジュアルを伝える「画報」というイメージ が、大衆にとっていかに新鮮だったかがわかるだろう。
戦地に送られた画家のなかには、のちに小杉放庵の名で有名になった画家の小杉未醒の名があった。わたしは独特のユーモアと知性の光る放庵の絵のファ ンで、日光にある彼の個人美術館も好きな場所のひとつである。彼が漫画やポンチ画を描いていたことは知っていたが、独歩の雑誌で挿絵画家として活躍してい たことは知らなかったから、この事実にはとりわけ興味を引かれた。独歩より10歳若く、83歳まで生きた放庵には、独歩と同時代人という印象は薄いが、独 歩が没するまでずっとそばにいた良き伴奏者だったのである。
未醒の挿絵が『戦時画報』に果たした役割は小さくないと著者は見る。当時は写真の技術がまだ稚拙だったので、写真と挿絵を半々くらいに載せたと未醒 は後に回想しているが、写真が力をつけてくるまで、ジャーナリスティックな視線に満ちた彼のコマ絵(カット画)は誌面を大いに活気づけたのだった。たとえ ば「足のいろいろ」と題して、歩兵、砲兵、新聞記者など5人の足を観察し、職種や地位によって履いている靴がどうちがうかを描いて見せたりしている。
当時は臨時増刊号が大はやりで各社が競ってだしたが、この企画にも独歩の独自の視点が光っていた。日露戦争終結の1905年には『捕虜写真集』を出 している。日本軍の捕虜となったロシア兵の数は7万人を超え、全国各地に29箇所もの捕虜収容所が造られたそうだが、そこでの捕虜の日常生活を写した写真 集を出したというのだから驚く。当時の日本の読者にはほとんど受けなかっただろう。「敵国の捕虜のなどには関心がなく、戦地で戦っている日本の兵士の状況 を知りたい、というのが多くの人々の本音だっただろう」という著者の意見に同感である。だが、捕虜のロシア人は異国の空の下でどんな日々を過ごしているの だろうという率直で人間らしい好奇心には、現代のわたしたちの心にも触れてくる何かがありはしないだろうか。いま見ても新鮮な写真だそうだから、ぜひ見て みたものだと思った。
『富士画報』という臨時増刊も出している。はじめは軍艦「富士」の特集号かと思ったと著者は書くが、文字どおり富士山の特集で、編集部員が富士登山 して書いた紀行文と写真と絵で構成されていた。当時、戦勝祈願に富士登山するのが流行っており、とくに戦争が終結したこの年には女性がたくさん登ったとい う。戦勝の高揚感がブームをあおったのだろう。編集部でも富士登山を体験して息吹を伝えようとしたのだった。
未醒の戦地での足の観察もそうだが、捕虜のドキュメントといい、この富士登山ブームの特集といい、独歩の考えることにはいまでいうカルチャー誌的な 発想が感じられる。直線的に切り込むバリバリのジャーナリズムとはちがう。ひとつの事柄を別の視点で見たらどう見えるのかと考えてみる着想家の一面があっ たように思う。
もうひとつ著者ならではの取材力が発揮されているエピソードがある。独歩の妻治子は、夫が病気で亡くなった翌年の1909年に、「破産」と題した小 説を新聞に連載した。これは夫が独歩社という出版社をはじめてから解散にいたるまでのいきさつを書いたもので、実在の人物が仮名で出てくる。著者はその 20余名の登場者のモデルを資料を駆使して突きとめているが、そのなかでひとりモデルのわからない女性がいた。近事画報社に女性の写真部員として入社した 「梅子」という女性である。実在のモデルがいるにちがいないと察した彼女は「梅子」探しに乗りだす。
だが、いろいろと手を尽くしたが見つからず、九分九厘まで諦めたとき、かつて目にした明治期の女性のための職業案内書がよみがえる。そこに女性の職 業として「写真師」がでているのではないかと調べてみると、予想どおりそういう項目があり、「女子写真伝習所」という教育機関のあったことがわかる。さら には『文芸倶楽部』に掲載された「女子の写真術」という記事のなかに、「梅子」と思われるその学校の卒業生が触れられているのを見つけ出す。最後には彼女 の遺族を探してインタビューもしているのだ。
明治期に女性のための写真学校があったこと、愛媛から出てきてそこで写真を学び、独歩のもとで働いた女性写真家がいたことなど、驚くべき事実がつぎつぎと明らかになるこの箇所は、古書の森を分け入る著者の面目躍如といった感があり、手に汗をにぎりながら読んだ。
技術的にも体力的にも彼女より優れた男性カメラマンがいただろうに、独歩が日野水雪子という駆け出しの女性カメラマンを雇ったのはなぜだろう。独歩 はぐずぐずするのが嫌いな、恐ろしく短気な人で、「驚きたい」「感覚を鋭く新しく」というのが口癖あったらしい。彼と同い年の友人、田山花袋が「国木田独 歩論」のなかでそう書いている。そんな独歩にとって、女性カメラマンという新人種が興味をかきたてなかったはずがない。
この日野水雪子の例に見られるように、古書を古書に終わらせずに現代に繋げるダイナミズムが、本書の著者であり、古書のコレクターでもある黒岩比佐 子の大きな魅力だ。村井弦斎の評伝を書くために明治期の婦人雑誌を調べる過程で『婦人画報』が国木田独歩の作ったものだと知り、興味をもったのが最初で、 その後、『日露戦争 勝利のあとの誤算』を書いて日露戦争とジャーナリズムの関係を探ったとき、戦時下で読まれた『戦時画報』というグラフ誌がまたしても 独歩の編集だったのを知り、驚きがさらに増したという。
このように彼女の場合は知りたいことがあって古書にむかうのであり、ただ物珍しさに稀覯本を集めて悦に入るのとちがう。また資料で明らかになったこ とを後づけるために、関係者への取材も怠らない。こうして古書と現実とを行き来しながら、歴史のなかに埋もれてしまった事実を掘り出していく姿には、知的 好奇心に裏付けされた瑞々しさが満ちていて、知ることの楽しさを読者に教えてくれる。
『古書の森逍遥』には、彼女のインスピレーションの元になった古書の数々が紹介されており、本書を読んだら、つぎにはこれを手にとりたくなるだろ う。人物別の索引がついていて、「国木田独歩」で引くと、ここに登場する古書や使用した資料などが逆引できるのも楽しい。古書の世界をこんなふうに演出し てみるところに、独歩にも通じる新鮮な眼が実感できるはずである。
『編集者 国木田独歩の時代』 →bookwebで購入
→bookwebで購入
『古書の森 逍遙』 →bookwebで購入
→bookwebで購入