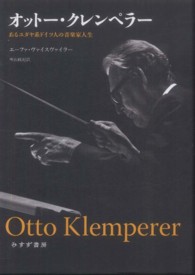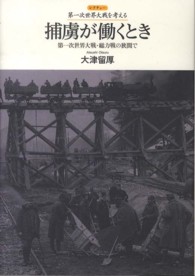→紀伊國屋ウェブストアで購入
→紀伊國屋ウェブストアで購入
「和歌と演技」
�和歌語り�は一つのジャンルである。呼吸がちょうどいいのだろう、ふと和歌をのぞいて賞味しては、「ふむ」と一呼吸置いてからおもむろに地の文 に戻るという流れが、ある種の読書にぴたりとはまる。ぐんぐん、ずいずい読むのではない。ぱらぱら、はらはら読む。岩波新書だけをとっても、斎藤茂吉の 『万葉秀歌』(上下)や大岡信の『折々のうた』シリーズなど短詩型に焦点をあてたものが定番となってきたのは、そうした収まりの良さと関係あるのだろう。
和歌語りの典型的なパターンは、濃密な「情」をたたえた和歌を、ちょっと距離をおいた評者が「知」のことばで受け止めるという形である。だから、さまざま な秀歌をあっちこっち覗きながらも、どことなく涼しい顔というか、退屈げでさえあるような、どこ吹く風という空気がある。そして、そんな緩い空気の中に、 ときおり射貫くような、あるいはひねりや毒を少しだけ盛った、寸言めいた評が差し込まれたりする。
しかし、本書『和歌とは何か』の著者の 姿勢はそんな「どこ吹く風」の批評とは少し違う。著者の渡部泰明氏には明確に伝えたいテーマがある。「和歌とは演技だ」というテーマである。だから渡部氏 ははじめからけっこう忙しい。序章でも、和歌なんてピンとこないでしょう?私だってそうですもん!と口調に熱がこもる。氏は宣言するのである。和歌を読む ためには「儀礼的空間」ということを頭にいれるといいのです、と。そういう場所で行為として行われるのが和歌なのだ、と。そして本論に入ると、渡部氏は約 束どおり枕詞や序詞、縁語といったおなじみの和歌のレトリックの機能を、「演技」、「偶然性」、「出会い」、「儀礼」、「行為」といったキーワードを助け に読み解いていくのである。
英米文学を専門とする筆者のような者には、この「行為」という概念はとても興味深い。というのも、英米文学の 批評でも、J・L・オースティン(ジェーン・オースティンではない)の言語行為論以降、詩や小説の語りを一種の行為と見ることで、その中に広い意味での政 治性や、読者・マーケットとの関係構築、さらには呪術的な発信作用などを読み取る視点が提示されてきたからである。ホイットマンのような、いかにも派手な パフォーマンスを思わせる詩人に限らず、前回本欄で扱ったディキンソンのように、ひとりでこっそり囁くかのような場合でも、「行為としてのことば」という 要素を見て取ることはできるし、そういうふうに読むことで、解釈に広がりや深みが出る。
ただ、本書で渡部氏が強調する「行為」という概念は、西洋的な言語行為論の枠組みと単純にかさなるわけではなさそうである。渡部氏は和歌が詠まれ た当時の状況を再構築しながら、和歌ならではの社会的機能にせまっていく。当然ながらそこには、当時の日本に特徴的な祭儀の感覚がからむのである。とりわ けおもしろいのは「唱和」という概念である。声を合わせる、ということ。
これはたしかに気になるところだ。和歌のレトリックに人が難しさを感じるのは、掛詞や縁語などにあらわれた声の複数性に戸惑うからである。ひとつ の言葉や句が、同時に複数の声を担うという、その同時性・シンクロの感覚にいったいどう感動したらいいのか、そんなことをして何が嬉しいのか、どこが楽し いのか、それが現代人にはなかなか理解できない。
従ってしばしば和歌語りでは(あるいは学校の授業では)そうしたレトリックについては淡々と語って済ませる。どう受け止めるかまでは踏み込まず に、単にその構造や機能を説明し「あとはご自由に」となる。ある意味では無難で賢明なやり方なのだが、渡部氏がおもしろいのは、そうした部分にさしかかる と、椅子から腰を上げんばかりにして、いよいよ熱心に語りはじめるということである。次々に比喩や付加疑問文的・「でしょう?」的突っ込みを繰り出し、 「えいや! どうだ! これでもわからないかぁっ!」とほとんどこちらの肘を引っ張らんばかりにして前に進んでいく。少し長くなるが、ぐいぐいとステップ アップしていく氏の語り口の例として「掛詞のリアリティ」についての説明を見てみよう。
掛詞のリアリティは、言葉の持つ意味に依拠しているというより、言葉が存在していることそのものの重みによって いる、と私は思う。風景とわが身が偶然に出会う。それは一つの事件である。その事件が存在した重みを、言葉の出会いの中に置き換えようとするのが掛詞なの であろう。我々が生きているのは、突き詰めれば偶然の積み重ねの世界にすぎない。ただ、日常生活の中では、個々の出来事がある程度の必然性を持って連なっ ている、と何となく思い込んでいる。これが原因でこういう結果になったと思い込むことで、心の安定を得ている。しかし、強く何かに心動かされた時—— 美 しいものにふれた、恋をした、人が亡くなった——、世界は新たな姿を見せる。個々の物事が面目を一新し、幸運にもたまたまそこに存在したのであったことに 驚かされる。お定まりの因果関係など、どこかに吹き飛んでしまう。(75)
掛詞って要するに駄洒落でしょ?などと思っていた人は、にわかに違う空気が流れ出してはっとするだろう。しかもそれはかび臭い学者的な説明ではない。渡部氏は勇敢にも「感動」そのものに切り込んでいくのである。
それをどう表現するか。その時の自分の心に感じたあり様を詳しく語る、という手がある。これは我々にもなじみや すい。しかし、もう一つ、世界が偶然ならば、それを言葉の偶然性に移し取る方法もあったことを、掛詞は教えてくれるのである。掛詞は、偶然性をむしろ強調 して、物と心、風景の文脈とわが身の文脈とを強引に重ね合わせ、風景との出会いの衝撃を再現してみせる。(75)
何しろエッセンスの部分を語っているので、引用部だけですべてを理解するのは難しいかもしれないが、本書を具体例とともに順に読み進めていけば、 こうした盛り上がりどころを十分に楽しむことができる。渡部氏によれば掛詞とは「声を合わせることを演じつつ、偶然を必然に変えてしまうようなレトリッ ク」なのであり、「言葉の偶然の一致が、歌の秩序にぴったりと当てはめられ必然化していく姿は、人々の心を捉えて離さなかった」という。
今も昔も、人は偶然に起こる出来事に弄ばれ、かつ孤独に苦しめられながら生きざるをえない。どうにかそこから脱 したいというあえかな願いを、言葉の上で見事に実現しているのが掛詞なのだ。これこそ定型文学・和歌の神髄ともいうべき「力」である。その意味で掛詞は、 和歌の中心的レトリックと呼ぶにまことにふさわしい。(78)
和歌を理解するためには「偶然でありながら、そうでしかありえぬ、という感覚」に敏感になる必要がある。序詞の説明の中でも、渡部氏はこの感覚に こだわりつつ、それを人と人とが声を合わせる「唱和」、さらには「共生の感覚」や「共同の記憶」に結びつけてみせる。このあたりは本書の芯となる議論だろ う。
つなぎ言葉に見られる偶然の音の一致は、和歌の定型に支えられて、必然的なものであるかのように感じられてくる。 するとそこに、人と声を合わせているかのような感覚が発生する。声を合わせている時、人は他の人も同じものを見、同じことを感じているような確信に囚われ る——決してそうとは限らないのだけれども——。この声の響く中で、序詞の風景は、体験に縛られない、純度の高い懐かしさをかもし出しながら、共同の記憶 となって人々に受け入れられるのであった。(58)
「唱和」という概念には、「いただきます」や「乾杯!」も含まれる。こうした部分からも察せられるとおり、本書で渡部氏が強調する「演技」は、 「儀礼」という概念と密着しているのである。「演技」は単に「ふりをする」「ウソをつく」というような皮相な意味でとらえられているのではない。それは人 と人とが社会の中で共生していく上で欠くことのできない祭儀的な装置なのであり、和歌を詠むという行為が、さまざまなイヴェントや習慣を通してそうした祭 儀に組み込まれていたことは、「演技」というキーワードを助けにするとはっきりと見えてくる。本書の後半では、「贈答歌」「歌合」などの具体的な検証を通 して、行為としての歌にいちいち微妙なニュアンスがこめられていたことが説明されるが、あらためて当時の社会の洗練と爛熟を感じさせるところである。
本書で渡部氏がことさら「演技」というポイントに力を入れたのは、現代の読者にとって和歌がますます読みにくくなったことと関係しているだろう。 自身の役者としての経験を踏まえ(氏はかつて野田秀樹氏らとともに「夢の遊眠社」で演劇活動を行っていた)、上演という枠にとどまらない「演技」の社会的 な機能を自覚してきた氏は、そうして得た想像力を存分に駆使し、まるで我がことのように歌人たちの心境を推し量りながら、ときには力強く、ときにはさらに 力強く、和歌語りを進めるのである。
私たちは「詩が読めない時代」を生きている。和歌語りに限らず、批評という�介添え者�なくしてはもはや詩は読まれ得ないのかもしれない。しか し、本書を読むとわかるように、和歌はそれ自体の中に強力な批評性を内在させたジャンルでもある。縁語にしても、本歌取りにしても、先行テクストとの微妙 な距離感をはらんだ批評的なレトリックだと言える。和歌とは自ら語り歌う形式であると同時に、他の歌を読み、読んだテクストを想起する形式でもあるのだ。 その意味では、そこにはきわめて現代的な「詩」の可能性があると言えるのかもしれない。
 →紀伊國屋ウェブストアで購入
→紀伊國屋ウェブストアで購入
![]() マイ本棚登録(0) レビュー(0) 書評・記事 (1)
マイ本棚登録(0) レビュー(0) 書評・記事 (1) ![]() マイ本棚登録(0) レビュー(0) 書評・記事 (2)
マイ本棚登録(0) レビュー(0) 書評・記事 (2) ![]() マイ本棚登録(0) レビュー(0) 書評・記事 (0)
マイ本棚登録(0) レビュー(0) 書評・記事 (0)