2010年06月25日
『現代写真論』シャーロット・コットン(晶文社)
「あたかも世界を編集しているような「現代写真」のありよう」
写真ほど誕生以来、激しく変し多様化を遂げてきたメディアはないだろう。撮り方のスタイルや様式だけでなく、それがもつ社会的な意味が大きく変化してき た。写真はカメラで撮るものだから、おなじ二次元の表現でも絵画よりもスピード感がある。変化の変遷にはそうした「生産しやすさ」がどこかで関係している のだろう。「現代美術としての写真」という原題が示すように、本書はアート作品としてギャラリーや美術館で流通している写真を8つのカテゴリーに分けて語った ものだ。評論というよりは紹介というような内容だが、分類の仕方に著者の論点を読み取るべきなのかもしれない。カテゴリーは以下のように分けられている。
1.あるコンセプトに従っておこなわれた行為の記録としての写真、2.物語を喚起させる絵画的要素の強い写真、3.中判や大判カメラで風景や建物を とらえた高画質の写真、4.日常で見過ごしがちな事物や空間を写し出した写真、5.親密な対象との深い感情的つながりを追求した写真、6.フォトジャーナ リスティックなシーンを報道とは異る視点でとらえた写真、7.名作写真・広告写真・映画のスチールからのリメイク写真、8.写真メディアの変化に着目した 「写真論」的写真。
こうした分類のもとに243点の写真が紹介されている。なんでもアリな印象で、これらすべてが写真の名のもとに展示されている場面を想像すると頭が くらくらするほどである。題材が写真ということだけが唯一の共通点。インターネットからとった画像を加工したトーマス・ルフの作品では、カメラすら使われ ていないのだ。
こうした多様な写真群がいま「コンテンポラリーアート」に場所を得て、美術館やギャラリーで展示され、コレクションされ、売買されている。「アート 写真が急速にその実体を現しはじめたのは1990年代に入ってからのことだ」と著者は書く。どうしてその頃に表に出てきたかは触れてないが、「実体を現し はじめた」という言い方は、ふたつのことを暗示しているように思われる。ひとつは「アート写真」という概念の登場によって従来の写真表現にそれまでとはち がう光が当てられたこと、それによってギャラリー展示にフィットする写真のあり方を模索する写真家が出てきたことである。
写真には本来決まったサイズがない。それが絵画との大きなちがいである。引き伸ばし機によって大きくも小さくも作れるし、一部をブローアップするこ ともできる。カテゴリー3の写真群は、そうした写真の融通無碍な特質をむしろ制御する動きと言えよう。最初からサイズを決めて撮影に入る写真家もいる。つ まりタブローに対するのと同じ態度で制作するわけで、それだけが理由ではないにせよ、美術館やギャラリーの空間が創作のプロセスを変化させたことはまちが いないだろう。
カテゴリー1の行為を記録した写真は、60〜70年代のコンセプチュアルアートの記録写真から派生したものだと著者は言う。パフォーマンスアート華 やかなりし頃は行為そのものが重要視され、写真は付随的なものにすぎなかった。だが、写真が作品として流通する制度と市場の成立により、作品の最終形とし て写真の比重が増してきたのではないだろうか。かように写真の存在は曖昧でゆらぎやすく、文脈によって立ち位置が変化する。かつて「日和見主義」というこ とばが揶揄的に使われたことがあったが、写真はまさに「日和見」的な性格をその本質に抱えもっていると言える。
ものの典型であるのがわかる。
写真と言葉の関係という古くて新しいテーマについても考えなくてはならないだろう。たとえばカテゴリー2のタブロー的写真では、作られたシチュエー ションで撮ったものと、まったく手を加えていない現実場面を撮った作品とが紹介されている。写真がもたらす印象はどちらもドラマチックで映画のワンシーン のようだが、その現場が演出されたものかどうかという情報は作品は含み込まれるのだろうか。こうしたタブロー写真の創作プロセスをどうとらえるのか、もっ と突っ込んで語られてもいいように思う。
テーマに分けて論じた本書は、写真によって世界を編集しているかような写真表現の現在をあぶり出している。写真には世界を可視化しようという欲望が あり、実際ありとあらゆるものがとらえられてきた。とくに小型カメラが一般に普及したと1950年代、60年代、写真家はコンセプトなしに目にするすべて のものを写真に収めようという無邪気な興奮に燃えた。それが過ぎ去ったあとにやってきたのが「現代写真」の時代であり、それぞれがテリトリーを決め、欲望 の一部を分担し、見せ方を考えて世界を再編集しているように見える
「本書では、最終的にはコンテンポラリーアートとしての写真は自律的なものであると考えており、写真の歴史を通してのみ考えうるという立場はとって いない」と著者は書く。だが「自律的」という印象はあまり受けないのである。70年代の「現代美術」がそうだったように、「現代」と名のつくものはある文 脈の上に成り立っているが、おなじように「現代写真」も美術の文脈の上に咲いた花のように思えてならない。
日本の写真家の作品も数人挙がっているが、あくまでも欧米の写真の動向にそって紹介されている。そのなかでいちばん年長なのは荒木経惟だ。「モダニ ズムが絵画や彫刻に匹敵する写真家の殿堂を作り上げようとした一方で、ポストモダンはそれとはことなる立ち場から写真を捉えていた。すなわち、写真という メディアを、制作、伝達、受容という観点から検証し、写真が本来持っている複製可能性や模倣性、虚偽性に注目したのである」。これはカテゴリー7のリメイ ク写真についての解説だが、70〜80年代に荒木がやってきたことの説明とも読めてしまった。それほど彼の写真活動は多岐にわたり、この本に登場する現代 写真のほとんどを試みてきたと言っても過言ではない。
だが彼および彼より上の日本の写真家たちは写真を「アート作品」とみなすことに違和感をもち、「タブローとちがう」点に写真の特質を求めようとし た。「写真とはなにか」を切実感をもって自問したのだった。だが、90年代以降の「現代写真」を見るのにそうした問いは不要である。むしろ理解のさまたげ になるだろう。こうした問いを無意味なものにするほど、欧米の「現代写真」に制度的な強さがあったということだろうか。
日本の戦後写真には欧米の影響をほとんど受けずに独自に進んできたおもしろさがある。そのことを主張する視点が日本の写真界に欠けているのを残念に 思う。これは写真家ではなく、評論家やキュレーターの課題なのだ。
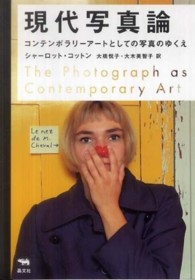
0 件のコメント:
コメントを投稿