2010年06月08日
『ナマコを歩く−現場から考える生物多様性と文化多様性』赤嶺淳(新泉社)
今年10月に名古屋で、生物多様性条約第10回締約国会議が開催される。「ラムサール条約やワシントン条約などの特定の地域、種の保全の取組みだけでは 生物多様性の保全を図ることができないとの認識から、新たな包括的な枠組みとして提案」された「生物の多様性に関する条約」は、1992年に採択され、翌 年発効して、2009年末現在、193の国と地域が締結している。その3つの目的は、「地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること」、「生物 資源を持続可能であるように利用すること」、「遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること」である。
本書の副題には、この「生物多様性」とともに「文化多様性」があり、著者、赤嶺淳は、その関係性について「終章 生物多様性の危機と文化多様性の保全」 の最後の節で、つぎのように私見を述べている。「人間の営為を再評価することにより、圧倒的な存在感を誇る熱帯雨林も、都会の片隅に追いやられている里山 も、貴賤なく、平等に人類の遺産となりうる」。もうひとつの副題のキーワード「現場から考える」は、地球環境主義の下に開催される国際会議で、あまりに現 場を無視した(知らない)議論が展開されていることへの著者の怒りが表れている。著者は、「生活しているという現実をかえりみるとき、たんなる科学的な見 地から環境問題を論じるのは無責任にすぎる、とする立場にある」。
本書でもうひとつ重要なキーワードは、「保全」である。著者は、このことばに関連してつぎのように説明している。「日本語の「保護」には、保全 (conservation)と保存(preservation)のふたつの意味が混在している[略]。後者はともかく、前者は日常生活で耳にすることの 少ないことばだし、両者を区別していない日本語辞書もあるが、両者には人間の介在度において決定的な差異がある。保全は動詞としてconserve water(水を節約しましょう)やconserve energy(省エネしましょう)などと使用されるように、人間による利用を前提とし、「無駄なく利用」することを含意している。他方、保存は食品保存料 (preservative)と同幹のpreserveからの派生語で、preserve historic landmarks(史跡を保存する)というように、なにかに壊されたり、傷つけられたりしないように原型を維持することを意味する。つまり、人間の介在 をできるだけ排除することが前提とされているのである」。問題は、この人間の介在度が、人によって、状況によってさまざまで、なにを共通の前提として議論 すればいいのかわからないことである。
著者は、「本書では、自然と人間、あるいはグローバル・コモンズと地域社会の関係を考える一事例として、中国食文化圏で少なくとも四〇〇年にわたり珍重 されてきた「ナマコ」を取り上げ、野生生物の利用と管理の問題点を検討してみたい」といい、ナマコに着目する4つの理由を述べている。さらに、具体的につ ぎのように希望している。「本書では、ナマコという野生動物をめぐって、資源利用者の漁民、資源管理の枠組みづくりの主体としての国家や国際機関、さらに は豊富な活動資金のもとボーダーレスに環境保護運動を推進する環境NGOらが、さまざまに入りみだれて関係しあう動態を「エコ・ポリティクス」とよび、ワ シントン条約という野生生物の国際貿易を規制する条約を舞台として展開されるエコ・ポリティクスの様相を検討してみたい。同時に野生動物の保全は、資源利 用を含んだ地域社会と食文化の歴史性をふまえ、生産者のみならず流通業者など、さまざまな関係者を巻き込んだ、外部にひらかれた体制が望ましいことを提示 したい」。
1997年以来、ナマコ調査のために世界を飛びまわった著者の成長ぶりは、「終章」で語られている。「好事家的な事象ばかりに眼を向け、グローバルな視 野をもとうとしなかった自分の研究姿勢」に変化をもたらしたのは、ある研究会で「文系の研究発表は、なるほどなぁ、と問題の分析視覚に驚かされるし、勉強 にもなる。しかし、そのような分析をもとに、どのような助言を漁業者におこなえばよいのでしょうか」と質問されたことだった。それから、著者は、「ナマコ 調査の際に漁業者や加工業者から一方的に情報を得るだけではなく、わたしが手持ちの情報を意識的に提供し、調査を情報交換の場としてきた」。
著者は、20年前に『ナマコの眼』という名著を著した鶴見良行のアジア学を継承するひとりで、「ナマコという商品に着目して、過去四〇〇年ほどのアジア 史のダイナミクスをとらえなおすことが、わたしの目下の研究課題であり、本書も、その作業の一環である」と、「未完のアジア学を継ぐ」スケールの大きな課 題に挑戦している。
鶴見良行のアジア学は、歴史学など東南アジアの基礎研究の発達と無縁ではなかった。欧米などの文書館での原史料の読解に基づく研究成果が出てくるように なり、1970年代には日本人研究者によって書かれた東南アジアの通史が読めるようになった。しかし、これらの机上の研究者が東南アジア現地を訪れ、調査 するための研究費も時間的余裕もなかった。したがって、長期間現地を歩き、肌で感じたさまざまな問題を論じた鶴見の著作は、けっして机上の学問ではわから ない人類の将来の問題を含めて、臨場感をもって伝え、魅力にあふれていた。しかし、根拠をあげることなく語られる「物語」は、大枠では正しいのであろう が、個々には基礎的間違いがあり、疑問も呈された。
著者もその鶴見のアジア学の魅力にとりつかれたひとりで、本書はその長所を活かし、欠点を克服しようとした成果である。その試みはみごとに成功し、それ を祝福するかのように門田修の写真が本書を飾っている。だが、ひとつ危惧がある。鶴見が基礎研究の成果を利用することによって、基礎研究では語れないこと に挑戦したように、本書のような現場から考える研究は、基礎研究との相乗効果によって発展する。その基礎研究が、いまの日本の東南アジア研究では充分でな いように思える。文献史学のような基礎研究は、考証した原史料を丹念に読んで、その背後にある時代や社会を理解したうえで、虚実ない交ぜの記述を考察・分 析する。関係する史料の一部だけを取り出して、都合よく自分の論旨にあてはめるようなことはしない。「未完のアジア学を継ぐ」ためにも、基礎研究の発展は 不可欠だろう。
本書の副題には、この「生物多様性」とともに「文化多様性」があり、著者、赤嶺淳は、その関係性について「終章 生物多様性の危機と文化多様性の保全」 の最後の節で、つぎのように私見を述べている。「人間の営為を再評価することにより、圧倒的な存在感を誇る熱帯雨林も、都会の片隅に追いやられている里山 も、貴賤なく、平等に人類の遺産となりうる」。もうひとつの副題のキーワード「現場から考える」は、地球環境主義の下に開催される国際会議で、あまりに現 場を無視した(知らない)議論が展開されていることへの著者の怒りが表れている。著者は、「生活しているという現実をかえりみるとき、たんなる科学的な見 地から環境問題を論じるのは無責任にすぎる、とする立場にある」。
本書でもうひとつ重要なキーワードは、「保全」である。著者は、このことばに関連してつぎのように説明している。「日本語の「保護」には、保全 (conservation)と保存(preservation)のふたつの意味が混在している[略]。後者はともかく、前者は日常生活で耳にすることの 少ないことばだし、両者を区別していない日本語辞書もあるが、両者には人間の介在度において決定的な差異がある。保全は動詞としてconserve water(水を節約しましょう)やconserve energy(省エネしましょう)などと使用されるように、人間による利用を前提とし、「無駄なく利用」することを含意している。他方、保存は食品保存料 (preservative)と同幹のpreserveからの派生語で、preserve historic landmarks(史跡を保存する)というように、なにかに壊されたり、傷つけられたりしないように原型を維持することを意味する。つまり、人間の介在 をできるだけ排除することが前提とされているのである」。問題は、この人間の介在度が、人によって、状況によってさまざまで、なにを共通の前提として議論 すればいいのかわからないことである。
著者は、「本書では、自然と人間、あるいはグローバル・コモンズと地域社会の関係を考える一事例として、中国食文化圏で少なくとも四〇〇年にわたり珍重 されてきた「ナマコ」を取り上げ、野生生物の利用と管理の問題点を検討してみたい」といい、ナマコに着目する4つの理由を述べている。さらに、具体的につ ぎのように希望している。「本書では、ナマコという野生動物をめぐって、資源利用者の漁民、資源管理の枠組みづくりの主体としての国家や国際機関、さらに は豊富な活動資金のもとボーダーレスに環境保護運動を推進する環境NGOらが、さまざまに入りみだれて関係しあう動態を「エコ・ポリティクス」とよび、ワ シントン条約という野生生物の国際貿易を規制する条約を舞台として展開されるエコ・ポリティクスの様相を検討してみたい。同時に野生動物の保全は、資源利 用を含んだ地域社会と食文化の歴史性をふまえ、生産者のみならず流通業者など、さまざまな関係者を巻き込んだ、外部にひらかれた体制が望ましいことを提示 したい」。
1997年以来、ナマコ調査のために世界を飛びまわった著者の成長ぶりは、「終章」で語られている。「好事家的な事象ばかりに眼を向け、グローバルな視 野をもとうとしなかった自分の研究姿勢」に変化をもたらしたのは、ある研究会で「文系の研究発表は、なるほどなぁ、と問題の分析視覚に驚かされるし、勉強 にもなる。しかし、そのような分析をもとに、どのような助言を漁業者におこなえばよいのでしょうか」と質問されたことだった。それから、著者は、「ナマコ 調査の際に漁業者や加工業者から一方的に情報を得るだけではなく、わたしが手持ちの情報を意識的に提供し、調査を情報交換の場としてきた」。
著者は、20年前に『ナマコの眼』という名著を著した鶴見良行のアジア学を継承するひとりで、「ナマコという商品に着目して、過去四〇〇年ほどのアジア 史のダイナミクスをとらえなおすことが、わたしの目下の研究課題であり、本書も、その作業の一環である」と、「未完のアジア学を継ぐ」スケールの大きな課 題に挑戦している。
鶴見良行のアジア学は、歴史学など東南アジアの基礎研究の発達と無縁ではなかった。欧米などの文書館での原史料の読解に基づく研究成果が出てくるように なり、1970年代には日本人研究者によって書かれた東南アジアの通史が読めるようになった。しかし、これらの机上の研究者が東南アジア現地を訪れ、調査 するための研究費も時間的余裕もなかった。したがって、長期間現地を歩き、肌で感じたさまざまな問題を論じた鶴見の著作は、けっして机上の学問ではわから ない人類の将来の問題を含めて、臨場感をもって伝え、魅力にあふれていた。しかし、根拠をあげることなく語られる「物語」は、大枠では正しいのであろう が、個々には基礎的間違いがあり、疑問も呈された。
著者もその鶴見のアジア学の魅力にとりつかれたひとりで、本書はその長所を活かし、欠点を克服しようとした成果である。その試みはみごとに成功し、それ を祝福するかのように門田修の写真が本書を飾っている。だが、ひとつ危惧がある。鶴見が基礎研究の成果を利用することによって、基礎研究では語れないこと に挑戦したように、本書のような現場から考える研究は、基礎研究との相乗効果によって発展する。その基礎研究が、いまの日本の東南アジア研究では充分でな いように思える。文献史学のような基礎研究は、考証した原史料を丹念に読んで、その背後にある時代や社会を理解したうえで、虚実ない交ぜの記述を考察・分 析する。関係する史料の一部だけを取り出して、都合よく自分の論旨にあてはめるようなことはしない。「未完のアジア学を継ぐ」ためにも、基礎研究の発展は 不可欠だろう。
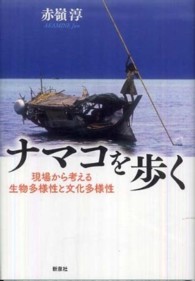
0 件のコメント:
コメントを投稿