2012年07月30日
『青い絵具の匂い—松本竣介と私』中野淳(中公文庫)
著者と竣介との出会いは昭和18年、「新人画会展」というグループ展に出品されていた作品がきっかけだった。この在野の展覧会は、美術展といえば戦争画一色となっていた当時、時局の風潮に屈せず、描きたい絵を描こうという作家たちの集まりによるものだった。
朝日新聞の一面に大きく藤田嗣治、中村研一、宮本三郎ら有名画家たちの戦争画の写真が掲載され、戦争画展開催の報道が連日つづ いて、厖大な観客が動員された。その是非は別として、現存作家による美術と大衆がされほど融合した例は稀である。混雑した美術館の会場では主要作品の脇に 「天覧」と大書され、私たちは当然のこととして戦争画を脱帽して見ていたのである。そうした大作の描写の迫真性やユニークな構想に当時は素朴に驚嘆したも のだった。
ただ私自身は戦争画を制作する能力などない画学生に過ぎず、裸婦や着衣像を習作している日々だったが、自身やがて兵隊にとられ死地に赴くことを考えると、もっと自由で知的な絵画世界に憧れていたというのが真情だったろうか。
知り合いのつてで竣介と面会した著者は、以来、描きためた絵を携えては松本家のアトリエを訪れるようになる。
翌19年、著者は絵を描くことに熱中するあまり、徴兵検査の日を忘れてしまう。家族にも友人にも告げられずにいたこの失態を、竣介には打ち明ける こができた。「驚いたな。検査を忘れたといっても、君は兵役拒否なんて考えてるわけではないんだろ?」と、竣介が取り出してきたのは美術雑誌『みづゑ』で あった。太平洋戦争開戦の昭和16年、同誌に掲載された軍人たちによる座談会「国防国家と画家」への、竣介の反論「生きている画家」が発表された号であ る。
生活や時代へのまなざしのきびしさ、思考の深さといった松本さんの画家としての精神の深淵に、私は会うたび魅きつけられていっ た。磊落な画家の側面しか感じなかった私も「生きている画家」読後、はじめて松本さんの捨身の信念を知ったし、人間性を肌に感じて信頼感を増していったよ うだ。戦時下だかこのアトリエでは何でも喋れると思った。
既成の思想や宗教に一定の距離をおき、自ら考え信ずるところに拠ってのみ、静かに筋を通して描き、そして生きた人。育ちがよく、頭も勘もよく、耳 が聞こえないという障害にも屈せず、人柄も円満でと、まるで非の打ち所のない人。もうほとんど聖人のような扱いをされている松本竣介だが、その、未熟な者 を侮らず、また自らを押しつけることもしない対しかた、こだわりなさもすてきだ。
戦局が激しさを増し、もはや「絵どころではない」状況、画友たちは次々と兵隊にとられてゆく。そんななか、自らの失態に心を重くし、ただ絵を描くしかなかった十代の著者にとって、この出会いはいかほどのものだったろうと思う。
20年3月10日の東京大空襲で、著者の住まう江戸川区一帯も焦土と化した。戦火をくぐり抜けた著者は家族共々神奈川の親戚の家に仮寓することになるが、危険を承知でたびたび上京し、竣介の元を訪れた。
同じ画家の眼からみた竣介とのエピソードには、絵画技法についての記述が多い。竣介を知るきっかけとなった絵(「運河風景」、現在は「Y市の橋」 というタイトルになっている)については、「強固なマチエール」や「透明な画面」、そこに走るさまざまなニュアンスの線に見惚れ、「まさしく詩と造形の合 体。精神の職人による絵だ」とある。
当時、油絵の技法書は少なく、古典技法や絵画組成を教える施設は美術学校、研究所に全くなく、西欧絵画に触れる機会も少ない。 多層性のグラッシ法(透明描法)の卑近な実例を私は戦争画、特に藤田嗣治の絵になかに見たが、この人だけは紛れもなく油絵技法の深奥を体得していると思っ たので、あるとき松本さんにそのことを筆談で訊いてみた。
「君はグラッシ法とかマチエールとか専門的な用語をどこで覚えたのか知らないが、そういうことは二義的に考えて、いまは基礎的な写実の勉強を身につけるべきだな」 とたしなめながらも、グラッシ法の実際について平明に語ってくれた。下塗りの必要性から始まり、単色による中塗りとマチエールの調整、仕上げ段階での透明色の選択など、松本絵画の方法論を具体的に語りつづける口調は、次第に熱気をおびていった。
絵画様式の変遷についての本はたくさんあっても、技法についての情報はまだまだ貧しかった当時、留学経験もない松本竣介は「おそらく持ち前の勘の良い手業と不備な技法書ほ手掛かりに、暗中模索の手さぐりで、それらしい効果に到達したのではあるまいか」と著者はいう。
アトリエを訪ね、その仕事を垣間見るなかで著者は油絵のさまざまを竣介から学んだ。ペンや筆に凝らした独自の工夫、裏に墨を塗ったガラス板に映った顔をもとに自画像を描くこと、乏しい色数のなかでも豊かな色相が作れること。
「……それから僕は下塗りをしっかりする。絵具の発色を良くしたり、好みのマチエールを望むこともあるが、作品を後世に遺すこ とを考え、耐久性を強くする為だ。作画中は何回も透明色を塗って、美しい色彩の画面をつくり、たとえば空襲でやられて断片だけが残ったとしても、その断片 から美しい全体を想像してもらいたいのだ」
著者によれば、藤田嗣治も戦争画についての文章で、同じようなことを書いていたらしい。それにしても、美というものへの信念だけでなく、作品の物質として堅牢さへこのこだわりの強さには恐れ入る。
以前とりあげた近藤祐『洋画家たちの東京』は、青木繁、村山槐多、関根正二など、夢と野心をもって上京し、自己顕示欲のかたまりような、破天荒な 生きざまをみせた彼等の足跡が描かれていたが、そんななかでただひとり、彼らとは対照的な「勤勉な努力家であり、性格破綻の欠片もない良識人」として、最 後にとりあげられていたのが松本竣介だった。
無頼な暮らしぶりの画家たちのなかでは、お行儀が良く、すべてにおいてバランスのとれた竣介のようなタイプはむしろ異質だろう。しかし、描くこと に対する信念の深さと強さは並大抵のものではない。同時代の画家たちが、キャンバス上に自己の表出を定着させることにのみとらわれがちであったなかで、彼 は彼独自の絵画への強い意志を貫くべく、入念に画面を造り上げていったのだ。
詩情にあふれているとか、透明感があるとか、静謐であるとか、竣介の絵はさまざまに表現されるけれど、そこにはなにか、情緒的なものだけに流され ない動じなさ、すこやかさのようなものが感じられる。それはひとえに、著者が垣間見た竣介の画面造りにたいするあのひたむきな姿勢によるのかもしれない。
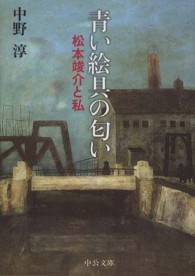
0 件のコメント:
コメントを投稿