2012年06月30日
『言葉を生きる』片岡義男(岩波書店)
片岡義男は実に不思議な作家だ。言葉の操り出し方、思考の進め方に独特のスタンスがある。その視野の広がりといい、どこにも帰属しない孤高性といい、既存のジャンルにとらわれない書き方といい、ほかに例を見ない。
とはいうものの、最初からそうとわかったわけではなく、長いこと自分には遠い作家だと思っていた。オートバイ、クルマ、美女、海、サーフィン、ハワイなど、彼の小説がもたらすイメージが障壁になり、愚かにも読もうさえしなかったのだ。
ところが、あるときふと、相当に変わった作家なのではないか、と思いはじめた。ほかの作家ならやらないようなことをたくさんおこなっている。まず驚 くのは興味の範囲の広さで、それを自在に文章に表している。自分の書いた小説に解説をつけたり、自分で自分にインタビューしたりもしている。写真も撮り、 東京をスナップした写真でいくつもの写真集を編んでいるし、蔵書や文房具をブツ撮りした本も出している。だれもやらなかったことを、何のためらいもなくつ ぎつぎと実行していく片岡義男とは、いったいどういう人物なのか、と気になり出したのだ。
自分を発動させる原理のようなものが彼のなかにあるようだ。その原理とアイデアが組み合わさると即実行となる。その原理とは何なのか、それはどのように生成されてきたのか、そうした疑問への回答として、『言葉を生きる』は実に興味深い読書だった。
ハワイ生まれの日系二世を父に、近江八幡生まれの母とのあいだに生まれた少年が、ものを書く人になる過程が描かれていく。ジャンルに分けるなら評論 とかエッセイとなるのだろうが、読んでいるときの感覚は小説に近い。片岡義男の小説は小説についての評論であり、評論こそが小説である、と看破したのは堀 江敏幸だが、まったくそのとおりで、私小説的な奥行きが感じられた。
日系二世の父親は英語を話し、母は終生関西弁で通したが、赤ん坊のときについた若い乳母は彼に東京弁で語りかけた。戦争が激しくなると父の故郷の岩国に疎開し、戦後もしばらく留まったが、そこでは瀬戸内の言葉が飛び交うなかで暮らした。
そうした複雑な言語経験と、彼の物の考え方や文章を書く態度や方法論は緊密に絡み合っている。欧米ではそういう背景をもった作家はよくいるが、日本では珍しく、その意味でも希有な作家だと改めて思った。言語が影響した例としてこんな一節がある。
「「拾った」という日本語のひと言を、自分の日本語のなかで、じつは僕は使うことが出来ない」。
えっ、と声をあげてしまうほど思いがけなくも新鮮な指摘だが、その理由について、彼は明晰に語る。「拾う」というのは、拾う人の感情や心理と密接な 関係にある日本語だ。「拾う」ためには「落ちている」という認識がそれに先立つものとしてあり、そのことが「拾う」という言葉に単なる行為以上の意味を背 負わせている。「どうせ拾った恋だもの」「思わぬ拾いもの」「拾いものにろくなものなし」「いまの会社に拾われた」などの表現がそうだ。
それならば、小説のなかでひとりの女性が海岸で貝殻を拾うとき、片岡義男はどのように書くのだろうか。
「なにも束縛されることなく、ほとんど自動的に書いているようなときにこそ、彼女はしゃがんで片手をのばし、その貝殻を指先でつまみ取った、というような書きかたを僕はするにきまっている」
つまり「拾う」と書く代わりに、英語のpick upに当たる言葉を体の動きに分解して使うのだ。日本語に距離を保とうとする意志がそうさせる。その意志は英語から来ている。英語の原理が彼の日本語を監視し、安易に一体化することをゆるさないのだ。
「僕の日本語のすぐかたわらにあり続けながら、その日本語によって僕が漂流しないよう明確につなぎとめておく機能を、英語という言葉は僕に対して発揮することになった」。
チェコ語と英語で育った人が、英語を使うときにチェコ語の監視を受けるということがまったくないとは思わないが、ヨーロッパ言語間では監視力はそれほど強くないと思う。日本語と英語が異なる論理をもつことが大きいだろう。
さらに言うなら、生まれ落ちた瞬間にその複雑な言語体系のなかにいたことも、関係しているだろう。ひとつの言葉に安住できる環境ではなかったのだ。 「拾う」という言葉について、彼の逆のケースとして、日本語のうまいアメリカ人の場合はどうかと考えてみる。アメリカ人の彼が「わたし、彼女に拾われたん です」と日本語で言いながら、日本人の奥さんを紹介する場面というのは容易に想像できる。それを聞いた日本人は笑いながら、彼が日本語にいかになじんでい るかに感心するだろう。
大人になって自分の意志で日本語を学んだのならば、そういう軽みを実演することは、キャラクターにもよるがさほどむずかしくはない。日本語の論理に 身を浸すことに、むしろゲーム感覚的なおもしろさを見いだすかもしれない。彼のなかに英語というたしかな陣地があるから、他者の陣地に出向くのにためらい がないのだ。
だが、幼いときから二重言語を体験してきたなら事情はちがってくる。陣地は最初からないも同然だった。ないなら作るしかないと、彼はどちらの言語からも距離をとり、その外側に独自の言語空間を作り出す道をとったのだった。
片岡義男の文章につきまとう日本語としてのこなれの悪さは、そこから来ている。私は浅はかにも単なるスタイルだと思っていたし、しかもそれをまねた文章が横行していたから、余計に距離をとりたくて敬遠したのだったが、スタイル以前の必然がそこにはあったのである。
彼には『日本語の外へ』という分厚い大著があるが、「外へ」というのは片岡義男を貫いている態度である。内側に留まるのは居心地が悪く、外に立って 自分との位置をはからずにはいられない。どこかに帰属することなどもってのほかで、何事においても外から観察し測定しようとする意志を発揮する
外から観察すると言ったが、境界線に立ってただ物事を眺めているような傍観者のイメージが彼にはないのである。諦観は強いと思うが、「いま現在」に情熱を注ぐ行動の人であることは、多岐にわたる彼の著作を見ればすぐにわかることだ。
片岡がはじめて夢中になって読み通したペーパー・バックはベス・ストリータ・オルドリッチというアメリカの女性作家の書いた『彼女は角灯を手に』と いう小説だったという。この小説との出会いそのものが、まさしく小説的におもしろいのだが、それについては読んでいただくとして、その小説の女主人公ア ビー・マッケンジーについて触れている箇所を書き出してみたい。
「自分自身への尽きることのない驚き、そしてその自分がいつのまにか作り出す新たな挑戦の対象などに対して、彼女は最後まで驚き続けた。いったいな にが自分なのかという問いを、アビー・マッケンジーは最後の最後まで、真剣に追いかけた。波瀾万丈のパイオニア物語をその裏で支えたのは、いったいなにが 自分なのか、という永遠の問いかけだった」
この言葉はそのまま片岡義男という作家にあてはまる。いったいなにが自分なのか、という問いが彼のなかにも潜んでいる。どこかにあるはずの自分を探 すのではない。いったいなにが自分なのか、と自分という概念そのものを問い詰めるのだ。彼の執筆活動を前へと押し進めているのはその問いへの希求であり、 その推進力を彼は英語の言語空間から学びとったのである。
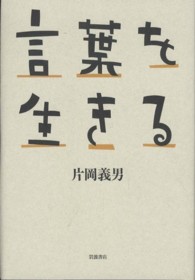
0 件のコメント:
コメントを投稿