2010年10月04日
『ならず者たち』デリダ,ジャック(みすず書房)
「デリダの理論の深みをうかがわせる」
帯によるとデリダの「晩年の主著」である。この書物は二つの講演で構成される。一つはスリジィの恒例の一〇日間にもおよぶ講演とセミナーでの長文の記録「強者の理性--ならず者国家はあるか」であり、もう一つは「来るべき啓蒙の〈世界〉--例外、計算、主権」である。最初の講演ではデリダは、アメリカ合衆国が一部の諸国を告発するために使った「ならず者国家」という概念をとりあげて、そのいかがわしさを暴き出す。こ こまではチョムスキーと同じだと思われるかもしれないが、問題は政治的なものに限られない。主権と理性の問題であり、生の自己保存としての免疫と、それが 生そのものを滅ぼしてしまう自己免疫、「死の欲動」(p.299)の問題でもある。アクチュアルな政治的な問題を哲学の根本問題にまで引き戻す手腕は、ア ガンベンとデリダの二人の思想家の際立ったところだろう。
第二の短い講演では、時間的な制約もあって、デリダは「電報的でも綱領的でもある」(p.293)形で、これまで論じてきたさまざまな問題を要約 的に、手際よく提示する。その要約の巧みさのために、読者は目がくらくらするところもあるが、逆に引用に耐える短い文章も多い。第一論文では時間の余裕が ありすぎて(デリダはそれでも足りない、足りないと言い続けるが)、迂回路をたどる時間が長すぎるので、引用できるところはあまりない。この迂回が楽しい のもたしかであり、デリダのセミナーは楽しかっただろうと想像する。
書評では電報的なものをさらに印象批評的に取り上げることしかできないのは残念だ。最初の論文では、民主主義が自己免疫を引き起こし、自殺する寸 前にいたる事例を考察する。何よりも範例的なのは、アルジェリアだ。民主主義を否定するイスラームの政党が民主的な選挙で圧勝することが確実になった時点 で、軍がクーデターを起こし、選挙を無期延期したのだ。
これは「民主主義の名における、民主主義に対するあらゆる侵害の典型的な出来事」(p.74)と言えるだろう。アルジェリア政府は、「開始された 選挙過程は、民主的に民主主義の終焉に導くだろうと考えた。そこで彼らは、みずから民主主義を終焉させることの方を選んだのである。彼らは主権的に決定し たのだった、民主主義を、民主主義にとって善いことのために、そしてその手当てをするために、最悪の、もっとも街全体の高い侵害に対してそれを免疫化する ために、少なくとも暫定的に停止することを」(同)。これは「自己免疫的な自殺」(p.75)だった。
電報的な第二論文から自己免疫の簡単な定義を復習しておこう。「ある生体の中で、他者の攻撃的な侵入に対する免疫を当の政体に与えているもの、ま さに当の主体が自発的に破壊しうる」(p.234)ことである。民主主義を守るために民主主義を殺すアルジェリア、主権を守るために主権の根源となるもの を殺すクーデター、ならず者国家を攻撃するという名目で、みずからならず者国家となるアメリカ合衆国。アメリカ行政府は、「悪の枢軸」に対抗すると称し て、民主的な自由を「不可避的に、また否認不可能な仕方で制限しなくてはならない。そして、それに対しては誰も、どんな民主主義者も本気で反対することが できない」のである(p.86)。
それだけではない。「もっとも暴力的なならず者国家、それは、みずからその第委任者と自称する国際法を、みずからその名のもとに語り、みずからそ の名のもとに、いわゆるならず者国家に対する戦争を開始する国際法を、みずからの利害が命ずる場合には毎回無視して来た国、侵犯し続けている国、すなわち アメリカ合衆国である」(p.189)。
そしてアメリカ合衆国と同盟する国も、これに対抗する国も、すべての国も国益の名において、主権の至高性の名において、国家理性の名のもとで、同 じように振る舞うのであるから、「もはやならず者国家しかなく、そしてもはやなず者国家はない。この概念はその限界に」(p.205)到達したのであり、 「この終焉はつねに、初めから、近かったのである」(同)。なおデリダはこの主権性の理論の背後にキリスト教の神学が存在することを示唆する。「民主的と 呼ばれる体制においてさえ、主権の根底には存在−神論がある」(p.299)。しかしこの論文ではそこまでは議論は進められない。
ところで自己免疫は、もっと普遍的な形で言い換えれば、アポリアでもダブルバインドでもある。「アポリア、ダブルバインド、および自己免疫的過程 は、単なる同義語ではないけれども、それらはまさしく共同に、そして負担=責任として、内的矛盾以上のもの、決定不可能性を、……内的アンチノミーをもっ ている」(p.78)のである。この概念は、ここまで敷衍してしまうと、何にでも使える便利な道具のようになってしまうのはたしかだ。
後は電報的にいくつか。デリダはクローニングを好まないが、治療的なクローニングは否定する根拠がないと考える。それはそもそもすべての個別性に は反復という要素が不可避的に存在しているのであり、それを無視して個性の貴さを、一つの生命の特異性をうたっても空しいからだ。「反復・複製は、生産・ 再生産とまったく同じように、文化・知・言語・教育の条件を保証しているのである」(p.278)。人間の特異性に基づくクローニング反対論は、「遺伝子 主義ないし生物学主義を、つまりは根深い動物学主義、根底的な還元主義を、みずから反対しているはずの公理系と分かち合っている」(同)ことになる。
しかし自己免疫が絶対的な悪であるわけではない。出来事がその名に値するものであるならば、「出来事は、絶対的な免疫も何の補償もなしに、自らの 有限性のなかで地平なしに、剥き出しの傷つきやすさにふれなければならない。その場合には、他者の予測不可能性に対峙して立ち向かうことは依然としてでき ない、あるいはもはやできないのである。その点からみれば、自己免疫性は絶対的な悪ではない。自己免疫性は対象にさらされること、すなわち到来することの ないものない者に、したがって計算不可能にとどまるほかないものに、さらされることを可能にするからだ。もし絶対的な免疫性があるばかりで自己免疫性がな いとしたら、もはや何も起こらないだろう」(p.290)。レヴィナスのアレルギーの議論と通底して、デリダの理論の深みをうかがわせる境地である。
【書誌情報】
■ならず者たち
■デリダ,ジャック【著】
■鵜飼哲、高橋哲哉【訳】
■みすず書房
■2009/11/20
■327p / 19cm / B6判
■ISBN 9784622073734
■定価 4620円
●目次
一 強者の理性(ならず者国家はあるか?)
1 自由な車輪
2 放縦と自由—悪知恵に長けた=車裂きにされた者
3 民主制の他者、代わるがわる—代替と交代
4 支配と計量
5 自由、平等、兄弟愛、あるいは、いかに標語化せざるべきか
6 私が後を追う、私がそれであるならず者
7 神よ、何を言ってはならないのでしょう?来たるべきいかなる言語で?
8 最後の/最低のならず者国家—「来たるべき民主主義、二回回して開く
9 ならず者国家、より多く/もはやなく
10 発送
二 来たるべき啓蒙の「世界」(例外、計算、主権)
1目的論と建築術—出来事の中性化
2 到来すること—国家の(そして戦争および世界戦争の)諸々の終焉に
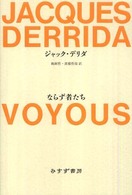
0 件のコメント:
コメントを投稿