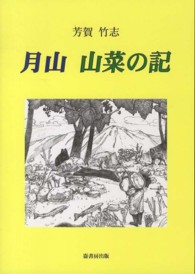2013年03月25日
『小商いのすすめ―「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ』平川克美(ミシマ社)
「経済成長」と「縮小均衡」
私は1960年代から70年代の初めにかけて10歳までの子供時代を過ごした世代なので、まさに高度経済成長時代の申し子といってもよい。一昨年、総合 雑誌『中央公論』が「私が選ぶ『昭和の言葉』」という特集を組んだとき、私も何か書いてほしいと依頼されたのだが、正直に最初に脳裏に浮かんだ「昭和元 禄」という言葉を選んだ。短い文章なので、それを最初に読んでもらうことにしよう。「私が生まれたのは、昭和37(1962)年である。日本が『高度成長の時代』を突っ走っていた頃と言ってもよい。私の専門は経済学だが、私よりも もっと上の世代のなかには、河上肇の『貧乏物語』(1917年)を読んで社会意識に目覚め、経済学を志したという碩学が少なくない。残念ながら、私にはそ れに似たような経験はない。幼い頃の思い出のなかで今でも鮮明に記憶に残っているのは、両親や兄弟と一緒に東海道新幹線(昭和三九年開通)に乗って上京 し、東京タワーや霞ヶ関ビルの一番上にのぼり、そのあと銀座の歩行者天国で楽しいひとときを過ごしたことである。家族で旅行することはよくあったが、東京 タワーの上から眺めた東京の街は格別であった。しかし、『高度成長の時代』でなければ、そもそも私たちの家族旅行はあり得なかった。
長じて、経済学を勉強するようになってから、実は、『高度成長の時代』にも、水俣病に代表される公害(環境破壊)などの『影』の側面があり、ある段階ま で、政府も国民もその問題をそれほど深刻に考えなかったことを知った。それでも、現在でも、私たちは、『高度成長の時代』の思考法から決して抜け切っては いない。それは、四半期ごとに発表されるGDPの指標にいまだに一喜一憂していることからも明らかである。GNPやGDP至上主義への疑問は、古くはE・ ミシャンや都留重人から現代のアマルティア・センに至るまで、何度も表明されてきたので、『脱成長』時代の経済システムの再構築にとうにとりかかっている べきなのだが、いまだに成長路線への復帰こそが増収をもたらすので、消費税の増税は必要ないという論説が一部に受けがよいようである。一度みた夢は忘れら れないものなのか、そんなとき、天下太平の時代を見事に表現した福田赳夫の『昭和元禄』という言葉を思い起こすが、当の福田は安定成長論者として池田勇人 と対立したというのだから皮肉なものである。」(『中央公論』2011年6月号、163ページ)
私よりもっと上の世代は、それこそ悲惨な戦争時代を思い起こさせるような言葉を選んでいる人たちもいたが、物書きとして嘘は書けないので、正直に 上のような文章を書いた。もちろん、これを読んでもらえばわかるように、私も現在が高度成長時代の思考法から完全に抜け出すべき時期に来ていることは頭の 中ではわかっているつもりである。だが、自分が完全に抜け出したかというとあまり自信はない。育った環境から完全に無縁でいられることなど、もともと無理 な話かもしれない。
しかし、2011年の東日本大震災は、「最後の一撃」のごとく経済成長至上主義に引導を渡したように思えた。平川克美氏の『小商いのすすめ―「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ』(ミシマ社、2012年)も、大震災の衝撃を受ける形で公刊された一冊である(誤解を招かないように付け加えると、平川氏は以前から経済成長至上主義に対する疑問を表明してきた一人である)。「小商い」の正確な意味は当初は不明だが、読み進むうちに明らかになってくる1。
日本がまだ貧しかった頃、日本はまだ「死に物狂いになる野生」を十分にもっており、「拡大均衡」が可能であった。しかし、日本は、高度成長の結果、富を 得て野生を失い、経済成長のための条件を失いつつある――これが、簡単にいえば、平川氏の基本的な視点である。ところが、高度成長時代に身についてしまっ た思考法(「経済成長神話」といっても「経済成長至上主義」といっても同じだが)は、いまだに経済界やエコノミストのあいだに根強い。平川氏は、そのよう な「強迫観念」の実態を次のように表現する。
「こういった経済成長によってしか、社会の安定や、個人の幸福や、国家の威信というものを思い描くことができない知性にとっては、社会の安定や個 人の幸福、そして国家の威信とは、お金で買える程度のものでしかありません。実際にはそのどれもがお金では解決できないということを、この数十年の世界の 歴史が明らかにしてきたのではないでしょうか。むしろ、経済的な発展の結果が、ある段階から格差の拡大や、文化の貧困化へ向かったと見るほうが自然です。 これは、経済の拡大が様々な問題を解決するフェーズを過ぎて、新たな問題となるフェーズに入ったということを意味しています。」(同書、144ページ)
平川氏は、資本主義が「産業資本主義」「消費資本主義」を経て「金融資本主義」の段階に到達したとき、逆説的に、最も進んでいたはずの西欧諸国に おいて総需要が停滞し、経済成長が実現できないという「袋小路」に入り込んでしまったという。そして、「このプロセスを後押ししたのは、各国の為政者の思 惑や、大資本家や企業の果てしない成長の欲望であるのは言うまでもありませんが、同時にわたしたち自身が自由と快適な生活を求めてきた結果でもあった」 (同書、186ページ)と付け加える。
それゆえ、平川氏は、「そろそろこの夢から覚める必要があると、わたしは考えています。そして、このような時代に、日本人が採用すべき生き方の基本は、 縮小しながらバランスする生き方以外にありません」(同書、202ページ)と主張するのだが、「小商い」とはこのような考え方から出てきた言葉である。た だし、「小商い」というと、ビジネスの規模のことだと誤解されるのを恐れて、平川氏は、「小商い」をおこなっている友人の会社(自動車の部品製造の会社) のイメージを次のように語っている。
「製品のひとつひとつを大切に誠意を込めて作り出す生産ライン。
それらを顧客に届けて、信頼と満足をフィードバックさせるシステム。
拡大よりは継続を、短期的な利益よりは現場のひとりひとりが労働の意味や喜びを噛み締めることのできる職場をつくること。それが生きる誇りに繋がること。ちいさな革命が労働の現場で日々起きているような会社。」(同書、205ページ)
このような文章から「古き良き時代」の日本的経営がうまく行っていた時代を懐古的に思い浮かべる向きもあるかもしれないが、以前と違う特徴は、 「経済成長神話」がなくともやっていけるという平川氏の「信念」のようなものが投影されていることである。平川氏は、次のように述べている。
「小商いとは、さまざまな外的な条件の変化に対して、それでも何とか生きていける、笑いながら苦境を乗り越えていけるためのライフスタイルであり、コーポレート哲学なのです。
これまでも、これからも、外的な環境変化に対して、あたかもそれが存在しなかったかのように、自分たちのすべきことを着実に実行し、積み上げ、価値を作ってきたものは生き残ってきたし、生き続けていくだろうと思います。
これは、わたしが日本の街場を歩いてみて、あるいは生産の現場を見てきた実感です。」(同書、221ページ)
平川氏と類似の思想を経済学に求めようとするならば、やはり古典派時代の偉大な知識人であったJ.S.ミルの「定常状態」〔「全生産額-地代]- 賃金総額=利潤=0となる状態、英語ではstationary stateという)に対する肯定的な評価だろう。「縮小均衡」といってしまうと、「縮小再生産」のように限りなくゼロにまで「縮小」してしまうようにイ メージされやすいので、経済学者でそれを理想的に描いた者はほとんど見当たらない。せいぜい定常状態に到達し、利潤がゼロになるのだけれども、そこでも人 間的進歩の可能性はあるというミルの主張や、その系譜が見つかる程度ではないだろうか。それにもかかわらず、ミルの見解は、古典派時代には十分に[異端」 的であったし、現代でもそうである。
きわめて重要なところなので、ミルの『経済学原理』(1848年)から原文も掲げてみよう2。
It is scarcely necessary to remark that a stationary condition of capital and population implies no stationary state of human improvement. There would be as much scope as ever for all kinds of mental culture, and moral and social progress; as much room for improving the Art of Living, and much more likelihood of its being improved, when minds ceased to be engrossed by the art of getting on. Even the industrial arts might be as earnestly and as successfully cultivated, with this sole difference, that instead of serving no purpose but the increase of wealth, industrial improvement would produce their legitimate effect, that of abridging labour.
「資本と人口の定常状態が人間的発展の停止状態を意味するものでは決してないことは、改めて指摘するまでもない。定常状態でも、以前と同じよう に、あらゆる種類の精神的文化や、道徳的および社会的進歩の余地が十分にあることに変わりはないだろう。また『生活様式』を改善する余地も以前と変わりな く、むしろそれが改善される可能性は、人間の心が仕事を続けていく術に夢中にならなくなるとき遙かに大きくなるだろう。産業の技術さえも、以前と同じよう に熱心に、かつ成功裏に開拓されるだろう。唯一の違いは、富の増大という目的だけに奉仕する代わりに、産業上の改善が労働を節約させるという、そのもっと もな効果をもたらすだけになるだろうということだ。」
ミルが他の古典派経済学者と違って「定常状態」に肯定的な評価を与えたのは経済思想史の上では全く「異端」の思想であったが、それは決して「ユートピ ア」ではないと言い切るのは、「社会的共通資本」(自然環境、社会的インフラストラクチャー、制度資本の三つに大別される)の概念で有名な宇沢弘文氏(東京大学名誉教授)である( 『経済学と人間の心』東洋経済新報社、2003年)。
宇沢氏は、ミルの「定常状態」をマクロ的諸変数(国民所得、消費、投資、物価水準など)が一定でありながら、ミクロ的には華やかな人間活動が展開されて いる状態として捉えているが、このような状態は、ソースタイン・ヴェブレンの制度主義の経済学によって実現可能だと主張する。「それは、さまざまな社会的 共通資本(social overhead capital)を社会的な観点から最適な形に建設し、そのサービスの供給を社会的な基準にしたがっておこなうことによって、ミルの定常状態が実現可能に なるというように理解することができる。現代的な用語法を用いれば、持続的発展(sustainable development)の状態を意味したのである」と(同書、118ページ)。
ミルの「定常状態」がヴェブレンを介して社会的共通資本論へと受け継がれるというのは宇沢氏独特の解釈だが、一つの思想が形を変えながら何度も甦るという経済思想史の典型的な特徴を垣間見るようで実に興味深い。
だが、平川氏は、「小商い」と「持続的発展」が類似のものだといわれたら承服するだろうか。おそらく、「違う」というのではないか。というのも、平川氏 の関心が単なる「経済」ではなく、それを支える価値観を問題にしているからである。『小商いのすすめ』には、次のような文章も登場する(この点、平川氏 は、自分の考えが橋本治氏の『貧乏は正しい!』小学館文庫、1997年、の影響を受けていることを率直に認めているようである)。
「もうおわかりだと思いますが、わたしが言う、昭和初期のおとなとは、いまだ富を手に入れていないひとびとであり、それゆえ野生と若さを身体の中 に蓄えていたひとびとのことだということです。当時の日本の社会はそういったひとびとによって支えられていたということです。そして、階級格差の少ないア ジアの島国では、関川夏央さんが言ったように、誰もが共和的に貧しく、それゆえに明るくいられたのだと思います。
かれらの社会の価値観の中心にあるのは、美しさということであり、富を蓄えるということではありません。この美しさの表象のひとつが、貧しさの中の帽子だったのかもしれません。
そして、その帽子の下に隠されていたのは、日本人のみずみずしい野生だったのです。
しかし、かれらが富を手にし始めた頃、つまり一家にテレビ、冷蔵庫、洗濯機、クーラー、自動車などが揃い、こどもひとりひとりにこども部屋ができ、主婦 たちが家事労働から解放されるころから、日本人から野生が消えていきました。その民主化のプロセスのなかで、じりじりと出生率が下がり始め、経済成長率は 頭打ちになっていくことになりました。」(同書、105-106ページ)
経済学者と文筆家とは違うといえばそれまでだし、私もノスタルジックに過去を憧憬するだけでは終わりたくはないのだが、平川氏の本を読んで、現代 の日本人が「人間が本来の野生を失い、金銭的欲望と利便性への誘惑に支配されてしまう」(同書、189ページ)という意味での「文明病」に冒されているこ とを繰り返し強調しているのをみると、『小商いのすすめ』とは一種の「文明批評」なのだと思い至る。「昭和元禄」のような時代を再び夢見るのか、それとも 「文明病」から目覚めて「小商い」の方へ舵を取るのか、それは私たちの決断にかかっていると言えるだろう。
注
1 平川氏の著書のサブタイトルは、「『経済成長』から『縮小均衡』の時代へ」となっているが、その問題意識は、同時期に公刊されたアンドリュー・J.サター氏の『経済成長神話の終わり』(講談社現代新書、2012年)と 驚くほど重なっている。サター氏は、サブタイトルに「減成長と日本の希望」という言葉を選んでいるが、ここで「減成長」とは、フランス語の décroissance(「脱成長」や「非成長」と訳されることもある)の意味で使われているようである。サター氏は、「減成長による繁栄」を実現する ための民主市議的諸改革にまで説き及んでいるが、少しこのエッセイが扱う範囲を超えているので、関心のある読者はその本を手にとってほしい。
2 Collected Works of John Stuart Mill,vol.3: Principles of Political Economy, Books Ⅲ-Ⅴ,Liberty Fund,1965,p.756. 『経済学原理』の翻訳は岩波文庫(末永茂喜訳)にあるが、少し古くなっているので、拙訳を掲げておいた。