2011年12月21日
『定本 見田宗介著作集 � 生と死と愛と孤独の社会学』見田宗介(岩波書店)
「社会学vs文学」
大作家と言われる人でもなかなか個人全集が出ない時代である。そんな中で見田宗介/真木悠介著作集の刊行がはじまった。意味深いことである。たとえば今、本を読むのが好きで、物を考えるのも好きで、「生」とか「愛」とか「死」とか「孤独」について、あれこれ言いたいひとりの若者がいた とする。50年前であれば、そのような若者は作家を志望したり、文学研究を志したり、批評を書いてみたりする可能性が高かったのではなかろうか。もちろん 今だってそういう例がないことはないが、明らかに50年前とは状況がちがう。「まずはともあれ文学」というような文学至上主義は遠い昔のものとなった。で は、そのような若者はどこへ向かうのか?いったい何が変わったのか?
「生と死と愛と孤独の社会学」と副題のついた『定本見田宗介著作集�』を読むと、そのあたりの事情が見えてくるように思う。まず驚くのは巻頭をか ざる「まなざしの地獄」である。永山則夫事件を扱ったこの論考は1973年「展望」に発表されたものだが、そこに書かれていることは、「社会学」という言 葉のイメージとは簡単には結びつかないような気がする。書き出しは次のような具合だ。
N・Nは一九六五年三月、青森県板柳町の中学を卒えて、集団就職の一員として東京に上京している。手にしたボストン バッグの中味は、「母親の用意したワイシャツ2、仕事用ズボン1、外出用ズボン1、シャツ2、パンツ2、靴下2、そして彼自身がえらんだ中学当時の教科書 数冊」であったという。この部分だけ読んで、この文章がいったいどのような性質のものか判断できるだろうか。そこには単なる 語りではなく、物語の気配がある。やや不穏な緊張感から、ストーリーの匂いが漂ってくる。もちろん直後に「ちなみにこの年中学や高校を卒えて京浜に流入し た少年の数は、一一万一〇一五人、うち中卒者は四万八七八六人である」といった俯瞰的な記述がつづき、やがて「N・N(=永山則夫)にいったい何が起きた のか?」という問いがこの論考の土台をなすことも明らかになるのだが、読み進めて印象づけられるのは問題提起→結論といった議論の枠組みではない。むしろ 感じられるのは、とにかくいろいろな種類の言葉があふれているということだ。いろんな種類の「言葉のモード」が出てくるのである。
ルポルタージュ風の記述からはじめて見田は事件を再構築し、永山の行動を追う。「戸籍事件」「麦飯問題」といった印象的なエピソード。「まなざ し」をキーワードとした分析的な言葉が問題点を絞りこんでいく。たしかにいかにも「社会学的」な抽象化である。「社会」や「学」にふさわしい硬質な思考が そこでは展開されている。社会のまなざしの中で次第に自分を見失い、苛立ちと怨嗟に取り憑かれていく永山の姿。見田はそれを以下のような言葉で語る。
都市が人間を表相によって差別する以上、彼もまた次第に表相によって勝負する。一方は具象化された表相性の演技。他方は抽象化された表相性の演技。おしゃれと肩書。まなざしの地獄を逆手にとったのりこえの試み——。(34)
まなざしの地獄の中で、自己のことばと行為との意味が容赦なく収奪されてゆき、対他と対自とのあいだに通底しようもなく巨大な空隙のできてしまうとき、対自はただ、いらだたしい無念さとして蓄積されてゆく。(48)しかし、このような言葉ばかりで書かれていたら、「まなざしの地獄」にはいったいどれだけの説得力が生まれていただろうかとも思う。記述と物語から出発 するこの論考には、「学卒就職者の転職理由」や「東京への就職転入者の初職」といった統計が散りばめられ、客観的なデータを支えにした�科学的�な議論が 展開される。そこには、永山則夫から出発しつつも広く社会や人間についての考察を展開しようとする、まさに社会学的な意志が読み取れるのだが、ほんとうに 重要なのは、分析でも構図でも、あるいデータでも一般論でもない。もっとも迫力があるのは、後半にかけて頻繁に引用される永山自身の言葉なのである。
私は逃げた。……まるで何かに取り憑かれた魂のない蒼空に飛び流れて消えて行く。風船のように。それでも黒い不気味な影跡は残していった。(24)
私には肉親というものを考えることは出来ない。なぜにこうなってしまったのかを一言的に表現すると、すべて、すべて、すべて、すべては、貧困生活からだと断定できる。貧困から無知が誕まれる。そして人間関係というものも破壊される。(40 引用元では太字ではなく傍点。以下同じ))
私には目的がなかった——と世間ではいっている。果たしてそうであるのか? 私から観ればあったのである。……あなた達へのしかえしのために、私は青春を賭けた。それは世間全般への報復としてでもある。そしてそれが成功した。(50)
私という人間が恐い、そう思えてならない。ある一つの物に燃え狂い、自制が効かないのです。(54)もちろん単に永山則夫の言葉と出会いたいならば永山の著である『無知の涙』を読めばいい。見田がここで行っているのは——しかも統計や、分析や、一般化 の言葉をさりげなく踏み台にしながら行っているのは——永山の言葉を�響かせる�ということなのである。既存のテクストに寄り添いながら、ときに介入し、 ときに解読し、ときにボリュームをしぼり、しかし、肝心のところでは大音量にして、場合によってはみずからもその声に唱和するようにして語る、これはまさ に文芸評論の行ってきたパフォーマンスに他ならない。実際、見田は、永山の言葉を引用してはまるでそれに感染するかのようにして語るようになる。
我が行動の終わりし後に/数多く事おこれば悲しく痛くなり……。
「見るまえに跳べ」というアジテーションは、跳ぶ前に見ることもできる人間の言い方だ。
「見る前に跳ぶ」ことだけを強いられてあることの無念。(56)
語る見田と語られる永山の間の閾は次第にはっきりしなくなる。このような文章を見てあらためて思うのは、70年代、「社会学」の言葉がきわめて自由な書 かれ方をするようになったのだなあ、ということである。文学が排斥されたわけではなかった。むしろ、文学は解放されたのである。狭い意味での文壇やら文学 研究から解放されて、「社会学」の領域にも文学が流れこみつつあった。
少なくとも見田の行おうとした社会学は「声」に対して敏感になろうとする学問だった。そういう意味では、場合によってはそれは詩人や作家の行おう とすることとほとんど区別がつかない。声をいかに響かせるかということに、文学者も無頓着でいられるわけはないのである。むろん、「学問」を看板にする書 き手だって、ほんとうは「声」のことに鈍感でいいわけがない。どちらの陣営もいつの間に同じことをしている。それはそうだろう。振り返ってみれば、「愛」 や「生」や「死」や「孤独」というその出発点も重なっているのだから。
その後、30〜40年をへて「社会学」がどのような変貌を遂げてきたのか筆者には概観する能力はないが、もしこの学問領域が「文学」などをはるか に超えて力を持ちつつあり、「声」をあげたいと思う若者を惹きつけているのだとしたら、それはきっと「社会学」が「声」を深く豊かに響かせる環境を整えた ということだろう。ほんとうにそうなのかどうか、注視したい。
本書には30年以上にわたって発表された7つの論考が収められている。今では誰も覚えていないであろう『愛と死をみつめて』という60年代のベス トセラーを扱った章もあれば、1999年にカラオケボックスで自死したネットアイドルの章もある。現代短歌の分析もある。その中でもっともよく知られてい るのはおそらく、「夢の時代と虚構の時代」という論考だ。高度経済成長期に至る時代を「理想」から「夢」という流れで、そしてポスト高度成長期を「虚構」 と「脱臭」と「やさしさ」で読み解く構図は、発表当時はともかく今となってはそれほど珍しい視点とも見えないかもしれないが、たとえば理想の時代と不即不 離なのが「リアリティ」の感覚である点を見田が見抜いているのはやはり鋭い。
表現のさまざまな様式の歴史において、リアリズムという運動が多くのばあい、理想主義的な原動機にうらうちされていたように、理 想の時代は、また「リアリティ」の時代であった。虚構に生きようとする精神は、もうリアリティを愛さない。二〇世紀おわりの時代の日本を、特にその都市を 特色づけたのは、リアリティの「脱臭」に向けて浮遊する〈虚構〉の言説であり、表現であり、また生の技法でもあった。(99〜103)
石原慎太郎の『太陽の季節』(一九五六年)という小説の主人公は、硬直したペニスを障子につき立てるという実体主義的な求愛の様 式をとった。これはこの当時「新しい」もの、「戦後」の終りを告知するものといわれたけれども、一九八〇年代以降の諸文学からふりかえってみると、それは なお典型的に「リアリティ」の時代の身体技法であった。(103)きれいな構図で「世代」や「時代」を説明するような言説を、社会はいつも求めている。「社会学」はいい意味でのその境界の曖昧さを持ち味に、そんな要請 に上手に応えてきた。しかし、その根っこに、たとえば石原慎太郎のペニスを置こうとする見田のこうしたやり方には、ある種のこだわりが見て取れる。構図の きれいさに気を取られた思考法はしばしば鋭利さを失うものである。そこからは声が聞こえてこないから。まさにそのことを見田は危惧しつづけてきたのではな かろうか。何しろ、ほかならぬ文学研究が「構図」に足下を掬われてきたのだから。
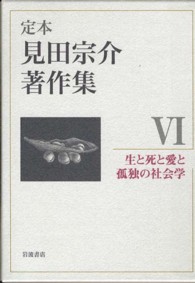
0 件のコメント:
コメントを投稿