2012年07月31日
『東北おやつ紀行』市川慎子(中央公論新社)
この十年ほどの地方ブームと連動し、郷土食もずいぶんと注目されるようになった。土地の人だけが通う個人商店やスーパーマーケット、農産物ととも に、古くから地元の味として親しまれている加工食品がならぶ「道の駅」、そんな場所で造作なく売られているそれらは、外からやってくるお客さんをあてこん だいわゆる�名物�とはちがう、生活感あふれるたべものたちだ。
そんな「おやつ」をめざし、郡山から車を飛ばして、東北の町々をたずねた小さな旅のレポート。観光とよぶにはあまりにも楚々とした移動であり、見学であり、飲食である。このご時世、こういうのこそ贅沢というものかもしれない。
行き当たりばったりなどでは決してない。ちゃんと、ネットなどから情報を得、準備万端に出発している。早起きをし、何時間も雪の道を進み、「おや つ」だけでなく、美術鑑賞したり、建てもの探訪したり、水族館でクラゲをみたり、祭りを楽しんだり、温泉につかったりと、充実した旅をしているのだけれ ど、なんというか、ただ黙って立ち上がり、おもむろに出かけていくようなところが著者にはある。
あれ、ちょっと、この人は、さっきまでこたつにあたってお茶をすすっていたと思ったら、もうあんなところでまんじゅう頬ばっているよ、というよう な、不思議な瞬発力。ちっともてきぱきとしているようにはみえないのに、どうしてか仕事を終わらせるのは早い、というような、そんな感じ。
入ってすぐの土間がこの店の売場らしい。木製の平たい菓子ケースが二列、向こうの隅まで続き、奧の棚にも分厚くて腹のところがまあるく膨らんだガラスの菓子瓶が並んでいる。店丸ごと都会の古道具屋で売られていそうな空間である。
こまごまと並んだお菓子を土間から伸び上がり(遠くて手が届かないので)目だけで漁る。紅白のストライプが入ったリボン型の飴、桃色や抹茶色の 梅の打ち菓子。まんなかに穴のあいたドーナツ型のパンやうぐいす色をした板状のハッカ飴もある。完璧な空間に収まった完璧にかわいらしいお菓子の数々に、 ボタン屋さんやビーズ屋さんに入った手芸おばさんのように興奮する。
天井が高く、がらんとした店内に入るが、誰もいない。入ってすぐの平台に、茶色く平べったい花の形をしたお餅(のようなもの)がのっていた。どちらも大人の手のひらくらい大きい。
これはなんだろう。甘いものかしら。近寄りみていたら、奧から白髪の小さなおばあさんが出てきた。……
手を後ろで軽く組み、腰を小さく曲げたおばあさんは、この辺の方言なのだろうか、わたしにはうまく聞き取れない言葉で、「今はこんなに食べられ ないから小さいのもある。でも昔はこれしかなかった。それでも余らせたことはなかった。あんたどっから来た? 旅行か? あんこ、好きだろ? それならこ のおまんじゅう、レンジでチンするといい。ちぎって少しずつ食べるとおいしい」というようなことを言う。今の相槌、正しかったかしら。わたしのおばあさん と同じように腰を折り、身をかがめ、耳をそばだて話を聞く。……
著者は愛知に生まれ育ち、のち大阪と東京で過ごし、家族の都合で郡山に移り住むことになった。そこからはじまった東北めぐり。そのためなのだろ う、ここには、旅人としてのまなざし、同じ東北の地で生活をする者としてのまなざしとがミックスされている。拠点である郡山では、外からやってきた著者は いわば余所者である。しかし、旅の上では、まったく別の地方からやってきたお客さんというわけでもないのだ。そんな立場が彼女を、遠慮がちなようでいて、 しずかな親しみにあふれた旅人にしているのだと思う。
本書は、2011年の夏の刊行をめざして書きすすめられていたが、東日本大震災後、作業は中断される。原発事故のために郡山をあとにしてしばら く、著者にとって、かつての旅の記憶はつらいものとなったが、次第に大切な思い出へと変わっていったという。この、苦しみをくぐり抜けたあとのいつくしみ の気持ちもまた、ここに収められた旅の数々が、著者の日常と地続きにあるものだったためかもしれない。
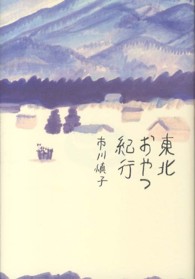
0 件のコメント:
コメントを投稿