2013年09月19日
『カント先生の散歩』 池内紀 (潮出版社)
カントというと謹厳実直な哲学者を思い浮かべる人が多いだろう。なにしろ難解な本を書いた人である。毎日規則正しく散歩したので時計がわりになったという逸話がいよいよ気難しそうなイメージを強める。
しかしカントを直接知る同時代人の書簡や回想によると、実際は座をとりもつのがうまい社交好的な人物だったらしい。
当時の大学の教師には黒ずくめで通したり、身なりに気をつかわない人が多かったようだが、カントは流行に敏感でお洒落だった(本書の表紙はおかしい。もっと派手な服を着せなければ)。通いの召使には白と赤のお仕着せを着せていた。白と赤が好きだったからだ。
授業も形而上学、論理学、神学、倫理学といった難しそうな科目だけではなく、自然地理学と人間学という「通俗的」な科目も担当していた。この二つはたいそうな人気で、学生以外も聴講にきていた。
本書は一般向けの本ではあまりふれられてこなかった社交的なカントに焦点をあわせた伝記であり、哲学上の著作にも社交の影響があるとしている。
著者はまずケーニヒスベルクの繁栄を描きだす。カントは生涯ケーニヒスベルクを出ることはなかったが、田舎町とか、北辺の港町と形容されることが多い。
しかしケーニヒスベルクは700年つづいた東プロシアの首都であり、19世紀になってベルリンが台頭するまでは北ドイツ文化の中心地だった。出身者には作家のホフマン、哲学者のハーマン、数学者のゴルトバッハやヒルベルトがいるし、オイラーも縁が深かった。
ケーニヒスベルク城や大聖堂をはじめとする歴史的建造物が林立し「バルト海の真珠」と称されたが、第二次大戦末期、連合軍の空襲と戦闘で街の98%が破壊された。
街はソ連に編入されてカリーニングラードと名前を変えられた。ドイツ系住民は追いだされ、代りにスラブ系住民が送りこまれた。ドイツ系住民は一部はシベリアの収容所に、残りは東ドイツに強制移住させられた。
同じように破壊されたドレスデンとワルシャワは民族の宝として国を挙げた復興事業がおこなわれ、戦前とたがわぬ街並が再建されたが、ケーニヒスベ ルクはつまらない田舎町になりさがった。ペレストロイカ後、ドイツからの寄付金と要請で大聖堂が復元されたが、市当局はまったく乗り気ではなかった。カン ト廟は奇跡的に無事だったが、現在のカリーニングラードには往時の繁栄をしのぶものはほとんど残っていない。
著者によれば、ケーニヒスベルク大学はカントの時代までは新興のベルリン大学をしのぐ北ドイツ一の大学だった。私講師として不安定な生活をつづけていたカントが他の都市の大学からの誘いを拒みつづけたこともそれほど奇異なことではないのかもしれない。
南ドイツの大学から教授に招聘された際、カントは身体の虚弱と街に多くの友人がいることを断りの理由にした。確かにカントはケーニヒスベルク社交界の人気者で、多くの友人がいた。しかし親友といえるのはジョゼフ・グリーンただ一人だったろう。
グリーンは穀物、鰊、石炭などを手広くあつかう英国人貿易商だったが、独身で遊びには興味がなく、自宅で「かたい本」を読むのが趣味という変わり者だった。
カントは40歳の時にグリーンと知りあったが(50歳説もある。中島義道『カントの人間学』参照)、以来劇場通いやカードゲームはふっつりとやめ、毎日のようにグリーン邸を訪れるようになった。
名うてのイギリス商人から口づたえに、刻々と変化する現実世界を知らされ、最新情勢にもとづいて「先を読む」コーチを受けていた。ディスカッショ ンという個人教育を通して、厳しい訓練にあずかった。グリーンを知ってのちのカントの生活が大きく変わり、グリーン家通いがすべてを押しのけるまでになっ たのには、カントにとって十分な理由があった。
グリーンの部下で後に後継者となるロバート・マザビーが二人が議論する場に同席したことがある。話題は英国とアメリカ植民地の経済問題で、英国 側・アメリカ側にわかれてディベートしたが、英製品ボイコットや印紙条例、フランスの財政破綻などその後の展開を的確に予測していた。
二人が語りあったのは世界情勢だけではなかった。カントは社交の場で哲学の話題にふれることを嫌ったが、グリーンにだけは準備中の『純粋理性批判』の内容を語り、すべての部分で意見を聞いた。
カント哲学は哲学者カントの頭から生まれたと思いがちだが、そこには二つの頭脳がはたらいていた。商都で成功した貿易商の優雅な客間の午後、思索 が大好きな二人が、形而上的言葉をチェスの駒のように配置して知的ゲームに熱中した。十八世紀から十九世紀にかけて、ヨーロッパの富裕層では国を問わずに 見られた現象であって、おおかたの哲学書はそんなふうに誕生した。カントの場合のやや風変わりなのは、知的サロンが独身の中年男二人にかぎられていたこと である。
著者は『純粋理性批判』の第一稿には「資本」「借用」「担保」等々の経済用語がまじっていたのではないかと想像しているが、裁判用語が残っていることからするとありえない話ではないだろう。
カントの時間厳守癖はグリーンの影響だったが、グリーンから学んだことがもう一つある。財テクだ。
カントは貧乏な職人の家に生れ、かつかつの暮らしをしてきた。グリーンはカントのわずかな貯えを有利な条件で運用してやった。グリーンの薫陶よろしくカントは亡くなった時には一財産残すことができた。
『純粋理性批判』刊行の5年後、グリーンが亡くなった。カントは料理女を雇わず外食で通していたが、店の開いていない日曜日はグリーン邸で食事に呼ばれた。
親友を失ったカントは同じ哲学部の教授で後輩のクラウスを新たな話し相手にした。クラウスも独身だったが、彼を日曜の食事にまねくために料理女を雇うことにした。日曜の食事会はしだいに参加者が増えていった。
著者は『実践理性批判』でグリーンの役割を果たしたのはクラウスではないかとしている。クラウスは実際的な道徳説を説いており、『実践理性批判』刊行後に仲たがいしたというから当たっているかもしれない。
『判断力批判』はどうか。もし対話相手がいたとすれば、東プロシア政庁の高官でケーニヒスベルク言論界の影の仕掛人であり、カントの庇護者でもあったヒッペルではないかというのが著者の見立てだ。ちなみに彼も独身だった。
ヒッペルは讃美歌やグリーンをモデルにした『時計男』という喜劇を書くなど多芸多才だったが、没後、マゾ趣味やきわどい挿画のはいった好色本のコレクションが暴露された。そういう風流才子が『判断力批判』にかかわっていたというのはなかなか楽しい空想である。
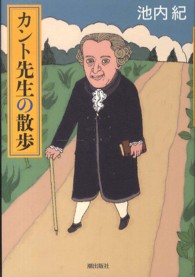
0 件のコメント:
コメントを投稿