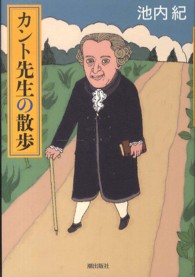2013年09月16日
『カント「視霊者の夢」』 カント (講談社学術文庫)/『神秘家列伝〈其ノ壱〉』 水木しげる (角川ソフィア文庫)
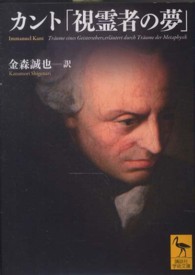 |  |
『視霊者の夢』は1766年、カントが42歳の時に出版したスウェーデンボリ論である(英語読みではスウェーデンボルグ)。
スウェーデンボリはカントより36歳年長のスウェーデンの科学者である。英国に留学して天文学(ハレーの助手をつとめたこともある)と機械工学を 学び、帰国後は王立鉱山局で鉱山開発に辣腕をふるって貴族に列せられ、国会議員にも選ばれた。ところが59歳で引退すると、それまで隠していた霊能力を公 然と披露するようになり、霊界のありさまを克明に描いた神秘的著作を矢継ぎ早に発表した。
1759年のストックホルムの大火の際には、500km離れた地方都市の夕食会で突然顔面蒼白になって大火の様子を事細かに語りだし、後日その通りだったことが確認されるとヨーロッパ中の話題となった。
この頃カントは出版社兼書店をいとなむカンターの家に間借りしており、大家でもあるカンターから依頼されて書いたのが『視霊者の夢』である。カン ターはスウェーデンボリ・ブームが終わらないうちに急いで出版しようとしたのだろう、原稿段階で検閲を受けるのが原則なのに、ゲラ刷りになってから提出し たため1万ターレルという巨額の罰金(50万円くらい?)を課されている。
『純粋理性批判』以前のカントは科学哲学者として知られていたから、カントは大槻教授のように科学的見地からのスウェーデンボリ批判を期待されていたはずである。
実際に読んでみると、のっけから憂鬱の風が体内で下降すれば屁となり、上昇すれば神聖な霊感になるとか、視霊者は火炙りにするより下剤を飲ませて腸内を浄化すればいいといった調子でスウェーデンボリをからかっており、風刺的文書に分類されるのも納得できる。
カントは出版社に強要されてしかたなく書いたと言い訳をくりかえしているが、読み終えてみると、はたしてそうかという疑問が起きた。
本書は第一部「独断編」(ドグマ編もしくは原理編と訳した方がいいのではないか)と第二部「歴史編」にわかれる。スウェーデンボリ批判はもっぱら 第二部で、第一部はなぜ霊視がありうるか(たとえ幻覚であっても)、なぜ霊は半透明で透けて見えるのか、なぜ霊は物体を通り抜けられるかについて大真面目 に考察している。最後は風刺的な書き方で茶化してはいるが、頭から霊視体験を否定していたらここまで長々と検討することはなかったと思うのだ。
デカルトの心身相関論を踏まえた議論をつづけた後で道徳の根拠の問題に移るのは意外だった。
思考する存在のなかの道徳的衝動という現象は、霊的存在をたがいに交流させあう真に活動的な力の結果と考えることはできないであろうか? そうなると道徳的感情とは個人の意志が一般意志にまさにその通りと感じられるように拘束されていることであり、非物質的世界に道徳的統一を獲得させる上で必要な自然にしてかつ一般的な相互作用の所産ということになるだろう。
『実践理性批判』はこのような道徳観を克服するために書かれたと考えるべきなのだろうか。
驚いたのは巻末におさめられている「シャルロッテ・フォン・クノープロッホ嬢への手紙」である。フォン・クノープロッホ嬢からスウェーデンボリに ついて問い合わせる手紙があって、その返信として書かれたらしいが、カントは受講生だったデンマークの士官からストックホルム大火の霊視事件を聞いたこ と、もっと詳しく知るためにコペンハーゲンに帰った士官に調査を依頼したこと、それだけでは満足できなくてストックホルム在住の旧知の英国商人に現地調査 を依頼したことを伝え、こうつづけている。
この出来事が信用できないとどうして主張できましょうか? このことを手紙で伝えたわたくしの友人は、すべてのいきさつをストックホルムばかりで なく、二ヶ月にわたりイエーテボリでも調査しました。同市では、彼は有力者たちをたいへんよく知っておりましたし、この事件からわずかしかたっていなかっ ただけに、大多数の証人がまだ存命中でしたので彼はいわば全市民からきめこまかく事情を教えてもらいました。
カントは件の英国商人にスウェーデンボリ宛の書簡を託していた。商人はスウェーデンボリと面会して書簡を手渡し、必ず返事を出すという約束をとり つけてくれる。カントはさらに「この奇妙な人物に自ら質問できればいいと切望しています」と今にもストックホルムに飛んでいきそうな勢いである(旅行嫌い でなければ本当に会いに行ったかもしれない)。
結局、スウェーデンボリからの返信はなく、面子をつぶされたカントは『視霊者の夢』でスウェーデンボリをこきおろすが、それでも半分以上信じていたのではないかという気がするのだ。
スウェーデンボリについては日本でも多数の本が出版されており、なんと全集まで邦訳されている。しかし『視霊者の夢』を読む範囲でなら水木しげる の『神秘家列伝〈其ノ壱〉』で十分である。この本ではスウェーデンボリのほかにチベットの聖者ミラレパ、ヴードゥー教の創始者マカンダル、日本の明恵上人 の四人の神秘家をとりあげているが、時代背景まで含めてコンパクトにまとまっていて便利である。