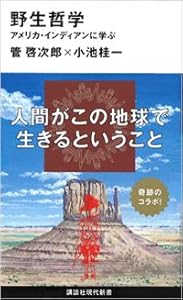→bookwebで購入
→bookwebで購入
本書はジュネットがテクスト論三部作の後、1991年に出した文学論集である。表題にある「フィクション」とはもちろん虚構のことだが、「ディクション」diction とは語り方、言葉づかい、措辞をあらわす普通名詞である。
『虚構と語り方』と訳そうと思えば訳せる本でジュネットは『アルシテクスト序説』で指摘されていた抒情詩がアリストテレスの『詩学』の基準では芸術とは見なされなかった問題に立ちもどっている。
アリストテレスが芸術にあたえた定義は模倣(ミメーシス)であることだ。殺人や大災害が好きな人はめったにいないが、殺人や大災害を描いた映画や小説は多くの人に好まれる。映画や小説の中の殺人や大災害は殺人や大災害のミメーシスであって、現実の殺人や大災害ではないからだ。
抒情詩が芸術と見なされなかったのは抒情詩の歌うものが感情のミメーシスではなく、詩人本人の真実の感情と考えられたからだ。抒情詩うんぬんなど という浮き世離れした話には興味がないという人がいるかもしれないが、ミメーシスを芸術性の基準にするならルソーの『告白』のような自伝や日本の私小説が 抒情詩も芸術——文学ではなくなるのである。
ロマン主義時代の文芸学者は抒情詩を装われた感情を歌うとしてミメーシスにとりこもうとした。確かに多くの抒情詩は誇張された感情を歌うし、自伝 や私小説にも誇張はつきものだろう。しかし誇張のない抒情詩や自伝、私小説もないとはいえないし、歴史書やノンフィクション、論説、日記、書簡などが文学 とされることもある。スタンダールにいたってはナポレオン法典を文学と見なしている。抒情詩や自伝、私小説、事実を語った言説を文学にとりこむにはミメー シスとは別の基準が必要になるのである。
そこで注目されたのが語り方である。ヴァレリーは普通の言語と詩の言語の違いを歩行と舞踏の違いになぞらえた。手段は同じでも普通の言語=歩行は なにかのためにおこなうのに対し、詩の言語=舞踏はそれ自体のためにおこなわれる。ローマン・ヤコブソンが言語の六つの機能の一つとした詩的機能も同様の 着眼である。普通の言語が意味をあらわす指示的機能に重きが置かれるのに対し、詩の言語はメッセージそれ自体に注意を集める詩的機能が重視されるというわ けだ。
しかし詩なら脚韻、頭韻だったり音数律をとったりすることで特別な語り方であることがはっきりわかるが、散文ではそうはいかない。形式という目印のない散文の詩的機能とはどのようなものだろうか。
ジュネットは「フィクションとディクション」という巻頭論文では読者の受けとり方の問題という結論を出すが、これは問題提起と受けとるべきだろう。
第二章「虚構の行為」では物語的虚構にもどり、サールの言語行為論を手がかりに虚構が虚構であるとはどういうことかを考察し、第三章「虚構的物語 言説、事実的物語言説」では『物語のディスクール』と『物語の詩学』で展開した自身の物語論を再検証し物語と事実をわかつ客観的な指標がないことを確認し ている。
さて最後の「文体と意味作用」である。文学作品かどうかが語り方の問題となると文体とは何かを問わなければならない。ジュネットはシャルル・バイ イ、ピエール・ギロー、サルトル、ネルソン・グッドマンの文体の定義を次々に検討し、グッドマンに共感を示しながらも、「文やその諸要素のような言語に固 有のミクロ構造レベルに現れる——あるいは構造よりはむしろ織物 texture のレベルに現れる——言説の形式的な属性」という無難な結論に着地する。
泰山鳴動しての感がなくもないが、むしろ重要なのは文体を標準的な語り方からのずれ、際立たせるための特異な語り方とする根強い見方に対する批判 だろう。標準からのずれという見方は文体要素が離散的にあらわれるというシュピッツァーやリファテールの文体観を結果し、文体の統計的分析に道を開くこと になる。ジュネットはプルーストの文体観に依拠しながら、文体は文体事象の集合ではなく一貫した世界観によって「形を歪められた統語法」だという見方を打 ちだす。
スリジーのシンポジュウムで「神は細部に宿る」というモットーを引用した文体学者に対しジャン=ピエール・リシャールは「私ならこう言うところです、神は細部のあいだに宿ると」と切り返したというエピソードをジュネットは最後に紹介しているが、ポスト構造主義に向かったバルトに対し、あくまで構造主義にとどまったジュネットらしい締めくくりといえよう。
 →bookwebで購入
→bookwebで購入