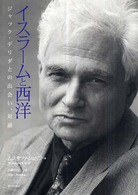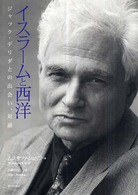
 →bookwebで購入
→bookwebで購入
「地中海の子、デリダ」
著者のムスタファ・シェリフは、デリダの生まれた国アルジェリアのイスラーム学者であり、駐エジプト大使や高等教育大臣を歴任した政治家で、哲学者であ る。著者はデリダの哲学に心酔しており、2000年の3月に、デリダをパリのアラブ世界研究所で開催されたシンポジウムに招待した。デリダは病気が悪化し ていたにもかかわらず、病院での検査の後に、このシンポジウムに直行したという。
シェリフはイスラーム世界の有力な知識人として知られているが、2006年に起きたムハンマド風刺画事件に関連して、「イスラーム意見 番」(p.155)として活躍した逸話が有名だ。ローマ教皇がこの問題についてレーゲンスブルク大学で発言して、イスラーム世界から批判をうけたことか ら、ローマ教皇がシェリフを招いて、助言を求めたのだった。
このシンポジウムに招かれたデリダは、まとめたスピーチを行える状態ではなく、シェリフの質問に回答するという形で発言しているが、あくまで「ア ルジェリア人としてお話したいと思います」(p.42)という姿勢を崩さない。そして西洋世界とイスラーム世界の「両岸をむすびつけ」る(p.133)と いう役割をはたすべく、ごく平易な言葉で語りかけているので、デリダの晩年の思想の入門としても役立つ書物になっている。
アルジェリアがデリダが受け継いだ「遺産」について、デリダはこう語る。自分はヨーロッパの思想にたいして「ある種の周縁から、ある種の外部から 投げかけるように数々の問いを提示してきた」(p.45)が、それができたのは自分が「単なるフランス人でもなく単なるアフリカ人でもない、言うなれば地 中海の子供」だったことが大きく影響していると想起する。
そしてデリダは、イスラームと西洋の相互の利益のために「民主主義の普遍主義」を求めていると語る。これは現在の地球には存在していない民主主 義、「来たるべき民主主義」である。デリダにとって民主主義というモデルは、「自らの歴史性、すなわち自らの将来を受け入れ、自己批判を受け入れ、改善可 能性(ペルフェクティビリテ)を受け入れるという、いわばモデルをもたないモデルという独特な政治体制」(p.58)であると信じているからである。
とは言いながらもデリダは、この民主主義を実現するためには国家という体制もまた必要であると考えている。「国家なるものはいくつかの条件におい て、……非宗教性、あるいは諸宗教的共同体の生活の保証人でありうるのです。国家は、何らかの経済的勢力、度を越した経済的な集中、経済的権力をもつ国際 的な勢力に抵抗することができます」(p.70)と考えるからである。
デリダのこの姿勢は、グローバリゼーションに対する姿勢とも一貫する。デリダは「グローバリゼーションなるものは生じていない」(p.82)と断 定する。帝国であろうとするアメリカにたいして、地球的な抵抗が生じているからであり、「ヨーロッパは、自らを作り直し、アメリカ合衆国の覇権主義的な一 方通行主義(ユニラテラリズム)とは一線を画し、そこから袂を分かつと同時に、世界にあって、アラブ・イスラーム世界同様にいつ何時でも、〈来たるべき民 主主義〉を達成する用意がある勢力とともに、新たな責任を担おうとしている」(p.83)と判断するからである。
デリダがグローバリゼーションが「生じていない」と主張するのは、文明はあくまでも多元的なものであり、多元的なものでありつづけるべきだと考え るからである。「多元性といっていも私は他者性という意味て使っていますが、差異の原理、他者性への敬意、これらのは文明の根源とも言えます。だから私 は、均質て普遍的な文明というものは想像できません」(p.108)と語るのである。
短い対話ではあるが、『他者の言語』『たった一つの、私のものではない言葉』「信仰と知」『マルクスの亡霊たち』などの書物のエッセンスが、イス ラーム世界との対話という形で表明されていて、分かりやすい。
【書誌情報】
■イスラームと西洋—ジャック・デリダとの出会い、対話
■シェリフ,ムスタファ/著
■小幡谷友二/訳
■駿河台出版社
■2007/10/10
■165,17p / 21cm / A5
■ISBN 9784411003775
■定価 1785円
●目次
序論 何にもまして友情が大切である
第1章 諸文明の未来
第2章 討論
第3章 アルジェリア人としての経験と思い出
第4章 東洋と西洋、同質性と差異
第5章 不正行為と急進的潮流
第6章 区別するべきか、関連づけるべきか?
第7章 進歩は完全である一方で不完全でもある
結論 私たちの生活には異なる他者が不可欠である
対談後記 南海岸からのアデュー、ジャック・デリダへ
 →bookwebで購入
→bookwebで購入