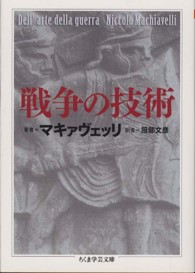→bookwebで購入
→bookwebで購入
「目の間違いが、役に立つ」
筆者の知り合いに探偵小説作家がいるのだが、この方は会議の最中に物思いにふけるような遠い目になるときは、たいてい探偵小説のトリックを考えて いる。あるいは深夜の新宿三丁目のまったりしたバーで、悲しげな無言とともに壁などを見つめているときも、頭にあるのはトリックのことだ。
おそらく世の中の探偵小説作家たちはみなそうなのだ。いかにも深い自己省察にふけるようでいて、隙あらばトリックのことを考えている。トリックにはつきせぬ魅力がある。人は騙されるのも、騙すのも好きなのだ。
本書には人の目がいかに騙されやすいかが、豊富な例とともに詳しく示されている。目は人間の緻密で鋭敏な知性を示す知覚器官として近代文化の中枢 を担ってきたが、ときにコロッと騙される。止まっているのに動いて見える、同じ色なのに違って見える、小さいはずなのに大きく見える……。いわゆる「錯 視」である。探偵小説のトリックを助ける素材としても、おそらく錯視は王道をいくものだろう。
正確な言い方をすると、錯視とは「物理的量と知覚される量との間に存在する乖離を指す」(45)とのこと。筆者はこのところ凝視に凝っていたの で、その延長で錯視のことも気になってきたが、凝視とちがって錯視は学会で発表されたり、Best Illusion of the Yearなどというコンテストまであって、華やかで楽しそうである。「凝視学会」とか、「凝視コンテスト」などというものは聞いたことがないし、あったと してもきっと陰気なものにちがいない。
人が「錯視」に寄せてきた関心は深く古い。おそらくそれは人間の知性のあり方そのものを体現している。本書に収められている錯視例の多くにはしっ かり発見者の名前がついて、さながら「古典的錯視アンソロジー」である。錯視コンテストでも「見事な錯視ですなあ」「いや、ありがとうございます。長年の 努力が報われました」といった会話が交わされているにちがいない。錯視などという言い方をすると、何しろ「目の間違い」を示すわけだから、失敗、愚かさ、 病いなども含意されそうだが、実際には、錯視と出会うことでこそ私たちは人間の特性を見出してきた。本書でも触れられているように、錯視との遭遇は人を大 いなる知的興奮へと導くのである。おそらくそれは錯視が「知ることについて知る」ための入り口となってきたからだろう。遠く哲学へとつながる「知を知りた い」という野望の発端には、「目の間違い」があった。
錯視についての本は数多く出版されているが、本書の特色のひとつは「人はなぜ錯視するのか」という難しい領域に果敢に踏みこんでいることだろう。 土台になっているのは進化論的な考え方だから、必ずしも証明ができるわけではないのだが、なるほどという指摘はいくつもあった。たとえば著者は次のように 言う。
…大きさや角度などの空間的特性に関する錯視は、進化の過程での自然環境の中で接することがないような構図の幾何学図形の観察で生じやすい。平面上に描画された幾何学錯視図形や不可能図形などは、そうした図形の典型例である。(114−115)
たしかに、人間にとって平面との出会いは、立体との出会いよりもずっと遅れて発生したものだ。今、私たちは立体的環境に足を踏み出すことなく、紙 にせよ、スクリーンにせよ、いかに平面上ですべてを理解し処理するかに多大のエネルギーを注いでいる。ときには、立体的環境に直接手を伸ばしたほうがはる かに簡単なときでさえ、である。「省略し縮減し図示する」というのが近代のひとつのキーワードとなってきたのだ。しかし、そのような平面との付き合いは人 間にとってはまだまだ珍しい新しいものでもある。そして珍しく新しいだけに、初期不良が生じやすい。私たちにとっては、立体との付き合いの方がはるかに馴 染みが深いのである。著者は写真を用いた錯視の例に言及しながら、「これらの写真観察で生じる錯視は、進化の過程で獲得された、立体を見るための仕組み が、平坦な画像の観察に誤って適用されたことで生じたのだろう」(115)と言っているが、たしかに平面を理解するのに、誤って立体を知覚するときの要領 でやってしまうという説明には説得力がある。
また、このような進化論を背景とした考察の中では、「錯視は実は人間にとって合理的な選択なのかもしれない」という主旨の見解も提示される。筆者もおおいに同意する。
生存のためには、何でも「正しく」見えればよいわけではない。たとえ正確さが犠牲にされて、全体的な構造として は破綻しているような見えが得られたり錯覚が生じたりしたとしても、生存にとって十分な特性さえ見間違えず、大雑把な構造的特性の情報が得られれば生き 残っていける。逆に、時間や労力のコストをかけて錯覚が生じないようにする戦略は、そもそも解にたどり着くのが困難である上、生存における合理性に欠ける のかもしれない。(114)
筆者にとって意外だったのは、高速道路などを走る車輪が逆方向に回転して見えるようなおなじみの錯視について、必ずしもその原因が突き止められて いないということである。これは「ワゴン・ホイール錯視」と呼ばれているそうだが、明滅している光の下で特定のホイールが誤って関係づけられるような状況 ならともかく(ジブリの展示にありますね!)、自然光のもとでなぜそのような錯視が生ずるのかははっきりわかっていないそうである。おそらくは私たちの視 覚処理過程の「周期的特性」に原因があるのではとの説が有力だそうだが、このような身近な錯視でも案外すべてがわかっていないというのはかえって、こちら の知的好奇心をかき立てる。
本書の後半では運動と色彩をめぐる錯視が中心的な話題になる。いずれも今何かと話題になるテクノロジーと深く関係したホットな領域である。ここで も「運動表象の惰性」(動いている対象の位置が進行方向側に行きすぎて見える)、「コントラスト錯視」(明るさや色相の見え方が、空間や時間における相対 的な関係によって決定される)、「同化現象」(違う色が同じように見える)といった代表的な錯視についての踏みこんだ解説が、短いスペースで手際よくなさ れるが、説明を読みながらあらためて思うのは、このような錯視が目にかぎらず私たちの知の領域全般を覆っているということである。私たちの知は、「進行方 向側に行きすぎる」ことがあるし、「相対的な関係によって決定される」こともあるし、その逆に「違う色が同じように見える」こともあるのだ。
もちろん、だから気をつけろ!というような単純な議論ではない。私たちはそうした人間の特性と付き合わざるを得ないし、おそらくそれがかえって役 に立つことだってある。巻末でのいわゆる「色覚異常」についての著者の見解も、そういう意味では冷静で合理的なものだ。かつて「色盲」と呼ばれた、通常よ りも少ない色しか見ない「2色覚者」に対する見方は、逆に通常よりも多くの色を見る「4色覚者」もいることを知らされるとがらっと変わるはずである。色覚 のタイプを越えてわかりやすい色彩を提供する「ユニバーサルデザイン」という考え方も、今後はおおいに普及していくだろう。
 →bookwebで購入
→bookwebで購入
![]() マイ本棚登録(0) レビュー(0) 書評・記事 (1)
マイ本棚登録(0) レビュー(0) 書評・記事 (1)