2012年01月03日
『愛国心—国家・国民・教育をめぐって』市川昭午(学術出版会 日本図書センター〔発売〕 )
「「愛国心」をめぐる議論の網羅的な整理」
本書は、教育学の碩学により、「愛国心」をめぐる社会理論、現実政治の動向、および教育を中心としたその制度の来歴など、極めて広範な論点を網羅しつつ書かれた大部の著作である。とりわけ、しばしば忘却されてしまいがちな、歴史的な文脈性、語義的な定義、また法制度におけるその取扱いにまつわる丁寧な記述が続く。
こうした記述と整理により、若い世代にとっても、愛国心について学習する際の基礎を提供する書物である。
著者は愛国心にまつわる大部のリーディングス(『文献選集≪愛国心≫とき教育』13巻、『資料で読む戦後日本と愛国心』3巻)の編者でもある。
その内実をすべてレビューすることは困難であり、ここでは評者が特に気になった論点をピックアップしつつ、コメントをさせて頂くこととしたい。
1)現在におけるナショナリズムの盛り上がり
ここに至るまでの歴史的文脈、とりわけ戦後すぐには左翼の側がむしろ積極的に「愛国」を唱えていたこと、右翼の側においては「忠君」概念が溶解していった こと、後者の背景としての天皇制の変容やアメリカに対する評価の混乱などの整理は、現在しばしば忘却されている点である。
その後、著者も指摘しているように、70年代中盤から90年代中盤にかけての「私生活優先主義」により、政治的関心そのものが薄らぎ、日本の文化的特殊性の肯定論などが流行したとはいえ、愛国心論議は下火だった(46)。
しかし90年代に「新しい教科書をつくる会」の活動が活発化した。その後は、インターネット・ナショナリズムの盛り上がりなど「若者の右傾化」が論じられるようになった。こうした認識を著者と共有した上で、三点ほど指摘させて頂きたい。
・「戦後民主主義」に対する批判意識
保守論壇では、かつてから文字通り「戦後民主主義批判」が行われてきた。しかし、私と同世代あるいは以下の人々と話をしてみると、「戦後民主主義」への不満と、本来はその欺瞞を批判して登場したものであるはずの、「新左翼」への不満が混同されているように思う。
評者自身、国家から独立した市民社会を重視した「戦後民主主義」の潮流には、現在を生きる若い世代にも学ぶ所が多いと思う。その反面、1970年前後に学 生運動が終わった後、文化・学術の面で大きな影響力を保つことになった新左翼の諸潮流には、あまり現代的意義を感じられない。
両者が混同されることによって、若い世代に、過去の知的営為の一切を無用のものとする、一種の「反知識主義」が蔓延していくことに、評者は一抹の危惧を抱いている。
・弱者の「癒し」や「プレカリアート」
孤立感・不安感をバネとした、「癒し」「プレカリアート」両者の運動に共通しているのは、上記の意味での「反左翼」であり、それに対し左派知識人が「悪しきナショナリズムの復活」というレッテルを貼る、という形で論争が進んできた。
これらの運動に含まれる「自分たちの不安をマスコミや知識人が正しく代弁していない」という不満が、「マスコミや政治権力が左翼に支配されている」という 陰謀論と結びついた「反左翼」となっており、それが近隣諸国に対する敵対意識などとして表出していることである。それに対する批判的応答が「ナショナリズ ムだから良くない」という形式を取る、という図式となっている。
(このことは、震災以後のマスコミ不信の一つの表れとしての「反韓流デモ」などでも引き継がれている。)
これらの論争は本来、近隣諸国に対する態度など関係がなく、「ナショナリズム」にまつわる問題でもないはずである。真の議題は、「不安」を解消するための 社会保障や雇用の問題であり、またそうした「不安」を社会全体の問題として提示するための、語彙・知的文脈が存在していないということである。
不安を訴える側も、それを批判する側も、いまだに「ナショナリズム」という枠組みしか持っていないということ自体が問題であり、それは70年代中盤以後の 「私生活優先主義」の中での「政治の空洞化」を背景としたものだろう。これ以後、新左翼と保守派の論争などにおいて、政治を語る言語が「ナショナリズムの 是非」以外に存在しなくなり、いまだにその認識枠組みが残存しているということではないか。
こう考えると、危惧すべきなのは、愛国心が盛り上がっているか否かということより、「公共的な参画」とは何か、それがいかにして可能か、というようなことが、現在に至るまで日本では不明確であることである。
また、それを試みようとすると、いつの間にか「愛国心」という疑似問題が呼び起こされてしまう言説空間が形成されてきたという点であるように思う。後者は前者を下敷きとした問題であり、後者のみに独立した対応策は存在しないはずである。
2)教育をはじめとする法制度における「愛国心」の取り扱い
上記の点は、本書の白眉とも言うべき、教育をはじめとする法制度における「愛国心」の取り扱いと、それをめぐる議論の混乱にも影を落としている。
1966年の「期待される人間像」、その後の空白を経た1999年の国旗・国家法制定、また2006年の改正教育基本法などにおいて、法制度の中での「愛国心」の取り扱いが議論されてきた、と著者は整理する。
これらの点は、その現実的な影響力の大きさに比して、ナショナリズムにまつわる社会学的研究では看過されがちであり、あったとしても「悪しきナショナリズムを批判する」というもの一色になりがちである。
その中で、教育基本法改正論が実質的に「殉国」を求めたものでありながら、それを欺瞞的にぼやかしていたことの指摘(319)、他方で国旗国歌反対論が、 代案を提示せず、菊の紋章という過去の軍国主義の本質をも無視したまま、いたずらな反対論を繰り返していることへの批判(325-6)などは、評者にとっ ても大変刺激的な指摘であった。
著者の整理によれば、これらの論争の通奏低音をなしてきたのは、「愛国心」の対象が、「文化的な共同体」なのか、国家という「統治機構」なのか、という区 別であった。古くは、保守派の本音が後者であり、また左翼は前者の側面も一緒くたに否定していた。しかし近年では、左右ともに、前者を是とし後者を否とす る議論が多い。
しかしながら現在でも、保守派の側は「文化的な共同体」の再建を唱えながら、外交的にはアメリカ追従であり、また産業界と結託し、新自由主義・グローバル化を推進しており、主張が矛盾している、と著者は評価する。
他方で左翼の側は、近隣諸国への同情ばかりが目立ち、かつてのような「国民の共感」そのものを否定するような思考が残存していると同時に、近隣諸国や途上国のナショナリズムに対し肯定的であるという矛盾が存在する(367-71)。
評者は、ここでも本来の論点は、「公共的な参画」なのではないかと考えている。
保守派は、これを「愛国心」に仮託することでしか維持・復権できないと考えているが、それはおそらく間違いである。
他方で、左派はかつて、「国家」の全否定と一緒くたに、「公共」という問題系をも捨て去ったのではないか。若い世代の左派が、格差問題などとからめて再考をうながしているのも、この点である。
「愛国」と「公共」は、ハーバーマスの議論にも見られる通り、まったく別の問題系に属する。それを無邪気に一致させてしまうという言論布置が、過去の左右両方に共有されてきたのであり、そうした形の左右対立そのものの意義が現在では消失しつつある。
この意味で、(本書末尾で著者が考察を加えている)「愛国心」を超えた世界政府が実現するか否かという問題よりは、「公共とは何か」という問題系を復権させることの方が、筆者は重要なのではないかと考えている。
単純に言えば、軍国主義への回帰がもはや支持を得られないのはもちろん、対米従属でありグローバル化推進と伝統主義を同居させているという保守の矛盾は、もはや明らかである。
他方で「国家」そのものを全否定してきた新左翼以後の日本の左派の論理も、継承できるものではない。
私以下の若い世代は、「政治」や「社会参加」といったことをたとえ考えたとしても、それを行動に移す際の「リソース」が、言語的にも組織的にも、存在しない状態が続いている。
唯一存在していたのが、「韓国や中国に同情するか否か」という点であり、これだけが「政治」を実感でき、行動を喚起できるものとなってきた、という第一段階の問題がある。
そして第二段階の問題として、本文にも引用されている辻大介が指摘しているように、すでに「韓国や中国に同情するか否か」という問題にすら関心のない世代 が、大量に出現している。これは唯一の「政治」的議題すら消失した状態であり、若い世代に対していかに社会への参画の実感を担保するかという、喫緊の問題 が存在している。「愛国心教育」は、たとえそれがなされても、この問題への対処にはなり得ないだろう。
またナショナリズムそのものについて付言すれば、このような文脈において、「ナショナリズム」や「愛国心」がもはや疑似問題という側面の色濃くなった日本 において、著者も議論に視野に入れている「リベラルなナショナリズム」という概念は、改めて論じられる価値が高いのではないか。
「リベラルなナショナリズム」の対義語はおそらく、H.コーン以来の分類を参考に言えば「被害者意識のみによる結束」(282)たる「脱植民地ナショナリズム」である。
日本と韓国・中国におけるナショナリズムの軋轢の背後にも、この両者が倫理的に区別されていないという問題がある。この意味で、「良い/悪い」ナショナリ ズムの規範的区分は、ヨーロッパの文脈においてはもう古いかもしれないが、日本およびその近隣諸国では、議論されてしかるべき問題なのではないかと筆者は 考えている。
保守派の言う、人類愛や国際貢献につながる「愛国心」は、保守派の考えているようには実現しないことが明らかであり、それよりも「公共的な社会参画」の道 筋をつけること、また各種の少数者問題などについても「リベラルな国民統合」という前提条件をはっきり示すことが重要である。
また国際関係の理解なども含め、「反知識主義」「社会参画への意欲の欠落」の蔓延を防ぐことが最も重要であり、私生活と全体社会とが常につながっていることを、地道に認識させる努力が、教育者には求められているのではないかと思う。
「愛国心」をめぐる問題とは何か、その本質をつかまえるのは容易ではないが、本書は必ずその助けになってくれるだろう。ぜひ手に取って頂きたい一冊である。
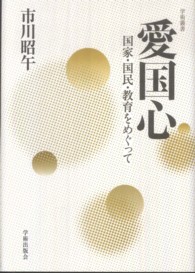
0 件のコメント:
コメントを投稿