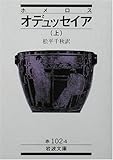カバー文学を読め
2010年8月18日
■王様芥川 めちゃうま太宰
鼎談(ていだん)にも参加した湯川潮音さんの最新作「Sweet Children O'Mine」はカバーアルバムの傑作 だ。オアシスやガンズ・アンド・ローゼズなどの、セックスでドラッグでロックンロールな暑苦しい曲を見事に換骨奪胎。フォークの森に住んでいる妖精ミュー ジックに昇華した。カバーするならこれぐらいしなきゃね、の好例だ。
ポピュラー音楽の歴史は、カバーの歴史でもある。オリジナルをリスペクトしつつ大胆に変奏。かえって曲の奥深くにある本質が浮き上がる。それは、実は小説でも同じなのだ。「カバー文学」と呼ぶ(いま、名付けた)。
日本のカバー文学の王様は、なんといっても芥川龍之介。「羅生門」や「鼻」「芋粥(いもがゆ)」など、平安朝の今昔物語からアイデアを得たものが多数ある。「芋粥」にはロシアの文豪ゴーゴリの影響もあるはずで、さすがの大読書人。
太宰治は、実はカバーもめちゃくちゃうまい。「カチカチ山」「浦島さん」でのブラックな再解釈や、シェークスピアに挑んだ「新ハムレット」、「わたくしのさいかく、とでも振仮名(ふりがな)を附(つ)けたい気持ち」で書いた西鶴のカバー「新釈諸国噺(ばなし)」など。
■愛あふれる深読みゆえ
中でもカバー文学の極北が「女の決闘」だ(いま、決めた)。
元々は19世紀ドイツの小説家オイレンベルクが著した小品で、森鴎外が訳した。その訳本をカバーしたもので、分量が数倍に増え ている。出番のなかった牧師に最後、決めぜりふを言わせるなど、太宰ならではの技のデパート。原作者の「さして高いものでもない文名」をわずかにとどめて いるのが、鴎外、太宰の愛あふれる深読みのおかげなのだから、カバーのだいご味、ここに極まれり。
その鴎外、芥川、太宰、そしてやはり中国古典文学のカバーの名手、中島敦(「山月記」「李陵」)を、現代の京都によみがえらせたのが森見登美彦の『【新釈】走れメロス 他四編』だ。
洋モノではジョイス『ユリシーズ』がいい。ホメロス『オデュッセイア』を物語の枠組みとして借用し、もはやカバーを超えた域。 主人公はギリシャの英雄どころか、ダブリンの寝取られ亭主。革命さえ「分割払い方式でやってくれ」という反暴力平和主義のダメ男くん。だけど、友達になる なら、英雄より絶対こっちでしょうよ。
作品は、すべて文庫で読める。(近藤康太郎)
- 羅生門・鼻・芋粥・偸盗 (岩波文庫)
著者:芥川 竜之介
出版社:岩波書店 価格:¥ 399
この商品を購入する![]() |ヘルプ
|ヘルプ
- お伽草紙 (新潮文庫)
著者:太宰 治
出版社:新潮社 価格:¥ 540
この商品を購入する![]() |ヘルプ
|ヘルプ
- 新ハムレット (新潮文庫)
著者:太宰 治
出版社:新潮社 価格:¥ 540
この商品を購入する![]() |ヘルプ
|ヘルプ
- お伽草紙・新釈諸国噺 (岩波文庫)
著者:太宰 治
出版社:岩波書店 価格:¥ 735
この商品を購入する![]() |ヘルプ
|ヘルプ
- 李陵・山月記 (新潮文庫)
著者:中島 敦
出版社:新潮社 価格:¥ 380
この商品を購入する![]() |ヘルプ
|ヘルプ
- 新釈 走れメロス 他四篇 (祥伝社文庫 も 10-1)
著者:森見 登美彦
出版社:祥伝社 価格:¥ 562
この商品を購入する![]() |ヘルプ
|ヘルプ
- ユリシーズ 1 (集英社文庫ヘリテージシリーズ)
著者:ジェイムズ・ジョイス
出版社:集英社 価格:¥ 1,200
この商品を購入する![]() |ヘルプ
|ヘルプ
- ホメロス オデュッセイア〈上〉 (岩波文庫)
出版社:岩波書店 価格:¥ 840
この商品を購入する![]() |ヘルプ
|ヘルプ
- ホメロス オデュッセイア〈下〉 (岩波文庫)
出版社:岩波書店 価格:¥ 798