2013年07月01日
『「坂本龍馬」の誕生 船中八策と坂崎柴瀾』千野文哉(人文書院)
「龍馬「船中八策」の謎に挑む」
坂本龍馬は幕末維新史のなかで最も人気の高い人物のひとりと言ってもよいだろう。司馬遼太郎の歴史小説『竜馬がゆく』(1963-66年)が龍馬人気の 定着に大きく貢献したことも今日では周知の事実だが、本書(千野文哉『「坂本龍馬」の誕生』人文書院、2013年)は、龍馬の名前とともに語られる「船中 八策」がどのように形成されてきたか、利用できる限りの資料を渉猟して解明しようとした話題作である。NHK大河ドラマ『龍馬伝』(2010年)の冒頭に土佐の新聞記者、坂崎柴瀾という人物が登場したが、柴瀾は本書でも鍵となる役割を演じる。どう いう意味かといえば、「船中八策」として知られる文書を坂本龍馬作として世の中に紹介し、それを普及させたのが他ならぬ柴瀾の作品「汗血千里の駒」であっ たからだ。論証のプロセスはかなり複雑なので、詳細は本書を読んでもらうしかないのだが、先に著者の結論を紹介しておくほうが理解しやすいだろう。
「�「船中八策」のテキストは、明治二十九年刊の弘松宣枝『阪本龍馬』に掲載された「建議案十一箇条」を、坂崎柴瀾が一つ書き・八箇条の形式に整理し、それを最終的に明治四十年刊、宮内省『殉難録稿 坂本直柔』が採録することで「史実」として扱われることになった。
�「船中八策」の名称は、慶応三年六月十五日に土佐の藩論が大政奉還策で確定した、という説から逆算する形で夕顔丸船中の協議が注目され、その協議の成果物を表す「記号」として、維新史料編纂会の中で使用されていた。」(同書、94-95ページ)
歴史家が史料を扱うには慎重にも慎重を期さなければならないのが現代の常識だが、柴瀾の活躍していた頃は、必ずしもこの常識は当てはまらないどこ ろか、まだ確立さえしていなかった。しかも、「船中八策」のなかに、慶応三年の時点で一般的に使われていなかった用語が複数存在するとなれば、その文書の 史料的価値についての疑問はさらに深まるだろう。
もっとも、「船中八策」とよく似ているものに「新政府綱領八策」という文書があり、これは明確な日付・署名がある歴とした龍馬の自筆文書である。著者の 立場は、基本的に龍馬の国家構想はこの文書を基づいて評価すべきだというものだが、「船中八策」と比較して、重要な相違がある。すなわち、「大政奉還」の 条文がないのである。大政奉還は龍馬でなくとも他に唱えるひとが少なからずいたらしいのだが、著者は、そもそも、龍馬が紋切り型の「大政奉還論者」であっ たこと自体を疑っている。
「これまでの龍馬本の多くは、龍馬=大政奉還論者=平和革命論者、という前提条件を当然のことのように設定し、龍馬の武断的言動は大政奉還拒絶という最悪の事態に備えた『保険』であり、決して彼の本意ではないのだと説明してきた。
確かに『保険』ではあるのだが、・・・・・・龍馬にとってはむしろ拒絶後の武力展開こそが想定されるシナリオであり、龍馬は明らかに土佐の武力行使勢力の一翼を担う存在だったのである。」(同書、43ページ)
龍馬は脱藩浪士であり、「世界の海援隊でもやりたい」という自由人のイメージで彼をみてきたひとにとっては、この主張は受け容れがたいだろう。し かし、著者は、浩瀚な文献渉猟を通じて、龍馬が薩長土の少なくとも対等の関係を維持することを重視していたこと、それゆえ、薩長芸三藩の出兵協定を知った とき、龍馬が土佐が薩長の後塵を拝さないように出兵に向けて尽力したことを明らかにしている。「筆者は最後まで龍馬は『土佐山内家家来・坂本龍馬』であっ たと考えている。龍馬は土佐を捨てた、あるいは土佐に捉われない自由人であった、というイメージをお持ちの方が圧倒的に多いと思うが、筆者はそれを採らな い」と(同書、283ページ)。確かに、「数年間東西に奔走し屡々故人に遇て路人の如くす。人誰か父母の国を思ハざらんや」(土佐山内家・溝渕廣之丞に宛 てた書簡より、慶応二年十一月)という言葉には、龍馬の望郷の念が表れているといえそうだ(同書、283ページ)。
ところで、本書は先ほど名前の出た坂崎柴瀾という人物についても詳しい経歴を紹介しているが、ここでは、複雑さを避けるために、彼が板垣退助の政治的立 場に近く、『土陽新聞』という自由党系の新聞の記者をしていたこと、そして、板垣がフランスから持ち帰った「政治小説」という手法を借りて、龍馬を描いた という事実のみを再確認しておきたい。著者はいう。「柴瀾はただの娯楽作品や評伝を書いたのではない。龍馬は自由党のプロパガンダに利用できる人物として 柴瀾によって『発見』されたのである」と(同書、121ページ)。
もちろん、柴瀾に公正を期すためにも、彼が次第に「史料に語らせる」というスタンスをより重視するようになり、それがのちの維新史家としての坂崎柴瀾の 誕生につながったことを追記しなければならないが、少なくとも「汗血千里の駒」という作品が厳密な意味での史書ではないことは間違いない(注1)。
著者は、司馬遼太郎の歴史小説に対しても類似の見解を提示している。
「よく知られているように、司馬龍馬は昭和三十年代後半、高度経済成長期の日本の価値観を体現したキャラクターである。入れ札で選ばれた大統領が下 女の給金を心配する国家を作ろうとする『民主主義者』龍馬。経済を重視し海外雄飛を志向する『ビジネスマン』龍馬。そして何よりも無血革命を成し遂げよう とする『平和主義者』龍馬。
司馬のビーズの選び方、そして糸通しが絶妙なために、司馬の物語は戦後の日本人の記憶を支配し、我々に龍馬はこのような人だった、と信じ込ませてしまったのだ。」(同書、10ページ)
著者は、本書の執筆に三年半の時間がかかったという。しかも、現在は、通信制の大学院で歴史を学びつつあるとはいえ、東京のテレビ局に勤務する多 忙な人だ。いかに内容が龍馬ファンを怒らせるようなものを含んでいたとしても、龍馬が本当に好きでなければ、このような本は書けないだろう。その正直な思 いは、本書の「おわりに」の中に明瞭に表れている。
「本書は龍馬ファンからすると看過出来ない論旨が並んだはずだ。「船中八策」はなかった、龍馬は西郷を一喝しなかった、龍馬は新政府に入る積りだっ た、等々。龍馬ファンの一番琴線に触れるエピソードばかりだ。折角最後まで読んでいただいたのに申し訳ない。人にこんな話をすると必ず言われるのが「本当 にお前は龍馬が好きなのか」という一言だ。もちろん大好きに決まってます。好きだからこそ龍馬の本当の姿が知りたいし、アカデミズムの中にも龍馬を置きた いのだ。」(同書、284ページ)
本書には、龍馬についての従来のイメージを覆すような発見が随所にみられるので、それだけでも楽しい読み物に仕上がっているが、龍馬関係の史料の解読は ひとつではないので、本書のテーゼをめぐって活発な論争につながればさらによいと思う。著者もそれを期待しているに違いない。その意味で、本書は龍馬ファ ンの必読書である。
1 幕末維新史には関係ないが、ついでに紹介しておく。薩摩に滞在していた龍馬とおりょうが二人で霧島登山に出かけたことはよく知られているが、柴瀾の作 品では、おりょうが書生を連れて登山し、天の逆鉾をひとりで抜いたことになっている。本書によれば、柴瀾は実は「急進的な女権拡張論者」で、おりょうをそ の模範例として描くことによって女権拡大を図ろうとしたのだという(同書、177-181ページ参照)。
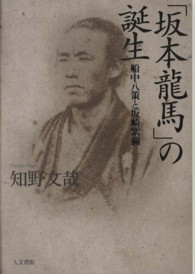
0 件のコメント:
コメントを投稿