2011年02月15日
『複合戦争と総力戦の断層−日本にとっての第一次世界大戦』山室信一(人文書院)
本書で、著者、山室信一は新たな一歩を踏み出そうとしている。京都大学人文科学研究所の共同研究「第一次世界大戦の総合的研究に向けて」は、開戦100 周年にあたる2014年に最終的な成果を世に問うことを目標として、2007年にスタートした。著者にとっては、個人的にもうひとつの意味がある。京都大 学での最後の共同研究という意味である。その意味で、なんらかのまとまりをつけようとしているのかと思ったら、とんでもない間違いである。
「あとがき」で、著者は、本書をつぎのように自分自身の研究のなかに位置づけていることを述べている。「何よりも私自身が次の課題としている第一次世界 大戦における「世界性」と「総体性」とは果たして何であったのか、という問題へ向けて進むに際して、立ちはだかっている壁に挑むために不可欠な、足元の地 固め作業でもあった。その意味で「日本にとっての第一次世界大戦」を「戦争と平和の世界史の文脈に配置する」という私自身の最終課題に向けた歩みは、今こ こから始まる。本書は、その意味でけっして結論ではなく、あくまでもスタートラインを画したものにすぎない」。
本書やつぎの課題、最終課題は、これまでの著書、とくに最近著の『日露戦争の世紀−連鎖視点から見る日本と世界』(岩波新書、2005年)や『憲法9条 の思想水脈』(朝日選書、2007年)で、著者が明らかにし、課題としたものを考えると、よりいっそう理解できる。たとえば、第一次世界大戦後に戦争違法 化を目指して制定され、日本を含む世界63ヶ国が参加した1928年の不戦条約を、真っ先に無視して「防衛」を理由に1931年に満洲事変をおこし、その 後も「事変・事件」の名の下に「防衛」のための日中戦争・「大東亜戦争」を展開した日本の原点のひとつが、第一次世界大戦にあったことを想定していること が感じられる。それは、「遠き戦火」であったがために、現実味を帯びなかったからなのだろうか。
著者は、「はじめに」で、本書では「何よりもまず日本にとっての第一次世界大戦とは何であったのか、を明らかにすることを課題としたい」と述べ、「日本 にとっての第一次世界大戦とは、対独戦争、シベリア戦争という戦火を交えた二つの戦争と、日英間、日中間、日米間の三つの外交戦からなる複合戦争として存 在していたと捉え直すべきではないか」と提起している。
さらに、つぎのように自身への課題を明確にしている。「第一次世界大戦を複合戦争として捉えることが可能であるとするなら、その期間は一九一四年八月の 対独戦争参戦からシベリア戦争時に占領した北樺太から撤退を終えた一九二五年五月まで、断続的であったとはいえ一〇年九カ月にもおよび、大正時代一五年の 大半は第一次世界大戦期であったといえることになる。それはヨーロッパにおける第一次世界大戦の期間である四年三カ月の二・五倍余に達するのである。その 決して短期の戦争とは言えないはずの日本にとっての第一次世界大戦の実相とは、果たしていかなるものとしてあったのだろうか。さらに第一次世界大戦の世界 史的重要性については戦争形態が総力戦へと転換していったことに求められてきたが、日本ではそれをいかに意識して対応し、それは日本社会をどのように変容 させていくことになったのか−その問いに答えるための歩みをここから踏み出してみたい」。
本書の結論は「はじめに」に記しているとおりなく、スタートラインとして「おわりに−「非総力戦」体験と総力戦への対応」で論点を整理している。その前 に、「日本にとっての第一次世界大戦は二つの実戦と三つの外交戦の複合戦争としてあった」ことを、つぎのようにまとめている。「二つの実戦は、重砲や機関 銃、無線通信や飛行機などの新兵器を試用したとはいえ日露戦争と同じ戦争形態の延長上にあり、三つの外交戦は「力こそ正義Might is right」という認識を基盤に、権益配分を秘密外交と威嚇外交によって競う旧外交の手法を用いて争われた。すなわち、日本にとっての第一次世界大戦体験 とは、実質的に非総力戦であったと言うことができる。しかし、けっして総力戦という戦争形態の変化に全く無関心でありえたわけではなかった。そうした非総 力戦と総力戦との接続と断絶の諸層については別稿を期すとして、今は論点だけをまとめておきたい」。
ヨーロッパでは、第一次と第二次の連続性が重視されて、1914〜45年の「30年戦争」として理解されることがあるのにたいして、日本では「アジア・ 太平洋戦争」をせいぜい「15年戦争」として捉えている。著者は「あとがき」で、日本にとっての第一次世界大戦のつかみ所のなさの理由をつぎのように述べ て、その歴史観に警告を発している。「第一次世界大戦を日独戦争の局面でのみ捉えて、そこで生じたイギリスや中国そしてアメリカ、ロシア(ソ連)との外交 関係を全く異なった次元の問題として議論し、さらに第一次世界大戦の重要な一環であったはずのシベリア戦争を反革命干渉戦争という次元でのみ語ってしまっ てきたこと、そこに第一次世界大戦に関する意識の希薄化と歴史認識の空白を招いてしまった大きな原因があるのではないか、という想いが日々強まってきた。 もし、そうした憶測が的外れでないとするなら、「見えない戦争」、「隠された戦争」という位相をも組み込んで初めて「総体としての日本にとっての第一次世 界大戦」が朧気ながらでも姿をみせてくるのではないか……。そして、その無意識化の背後で着々と進んでいた国際環境と総力戦体制への地層での変容を捉える ことなしに、単に一九三〇年代以降の表層的言説をもって日本がアジア・太平洋戦争(第二次世界大戦)に不可避的に踏み込まざるをえなかったと説く昨今の歴 史論議は根底において危ういのではないか……」。
本書は、著者が「あとがき」の冒頭で述べているように、この「レクチャー」シリーズの本来の目的である「広く一般の読者に対し、第一次世界大戦をめぐっ て問題化されるさまざまなテーマを平易に概説する」ものからは外れ、自身への課題を中心としたものになっている。それだけに、「総力戦」である共同研究の それぞれのメンバーのなすべきこと−著者の課題との絡みと課題から抜け落ちていること−が、本書から明らかになったように思える。著者は、「おわりに」 で、「一般には総力戦については軍事力とともに経済力、科学力、精神力などを結集しつつ、ひたすら消尽つ続ける物量戦となるために、持久消耗戦となる」と 述べている。いましばらく著者とともに、共同研究は「持久消耗戦」が続く。その成果として期待される「第一次世界大戦における「世界性」と「総体性」」 は、これまでの歴史観を覆す可能性をもつとともに、現在直面している問題を考えることにも通じている。
「おわりに」は、つぎのことばで終わっている。「現在、第一次世界大戦からほぼ一世紀を経て、日本と中国とアメリカとの三者関係をめぐる軋轢のなかで、 いかなる外交交渉をもって環太平洋世界における安定的地域秩序を形成していくのかという難問(アポリア)に、私たちは改めて直面している」。「そして、日 本が第一次世界大戦から歩み始めた東アジア世界そして国際社会でのあり方に批判的に対峙した中国に、今ほど、その批判した前車の覆った事実を後車の戒めと する叡智が求められている時はないのかもしれない」。
近代的価値観で近代史を総括するのではなく、現在そして未来へとつながる「世界性」「総体性」をもった東アジアの地域秩序、さらに世界秩序を考えるための歴史観が、「第一次世界大戦の総合的研究に向けて」から生まれようとしている。
「あとがき」で、著者は、本書をつぎのように自分自身の研究のなかに位置づけていることを述べている。「何よりも私自身が次の課題としている第一次世界 大戦における「世界性」と「総体性」とは果たして何であったのか、という問題へ向けて進むに際して、立ちはだかっている壁に挑むために不可欠な、足元の地 固め作業でもあった。その意味で「日本にとっての第一次世界大戦」を「戦争と平和の世界史の文脈に配置する」という私自身の最終課題に向けた歩みは、今こ こから始まる。本書は、その意味でけっして結論ではなく、あくまでもスタートラインを画したものにすぎない」。
本書やつぎの課題、最終課題は、これまでの著書、とくに最近著の『日露戦争の世紀−連鎖視点から見る日本と世界』(岩波新書、2005年)や『憲法9条 の思想水脈』(朝日選書、2007年)で、著者が明らかにし、課題としたものを考えると、よりいっそう理解できる。たとえば、第一次世界大戦後に戦争違法 化を目指して制定され、日本を含む世界63ヶ国が参加した1928年の不戦条約を、真っ先に無視して「防衛」を理由に1931年に満洲事変をおこし、その 後も「事変・事件」の名の下に「防衛」のための日中戦争・「大東亜戦争」を展開した日本の原点のひとつが、第一次世界大戦にあったことを想定していること が感じられる。それは、「遠き戦火」であったがために、現実味を帯びなかったからなのだろうか。
著者は、「はじめに」で、本書では「何よりもまず日本にとっての第一次世界大戦とは何であったのか、を明らかにすることを課題としたい」と述べ、「日本 にとっての第一次世界大戦とは、対独戦争、シベリア戦争という戦火を交えた二つの戦争と、日英間、日中間、日米間の三つの外交戦からなる複合戦争として存 在していたと捉え直すべきではないか」と提起している。
さらに、つぎのように自身への課題を明確にしている。「第一次世界大戦を複合戦争として捉えることが可能であるとするなら、その期間は一九一四年八月の 対独戦争参戦からシベリア戦争時に占領した北樺太から撤退を終えた一九二五年五月まで、断続的であったとはいえ一〇年九カ月にもおよび、大正時代一五年の 大半は第一次世界大戦期であったといえることになる。それはヨーロッパにおける第一次世界大戦の期間である四年三カ月の二・五倍余に達するのである。その 決して短期の戦争とは言えないはずの日本にとっての第一次世界大戦の実相とは、果たしていかなるものとしてあったのだろうか。さらに第一次世界大戦の世界 史的重要性については戦争形態が総力戦へと転換していったことに求められてきたが、日本ではそれをいかに意識して対応し、それは日本社会をどのように変容 させていくことになったのか−その問いに答えるための歩みをここから踏み出してみたい」。
本書の結論は「はじめに」に記しているとおりなく、スタートラインとして「おわりに−「非総力戦」体験と総力戦への対応」で論点を整理している。その前 に、「日本にとっての第一次世界大戦は二つの実戦と三つの外交戦の複合戦争としてあった」ことを、つぎのようにまとめている。「二つの実戦は、重砲や機関 銃、無線通信や飛行機などの新兵器を試用したとはいえ日露戦争と同じ戦争形態の延長上にあり、三つの外交戦は「力こそ正義Might is right」という認識を基盤に、権益配分を秘密外交と威嚇外交によって競う旧外交の手法を用いて争われた。すなわち、日本にとっての第一次世界大戦体験 とは、実質的に非総力戦であったと言うことができる。しかし、けっして総力戦という戦争形態の変化に全く無関心でありえたわけではなかった。そうした非総 力戦と総力戦との接続と断絶の諸層については別稿を期すとして、今は論点だけをまとめておきたい」。
ヨーロッパでは、第一次と第二次の連続性が重視されて、1914〜45年の「30年戦争」として理解されることがあるのにたいして、日本では「アジア・ 太平洋戦争」をせいぜい「15年戦争」として捉えている。著者は「あとがき」で、日本にとっての第一次世界大戦のつかみ所のなさの理由をつぎのように述べ て、その歴史観に警告を発している。「第一次世界大戦を日独戦争の局面でのみ捉えて、そこで生じたイギリスや中国そしてアメリカ、ロシア(ソ連)との外交 関係を全く異なった次元の問題として議論し、さらに第一次世界大戦の重要な一環であったはずのシベリア戦争を反革命干渉戦争という次元でのみ語ってしまっ てきたこと、そこに第一次世界大戦に関する意識の希薄化と歴史認識の空白を招いてしまった大きな原因があるのではないか、という想いが日々強まってきた。 もし、そうした憶測が的外れでないとするなら、「見えない戦争」、「隠された戦争」という位相をも組み込んで初めて「総体としての日本にとっての第一次世 界大戦」が朧気ながらでも姿をみせてくるのではないか……。そして、その無意識化の背後で着々と進んでいた国際環境と総力戦体制への地層での変容を捉える ことなしに、単に一九三〇年代以降の表層的言説をもって日本がアジア・太平洋戦争(第二次世界大戦)に不可避的に踏み込まざるをえなかったと説く昨今の歴 史論議は根底において危ういのではないか……」。
本書は、著者が「あとがき」の冒頭で述べているように、この「レクチャー」シリーズの本来の目的である「広く一般の読者に対し、第一次世界大戦をめぐっ て問題化されるさまざまなテーマを平易に概説する」ものからは外れ、自身への課題を中心としたものになっている。それだけに、「総力戦」である共同研究の それぞれのメンバーのなすべきこと−著者の課題との絡みと課題から抜け落ちていること−が、本書から明らかになったように思える。著者は、「おわりに」 で、「一般には総力戦については軍事力とともに経済力、科学力、精神力などを結集しつつ、ひたすら消尽つ続ける物量戦となるために、持久消耗戦となる」と 述べている。いましばらく著者とともに、共同研究は「持久消耗戦」が続く。その成果として期待される「第一次世界大戦における「世界性」と「総体性」」 は、これまでの歴史観を覆す可能性をもつとともに、現在直面している問題を考えることにも通じている。
「おわりに」は、つぎのことばで終わっている。「現在、第一次世界大戦からほぼ一世紀を経て、日本と中国とアメリカとの三者関係をめぐる軋轢のなかで、 いかなる外交交渉をもって環太平洋世界における安定的地域秩序を形成していくのかという難問(アポリア)に、私たちは改めて直面している」。「そして、日 本が第一次世界大戦から歩み始めた東アジア世界そして国際社会でのあり方に批判的に対峙した中国に、今ほど、その批判した前車の覆った事実を後車の戒めと する叡智が求められている時はないのかもしれない」。
近代的価値観で近代史を総括するのではなく、現在そして未来へとつながる「世界性」「総体性」をもった東アジアの地域秩序、さらに世界秩序を考えるための歴史観が、「第一次世界大戦の総合的研究に向けて」から生まれようとしている。
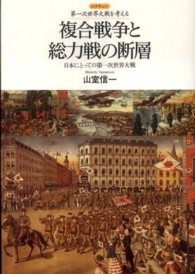
0 件のコメント:
コメントを投稿