2012年10月09日
『森敦との時間』森富子(集英社)
「これというものをひとつ書けばいい」
森敦は、その実人生の「物語」で知られた人である。作家を志して旧制一高を中退、菊池寛や横光利一の推挙で若くして文壇デビュー。太宰治をはじめ 当時の花形作家とも交わり、22歳にして『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』に連載を持った。ところが、その後小説の発表は途絶え、山形、新潟、三重と各地 を放浪する生活が始まる。おもしろいことに、その後も作家の間には森信者が増え続け、小島信夫、後藤明生、三好徹、勝目梓といった人々がしがない印刷会社 に勤める無名の森敦に助言を求め続けた。人呼んで「森敦詣で」。以前、この書評欄でもとりあげた勝目梓『小説家』では、森の独特な振る舞いが次のように描写されている。
あるとき、池袋の居酒屋の二階の座敷で開かれた『茫』の合評会に、主宰者の高田欣一が、見るからに曲者といった印象の眼 光鋭い五〇年配の人物を連れてきた。そうして、その人物はどこか胡散臭い感じを漂わせながら、しかし自信に満ちた断定的な口調で、その号に掲載されている 作品の批評をはじめた。曲者然とした胡散臭い印象とは裏腹に、その批評は犀利である上に、問題の捉え方にきわだった独創性をうかがわせるところがあった。 つまりその人物は、『茫』に掲載されている作品それぞれをタネにして、自身のユニークな文学観を開陳しているのだった。そうしてその場はその人物の独り舞 台のようになっていた。(362-63)
とにかく座談の名手。電話魔。作品への感想を求める作家たちとひとりひとり順番に面会し、思わせぶりな語り口に昔話や文学論を織り交ぜながらも貴 重なコメントをしてくれる。「深淵の帝王」などとも呼ばれた。その森が62歳にしてついに「月山」で芥川賞を受賞することになる。今も破られていない芥川 賞の「最年長受賞記録」である。「とにかくひとつこれというものを書けばいいのだ」というのは森の持論でもあったが、ついにそれを果たしたことになる。
『森敦との時間』はこうして遅いデビューを果たした森の姿を、養女としてその生活を支えた富子の立場から描いたもので、『森敦との対話』につづく 評伝となる。森敦は芥川受賞後、その波乱に富んだ人生や独特の雰囲気が話題になり、原稿の注文だけでなく、テレビ、ラジオの出演依頼も殺到した。住んでい たおんぼろアパートには毎晩のように崇拝者や編集者たちが押し寄せ、狭い四畳半にぎゅうぎゅうになって森の話に耳を傾ける。会社から帰った富子は毎晩その 接待に追われた。缶詰をあけた程度のつまみも、あっという間になくなる。疲れ果てて缶詰めをあける余裕もないときは、鮨を頼むのだが…。
届いた鮨桶を卓袱台の中央に置くと、いっせいに客の箸がのびてくる。二重に並んでいた客が、右半身の一重の列になって、 のばした箸で鮨をつまむ。みな右利きだから右手をのばせばいい。もし左利きがいたらおかしなことになるだろう。チチまでも半身に構えているからおかしい。 (6)
富子自身も作家志望だった。養女になったのも、森敦と同人誌で一緒だった縁からである。しかし、今の引用箇所からもわかるように、本書には作家的 な、文学的な文章を書こうとする暗い情念や執着からついに自由になったような身軽さがある。語る自分の言葉に拘泥することなく、急ぎ足で、さっぱりした気 分で、「まったく何言ってんだか!」というような突き放した口調とともに、「チチ」である森敦をからかうように、文句を言いながらも、愛おしんで語るので ある。途中、文の主語が森敦なのか森富子なのかわからなくなるところもあるのだが、森の最晩年を描いた最終部では、それがくるっと感動的な場面に転換す る。
会議で帰宅の遅い日は、冷蔵庫から料理を詰めたお重を食べる習わしが続いていた。しかし、私の帰宅を待つようになった。食卓に腰掛けて待つ姿を見るのはつらい。(252)
もちろん「会議で帰宅の遅い」のは、会社勤めの富子である。「冷蔵庫から料理を詰めたお重を食べる習わし」は、外食嫌いの森敦のこと。「食卓に腰掛けて待つ」のは森敦で、それを見て「つらい」のは富子。ところがこの場面は、こんなふうに続く。
……食卓に腰掛けて待つ姿を見るのはつらい。わざと大声で「ただいま!」と叫び、冷蔵庫からお重を出し、ビールで乾杯をする。
「これ、飲んでくれないか」
湯飲み茶碗くらいの小さなコップに入ったビールだ。それが飲めない! どうしたのだろう。
「そう」
明るい声で言いながらコップを受け取って、私は一気に飲む。
「美味しかったね」
チチは、さも自分が飲んだかのように言った。(252)
なるほど、こういうことだったのだ。富子の飲んだ一杯のビールを、さも自分が飲んだかのように「美味しかったね」と言うようになった最晩年の森 敦。養女になって一五年、一度も言われたことのなかった「ありがとう」という言葉を頻繁に口にするようになったのもこの頃だ。「美味しかったね、ありがと う」などとも言った。
主語がなくてこんがらかるのは、決して一心同体ということではない。名前が言えないのはどこか関係が不安定なのである。どこか照れくさい。だから 「チチ」なんていう窮余の策で言及する。困った人だけど愛しい。富子にとって森敦は終始「まったくもお」的な存在であった。自宅で散髪してあげたら、前髪 のことで「こんなに、短く切ってしまって!」と大騒ぎ(たしかに写真で見るとふだんの森敦は前髪が長い)。富子が引いた電話なのに「長い」「使うな」と文 句を言うかと思うと、自分では残飯の処理ひとつできない。テレビに出れば、ズボンの裾から下着が見えている。
しかし、こんなふうに「まったくもお」の地点に持ってくるまでには、富子だってきっとたいへんだったのだ。あまりにカリスマ的だった森敦という人 の言葉を、やわらかくほぐしてみせたのは富子の手柄の一つである。たとえば「月山」の生原稿紛失事件がちょっとしたサスペンスまじりに語られる箇所がある が(どこぞの「見目麗しい女性」にでもあげたのではないかと富子は疑ったりする!)、これにからめての以下のような一節がある。
チチは、ノートに書いている。
〈「存在」を意識するとは、失われたものがよみがえる(原文は傍点。以下、太字については同)ということである。失われたものがよみがえる(同)という概 念が如何に重大であるか、これを見ても分ると思う。われわれが「存在」を意識するとき「嘔吐」するとは〈或は「笑う」とか、「絶望」するとか)この失われ (同)、そしてよみがえったものに対して、「嘔吐」するということである。〉(「吹雪からのたより」)
チチの言う「存在」を「生原稿」と置き換えてみる。生原稿という存在を意識すると、失われた生原稿がよみがえってくる。よみがえってくるたびに、絶望的 な気分になるし、ときには笑いが止まらぬほど喜劇的な気分になる。つまり、失われた生原稿に対して、「嘔吐」するのだという。
チチと話した後に、嘔吐することがある。それは胃腸が弱いために起こる生理的な現象だと思っていた。嘔吐するのは、失われた生原稿がよみがえるからだろうか。 (125)
森敦の省察にちょっと横からちょっかいを出して、厳かな「神話」をひっくり返そうとしたとも読める部分だが、最後の下りは逆に意味深長である。何 しろ失われた生原稿には、「女」がからんでいたかもしれないのである。「養女」富子はいろいろと苦しい思いをしていたのかもしれない。
急ぎ足に淡々と語るかのような口調なのに、何度も繰り返し出てくる話題がある。会社からの帰宅時に富子は電車に乗っていられなくなって何度もトイ レに駆け込んだ。何時間もかけて都心から布田まで帰ったこともある。「途中下車病」などと富子はひょうきんに言ってみせるが、今で言うパニック障害だろ う。接待ストレスだけではない。その根本には、折に触れて森敦から「書いてない!」と言われた富子の心の緊張があるように思える。もちろん、それは富子だ けの問題ではない。書けるか、書けないか、というぎりぎりの境地を生きながら懸命に放浪した森敦にとっても、文章で生きるというのは苦しい怖ろしいこと だったのである。
将来を期待されながら原稿が書けず、ついに作家デビューを果たす機会を失ってしまった若き日の森敦。そのことがあったから、芥川賞受賞後の殺人的 なスケジュールを体調を崩しながらも懸命にこなした。一度注文を断ったら、もう来なくなるかも知れない…、そんな恐怖感があった。ついに入院。富子はどん どん仕事を断った。しかし、断ったのは主にテレビやラジオの仕事だった。「そうかあ。もう仕事がないのか」と森敦は寂しそうだったが、富子は「侘びしい境 地になれば、小説が書けるかもしれない」と思ったのである(133)。
下手に文学的になるまい、と覚悟を決めて書いたようにも見える著者の筆が、最後に少しだけ居住まいを正したようになる箇所がある。腹部大動脈瘤で 急死した森敦に霊安室で付き添う富子は、泣き崩れたいのに一滴の涙も出ない。そのとき、隣の部屋から女性の泣き声が響いたのである。
韓国の男性が交通事故死したという。泣き声は途切れることがなく、高く低く響く。チチへの手向けの泣き声のように聞こえる。(262)
天才とははた迷惑なものだとよく言う。傍らにいる人には、本人の分も含めて言いようのない「負担」がかかる。森敦が天才だったのかどうかは筆者に はわからないが、ともかく理解しがたい人を「天才」と呼んですませるのは安易なような気もする。書ける・書けないという地点に踏みとどまり、その苦難を味 わいつづけたからこそ、彼は「書く人」に伝えるべき言葉を持ち得たのではないだろうか。
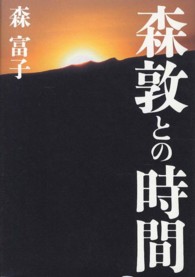
0 件のコメント:
コメントを投稿