2011年09月13日
『4億の少数派−南アジアのイスラーム』山根聡(山川出版社)
「4億の少数派」ということばを、いまわたしたちはどうとらえたらいいのだろうか。まとまれば、なんでもできる数のように思える。この「少数派」という ことの意味と、「少数派」の帰趨がわかれば、南アジアだけでなく、イスラーム世界、全世界の未来もみえてくるような気がした。
著者山根聡は、まず「少数派」の意味を、つぎのようにまとめている。「南アジアが非アラブ圏にあるために、イスラーム世界で南アジアは周縁的存在となっ ている。さらに、四億人にも達する南アジアのムスリムは、九億人近いヒンドゥー教徒の前では少数派となり、「南アジア」の枠組みでも周縁に位置づけられ る」。
そして、この歴史的にも重要な「二重の周縁性」が、今日さらに重要になってきていることを、つぎのように説明している。「南アジアという地域のイメージ で浮かぶ、多宗教、タージマハル、都市の壮麗な城塞、細密画(ミニアチユール)といった文化的な事柄が南アジアのイスラーム文化の一端を示しており、頻発 するテロやターリバーン運動、あるいはカシュミール問題などの現代的問題もまた南アジアのムスリムの一部がかかわり、彼ら自身がかかえる問題でもある。す なわち、この地域の歴史、政治、経済、社会、文化のあらゆる場面でイスラーム的な要素が南アジアに与えた影響の大きさがわかる。これを正面からとらえなお すことは、南アジア研究のさらなる深化をもたらし、南アジアにかんする知識をより多角的に構築できるといえよう」。
本書では、イスラームがはじまったほぼ1世紀後からはじまる南アジアのイスラームの歴史を、年代順につぎの5章に分けて紹介している。
第1章 インド・イスラーム文化
第2章 西欧的近代との出会い
第3章 イスラームの政治運動化
第4章 イスラームと国家の関係
第5章 世界情勢と南アジアのイスラーム
南アジアのイスラーム教徒は、確実にアラブ世界と繋がり、近代ではオスマン帝国を介してヨーロッパ世界とも繋がっていた。露土戦争(1877-78年) のときにはオスマン帝国に義捐金を提供し、第一次世界大戦後にはカリフ制の廃止にともない反イギリスに転じた。もちろん、アラブ世界の原理主義運動とも、 さまざまなかたちで繋がっていた。
また、同じイスラーム世界の「周縁」に位置づけられた欧米、アフリカ、東南アジアなどとも、直接繋がっていた。とくに東南アジアとは歴史的に深く、南ア ジアでイスラーム諸学を学んだ東南アジアからの指導者もおり、南アジア系のイスラーム教徒のコミュニティが東南アジア各地で形成された。このように世界各 地に、数百万の南アジア系のイスラーム教徒がいることを忘れてはならないだろう。
国や地域、時代を越えて全世界のイスラーム教徒と繋がるいっぽう、南アジアの多宗教社会のなかで共存しているようすが、つぎのように紹介されている。 「アジメールのムイーヌッディウーン・チシュティー廟やラクナウー郊外にあるバハラーイチなどには、宗教、宗派を問わず多くの参詣者が訪れる。ベンガルの 民俗芸能バウルの担い手で宗教詩人フォキル・ラロン・シャハ(一七七四?〜一八九〇)もまた、宗教をこえた聖者として現在も支持を集めており、南アジアの 大衆にとっての「宗教」が、教義にとらわれない民間信仰や芸能のかたちで広く浸透し、続いていることを忘れてはならないだろう」。
インドを代表する墓廟、タージマハルは、インド・イスラーム文化を象徴するものといえるが、「ヒンドゥーは例外を除いて、墓を造らない宗教文化をもつこ とから、墓廟の文化はアジアのイスラームの特徴といえる。聖者廟やモスク周辺には宿泊施設などが建設され、周辺地区が発展した。聖者廟にはムスリムのみな らず、ヒンドゥーやスィクなど、宗教、宗派を問わず多くの参詣者が集まった」。「これらインド・イスラーム文化とは、宮廷や都市部で発展した建築や細密画 などの美術、あるいは文学などであって、農村部ではヒンドゥーなど土着の宗教文化や民族文化とまじりあった文化が広がっていた」。
そして、「異なる宗教集団が対立と共存を繰り返してきた」「政治的・経済的な動きと離れた日常では、宗教、宗派を問わずしてまじり合った宗教文化もみら れ」、「これら集合的な習俗を内省的に改革してイスラーム本来の教えにもどろうとする動きが、イスラーム世界で先駆的に起こったのも、南アジアなのであ る」と、イスラーム世界のなかでの南アジアを特徴づけ、つぎのように本書を結んでいる。「これからも四億の人びとは、世界各地の移民とのネットワークを保 ちつつ、南アジア世界のみならず、イスラーム世界全体、ひいては世界情勢にも影響を与え続けるであろう。だからこそ、南アジアのイスラームと四億の少数派 について、知識を深める必要がある」。
著者山根聡は、まず「少数派」の意味を、つぎのようにまとめている。「南アジアが非アラブ圏にあるために、イスラーム世界で南アジアは周縁的存在となっ ている。さらに、四億人にも達する南アジアのムスリムは、九億人近いヒンドゥー教徒の前では少数派となり、「南アジア」の枠組みでも周縁に位置づけられ る」。
そして、この歴史的にも重要な「二重の周縁性」が、今日さらに重要になってきていることを、つぎのように説明している。「南アジアという地域のイメージ で浮かぶ、多宗教、タージマハル、都市の壮麗な城塞、細密画(ミニアチユール)といった文化的な事柄が南アジアのイスラーム文化の一端を示しており、頻発 するテロやターリバーン運動、あるいはカシュミール問題などの現代的問題もまた南アジアのムスリムの一部がかかわり、彼ら自身がかかえる問題でもある。す なわち、この地域の歴史、政治、経済、社会、文化のあらゆる場面でイスラーム的な要素が南アジアに与えた影響の大きさがわかる。これを正面からとらえなお すことは、南アジア研究のさらなる深化をもたらし、南アジアにかんする知識をより多角的に構築できるといえよう」。
本書では、イスラームがはじまったほぼ1世紀後からはじまる南アジアのイスラームの歴史を、年代順につぎの5章に分けて紹介している。
第1章 インド・イスラーム文化
第2章 西欧的近代との出会い
第3章 イスラームの政治運動化
第4章 イスラームと国家の関係
第5章 世界情勢と南アジアのイスラーム
南アジアのイスラーム教徒は、確実にアラブ世界と繋がり、近代ではオスマン帝国を介してヨーロッパ世界とも繋がっていた。露土戦争(1877-78年) のときにはオスマン帝国に義捐金を提供し、第一次世界大戦後にはカリフ制の廃止にともない反イギリスに転じた。もちろん、アラブ世界の原理主義運動とも、 さまざまなかたちで繋がっていた。
また、同じイスラーム世界の「周縁」に位置づけられた欧米、アフリカ、東南アジアなどとも、直接繋がっていた。とくに東南アジアとは歴史的に深く、南ア ジアでイスラーム諸学を学んだ東南アジアからの指導者もおり、南アジア系のイスラーム教徒のコミュニティが東南アジア各地で形成された。このように世界各 地に、数百万の南アジア系のイスラーム教徒がいることを忘れてはならないだろう。
国や地域、時代を越えて全世界のイスラーム教徒と繋がるいっぽう、南アジアの多宗教社会のなかで共存しているようすが、つぎのように紹介されている。 「アジメールのムイーヌッディウーン・チシュティー廟やラクナウー郊外にあるバハラーイチなどには、宗教、宗派を問わず多くの参詣者が訪れる。ベンガルの 民俗芸能バウルの担い手で宗教詩人フォキル・ラロン・シャハ(一七七四?〜一八九〇)もまた、宗教をこえた聖者として現在も支持を集めており、南アジアの 大衆にとっての「宗教」が、教義にとらわれない民間信仰や芸能のかたちで広く浸透し、続いていることを忘れてはならないだろう」。
インドを代表する墓廟、タージマハルは、インド・イスラーム文化を象徴するものといえるが、「ヒンドゥーは例外を除いて、墓を造らない宗教文化をもつこ とから、墓廟の文化はアジアのイスラームの特徴といえる。聖者廟やモスク周辺には宿泊施設などが建設され、周辺地区が発展した。聖者廟にはムスリムのみな らず、ヒンドゥーやスィクなど、宗教、宗派を問わず多くの参詣者が集まった」。「これらインド・イスラーム文化とは、宮廷や都市部で発展した建築や細密画 などの美術、あるいは文学などであって、農村部ではヒンドゥーなど土着の宗教文化や民族文化とまじりあった文化が広がっていた」。
そして、「異なる宗教集団が対立と共存を繰り返してきた」「政治的・経済的な動きと離れた日常では、宗教、宗派を問わずしてまじり合った宗教文化もみら れ」、「これら集合的な習俗を内省的に改革してイスラーム本来の教えにもどろうとする動きが、イスラーム世界で先駆的に起こったのも、南アジアなのであ る」と、イスラーム世界のなかでの南アジアを特徴づけ、つぎのように本書を結んでいる。「これからも四億の人びとは、世界各地の移民とのネットワークを保 ちつつ、南アジア世界のみならず、イスラーム世界全体、ひいては世界情勢にも影響を与え続けるであろう。だからこそ、南アジアのイスラームと四億の少数派 について、知識を深める必要がある」。
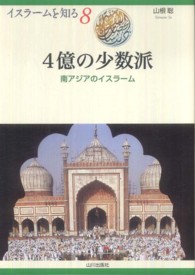
0 件のコメント:
コメントを投稿