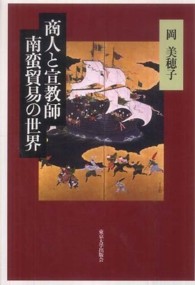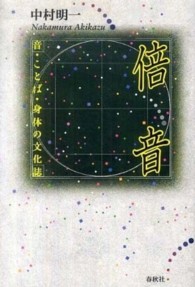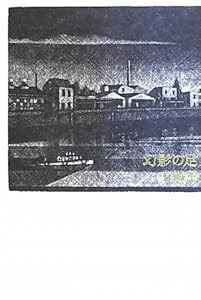2010年12月27日
『一七世紀科学革命』 ヘンリー,ジョン (みすず書房)
マクミラン社の「ヨーロッパ史入門」というシリーズの一冊である(邦訳はみすず書房から)。235ページあるが、本文150ページほどのコンパクトな本で80ページ以上が用語辞典、索引、300冊近い参考文献、訳者解説、日本語の参考文献にあてられている。
入門書とあなどって読みはじめたが、見通しのよい明解な記述に舌を巻いた。
科学革命の解説はまず自然の数学化をどう説明するかがポイントになるが、本書は科学革命以前の天文学はプラトンの流をくむ数学的部分と、アリスト テレスの流れをくむ自然学的部分からなる「混合学」だったと大づかみに把握した上で、プトレマイオスの周天円やエカントは実在ではなく、計算のための単な る補助線とみなされていたとつづける。
プトレマイオスは観測される惑星運動を説明するために数学的なモデルを考案したが、その結果提案された仮設的構築物や作業仮説は、アリストテレス 主義的自然学とは整合性がないと考えられた。人々はプトレマイオスの体系をまるごと拒否してもよかっただろうが、実際にはうまくいく天文理論はプトレマイ オスのものしかなかった。有用なプトレマイオス天文学を使いつつも、同時に天界の本当の姿はアリストテレスの宇宙論に描かれているものに違いないと考える ことで、決着をはかるしかなかった。
アリストテレス自然学とプトレマイオスの天動説は一体のものと見なすのが一般的なので、両者が調停不能な対立関係にあると言われてもぴんと来ないが、よくよく考えればアリストテレスの質的な説明とプトレマイオスの量的な説明は水と油である。
オジアンダーは『天球回天論』出版の実務をまかされると地動説(太陽中心説)=計算の道具説をうたった序文を勝手につけくわえ、コペルニクスの支持者から猛反発を受けたが、計算のための道具という点ではプトレマイオス説も同じだったのだ。
著者はさらに自然学と数学の対立は社会的身分にもおよんでいたと指摘する。自然学を研究するのが大学を出た知識人なのに対し、計算士や建築家、技師はただの数学職人と見なされていた。数学職人の社会的地位は科学革命によって床屋外科医や画家などとともに著しく向上した。
数学的な自然把握が権威を持ちはじめると一つ問題が持ちあがった。アリストテレス自然学は自明の経験的命題から出発するのに対し、数学的命題は素 朴な日常的知識に反するものが多い。たとえばマイナスの数とマイナスの数をかけるとプラスの数になるとはどういうことなのか。数学は人工的な構築物であ り、限られた条件下でしか成りたたないのに、なぜ自然に適用できるのだろうか。
数学的認識の確実性の問題にとりくんだのはカントであり哲学の問題として議論される傾向があるが、著者は哲学論議には向かわず、数学的認識を正当 化したのは実験だと指摘する。数学的モデルと一致する実験結果がえられたら、自然はその数学的構造をとっていると見なすわけである。実際、数学化された自 然科学の権威を確立したのは『純粋理性批判』よりも実験だったろう。
マルクス主義歴史観が全盛だった頃は実験的手法は職人によって生みだされたとされていたが、今日では「職人」と見なされていた実験の担い手は実は 錬金術師だったり自然魔術師だったことが明かになっている。そもそも中世以来、実験は錬金術師や自然魔術師の独擅場であり、実験器具も彼らが考案し、改良 したものだった。
科学革命の最大の達成であるニュートンの万有引力の発見も魔術とかかわっている。ニュートンが錬金術の研究に打ちこんでいたことはよく知られてい るが、科学的な研究にも物活論的や万物照応的な魔術的発想を背景にしていることが明かになっている。たとえば『光学』で白色光を七色のスペクトルに分解し たが、初期の草稿では七色ではなく五色にになっていた。最終的に青色と橙色をくわえて七色にしたのは音階と光のスペクトルを対応させるためだったという。
万有引力の法則は機械的接触のない遠方に直接力が伝わるとしているので、同時代のデカルト派やライプニッツ派の学者からスコラ哲学の「隠された 力」の焼直しだと批判された。ニュートンは表向き、何故ではなく如何にを問うのが科学だとつっぱねたが、裏では魔術的思考にどっぷり浸かっていたことがわ かっている。
著者は最終章でニュートンは実際は突破口を開いたにすぎず、力学はむしろ大陸系の学者によって築かれたと指摘している。ニュートンの虚像を作りあげたのは18世紀の啓蒙主義者であり、17世紀科学革命という概念そのものも18世紀啓蒙主義の産物だったとしている。
本書は内容もすぐれているが、翻訳がひじょうに読みやすい。科学革命を知るための決定版といってよいだろう。