2013年09月29日
『爪と目』藤野可織(新潮社)
「ぜんぶ読ませないと気が済まない小説」
遅ればせながら芥川賞受賞作。当欄でも、すでに大竹昭子さんが取り上げておられる。
読みはじめての第一印象は、こちらの読書のぜんぶを面倒みてくれる文章だな、ということだった。たいていの小説はどこか雑然としているから、読ん でいると風が吹き抜けたり、ゴミが落っこちてきたり、インターフォンが鳴ったりする。それでけっこう気が散ったり、間が空いたり、下手をすると読むのをや めてぼおっとしたりする。そういうところまでが作品の一部と感じられる。
「爪と目」の中でも、文字通り風が立ったり空が見えたり、インターフォンが鳴ったりするのだが、それがぜんぜん雑然とした立ち方や見え方や鳴り方 ではなく、すべてが隙間無くつながっていると思える。まるで隠れた意図でもあるかのように。呪いでもかかっているかのように。一語一語の選択にも神経質な ほどの意思を感じるし、文と文の間にもきっちりプロットがあり、ちょっとゆるくなったかと思うと、すぐにぎゅっとしぼりあげられる。
それがまさに読みどころでもある。この作品にはところどころでぎゅっとしぼりあげられる、その快楽で読んでしまうところがあるのだ。必ずしも意味 ありげな警句などではない。ごくふつうのことばなのだが、どういう加減かそれがワンランク違う響きとともに、ぐいっと割り込んでくる。たとえば次のような ものだ。
父は、できるだけ早くあなたを妊娠させるつもりだった。けれど、うまくいかなかった。(31)
わたしは、ものすごく目がいいから。強度の近視の視界が想像できるくらいに、わたしは目がいいのだ。(33)
でも、わたしがスナック菓子を食べる姿は、わたしが持っているあらゆる未来を食い荒らしているように見えた。(36)
わたしの裸足が踏むコンクリートの床は、場所によってはわたしの足の裏よりあたたかかった。(66)
こういう部分の語調の、その引き締まった強烈さからは、冷たい観察や嘲りも読めるし、断罪や、怒りだって読めるかもしれない。あるいはもっと純粋 な暴力性かもしれない。いずれにしても、何だか得たいの知れないこもった感情性を読みとりたくなる。これは、作品全体に見られる、隙間をみっちり埋めた感 じとも通ずるように思う。読者の視界を隈無く引き受ける精妙さの背後にあるもの。それはいったい何だろう。
その答えを得るためには、これがいったい誰の小説なのかを考えなければならない。この作品、実は主人公が誰なのかが、最初はよくわからない。とくに最初の一文のまわりくどさときたら!
はじめてあなたと関係を持った日、帰り際になって父は『きみとは結婚できない』と言った。
いったいどういうことだろう?——日本語の試験に使いたいくらいだ。何しろ、短い文に「あなた」「父」「君」、そして言外の「わたし」が一挙に出 てくる。読み直してみれば文法的にはわかるだろうが、あいかわらず変な気分は残る。大竹さんがこの作品で使われる「あなた」の不思議さについて「三半規管 をおかしくする」という絶妙の比喩で説明しているので、是非、そちらも参照していただきたいが、いちおう設定としては、視点が三歳の女の子におかれている ということらしい。より正確に言うと、三歳の頃の自分の状況を回想する大人の女がその陰にいる。でも、作中、この大人の女にはほんのわずかしか言及がない (その言及はたいへん意味深い。どうして二の腕をつかんでいるのだろう…〈69−70〉)。
この女の子の母は、謎の事故で死ぬ。残された父は浮気相手だった女性と同居することになった。この女性が「あなた」なのである。父と眼科医で出 会った「あなた」には生活感が希薄で、友人もおらず、人生に対する意思のようなものがあまり感じられない。美人でもない。でも、なぜか男を引き寄せる。 「あなた」は来る者は拒まず、去る者は追わずという態度で、男たちとも何となく付き合ってきた。女の子の父親と同居するようになっても、このやり方は変わ らない。
ただ、「あなた」にはひとつだけこだわりというか、急所があった。目、である。裸眼で度数が0.1もない目にコンタクトレンズをはめて、「あな た」は世を渡ってきた。傷つきやすい繊細な目である。この女性を「あなた」と呼ぶ女の子は、対照的にたいへん視力がいい。そのあたりからしてすでに、目を めぐる緊張関係が仕組まれているのだが、やがてこの薄弱な目をめぐって事件がおきる。はじめはちょっとエロティックだけど些細と思えるような、しかし、最 後は実に恐ろしい、読んでいるだけでも神経がつらくなるような出来事である。
ミステリーめいた気配の中で最後までドキドキしながら読み進めてわかるのは、この作品に二種類の神経が行き渡っているということである。一方は、 美人ではないという「あなた」が世渡りのために必要とした神経である。人はときにそうした神経を「計算」と呼ぶかもしれない。たとえば「あなた」は、女の 子の父親と同居した後に付き合いはじめた古本屋に、自分の本当の素性はあかさない。
あなたは、わたしが自分の産んだ子どもではないことも、父と入籍していないことも、父に死んだ妻がいることも古本屋には話していなかった。そのことが古本屋とのつきあいに影響をおよぼすとはあまり思えなかったが、説明するのが面倒だったのだ。(42)
たしかに「面倒」だったのだろう。しかし、そこで「面倒」だと思うような、その淡泊さというか、冷たさというか、寡黙さ、無神経さなどとも呼べるも の、それがおそらくは男たちを引き寄せてきたのだろうし、おそらく「あなた」も無意識のうちでそのことを知っていた。つまり、なかば承知のうえで、「あな た」はいろいろなことをしないですませてきた。やらずにすませたり、見ないですませたりしてきた。それが彼女なりのライフスタイルであり、人生に対する神 経の使い方なのである。
これに対し、もうひとつの神経は「わたし」のものである。こちらは、ちょっと違う。爪の先端を食いちぎるような「わたし」の癖にもあらわれている ように、「わたし」の神経は小さいものや細かいものにどんどん向かっていく。どんどん見る。どんどんやる。しかし、「わたし」に見えているのは、その細か い先端だけなのである。背景も文脈も見えない。だからこそ、あの恐ろしい結末にもつながった。
おそらく多くの人は、神経質なまでに無神経を維持することでバランスを保ち、生活を守っているのだろう。しかし、女の子はそうした領域を、容赦な く視線の威力で暴いていく。その精妙なことばは、最初から最後まで電気がぴりっとするような緊張感をはらんでいて、こちらがちょっとでも目をそらそうもの なら容赦はしない。「爪と目」はそういう小説として書かれているのである。
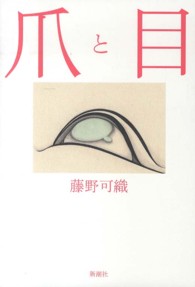
0 件のコメント:
コメントを投稿