2013年12月26日
『神話論理〈1〉生のものと火を通したもの』レヴィ=ストロース(みすず書房)/『アスディワル武勲詩』(ちくま学芸文庫)
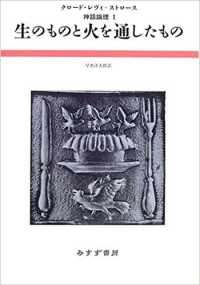 →『生のものと火を通したもの』を購入 |  →『アスディワル武勲詩』を購入 |
レヴィ=ストロースの大著『神話論理』の第一巻である。生きているうちに読みきりたいと思い、手をつけることにした。
レヴィ=ストロースには『アスディワル武勲詩』という神話研究の傑作がある。わずか120頁の小著ながら、カナダ太平洋岸、バンクーバーのあたりからアラスカにかけて伝承されたツィムシアン族の神話群を水際立った手際で分析してみせ、新しい神話研究の方法論を世に問うた構造分析宣言とでもいうべき本である。
『神話論理』四部作は『アスディワル武勲詩』の延長上で起稿されたが、最初の二巻が主に南アメリカ、後半の二巻が主に北アメリカと南北両アメリカ大陸を覆い、邦訳にして3000頁近くにおよんでいる。
規模がこれだけ違う以上、重点の置き方も違ってくる。
神話にはオリジナルがなく、すべて異文だという立場は同じであり、異文を生みだす神話素をとりだすのに構造言語学の音素分析の方法を援用する(英 語話者には law と raw は別の音だが、日本語話者にはどちらも「ロー」で同じ音になるというように)点も共通だが、『アスディワル武勲詩』が神話素とツィムシアン族の習俗や宇宙 観の相関関係を重視するのに対し、『神話論理』では神話素の対立が部族から部族をまたいでどのように変形されていくかにより注目している。最終的には現実 につながるのかもしれないが、とりあえず神話は現実に根をおろすのではなく、神話固有の時空に枝葉を伸ばしていくのである。
『アスディワル武勲詩』には神話が部族の現実に直結するという「岩底に達する」ような安心感があったが、『神話論理』では神話が神話を際限なく生みだしていくという浮遊感が広がっている。
本書の章立ては音楽用語で統一されているが、序文にあたる「序曲」には次のようにある。
そしてたぶん、すでに示唆してあるが、さらに踏み込んで、主体というものを取り除いて、ある意味では、神話たちはお互いに考え合っている、と想定すべきであろう。というのは、本書で取り出して示したいのは、神話の中に何があるかであるよりは、互いに最大限離れた精神や社会や文化から取り出した具体的資料である無意識に作られたものに共通の意味を与えることのできる、最上のコードを決めている公理と公準の体系だからである。
「神話たちはお互いに考え合っている」という表現を奇矯と受けとる人がいるかもしれないが、『神話論理』を行きつもどりつしながら読みすすめていくと、まさに神話が神話を考える世界なのだと実感する。わたしは本書を二回読んだが、二回目の方が浮遊感がよりいっそう深い。
さて『生のものと火を通したもの』である。本書は人間が火を獲得して料理が可能になり、自然と文化が分割されたという料理の起源をあつかうが、出発点となるのは『悲しき熱帯』でおなじみのボロロ族の神話で、『神話論理』全体の「基準神話」ともなっている。長いので、ごくかいつまんで要約してみよう。
成人式をむかえる若者にペニスの鞘を作ってやるために母親が森にはいるが、若者は森の中で母を犯してしまう。父親は息子が母親を犯したのを知り、死者の霊のがらがらを取りに行かせるが、彼は祖母と鳥の助力で無事にもどってくる。
父親は若者に崖の上のコンゴウインコをとりにいかせる。巣の高さまで登ったところで棒を倒してしまい、彼は宙吊りになる。どうにか頂上にたどりつき、木の枝で弓矢を作ってトカゲをとらえる。
若者はトカゲを食い、残りを手足にくくりつけたが、腐ってあまりに臭いので気絶する。そこにコンドルが降りてきてトカゲをたいらげ、彼を尻から食いはじめる。尻を全部食べたところで満腹になり、コンドルは若者を地上に下ろしてやる。
彼は我に返り果実を食べるが、尻がないので素通りしてしまう。彼は祖母の話を思いだし、塊根をつぶして練って尻を作った。
若者はようやく村にもどるが、村には誰もいない。彼は親兄弟を探してさまよい、祖母と弟を足跡を見つける。彼は恐れからトカゲの姿を身にまとっていたが、ついに決心して真の姿を見せた。
その夜、嵐になり、村の火が全部水につかり、祖母の火だけが残る。翌朝、村人全員が種火をもらいにきた。父親は何ごともなかったように彼をむかえた。
若者は父親に復讐するために狩りを催すように仕組む。彼は父親が待ち伏せしている場所を見つけると、偽の角をつけてシカに変身し、父親に突進して突き刺し、湖に突き落とした。父親はブイオゴエの霊(人食魚)に食われ、骸骨は底に沈み、肺は水草になった。
若者は村にもどると父親の妻たちにも復讐した。
この神話のどこに料理の起源があるのか、自然と文化の分割があるのかと不思議に思う人がほとんどだろう。ボロロ族の神話そのものは料理に直接は結 びつかない。料理につなげるにはボロロ族と隣あった地域に居住するジェ語を話す諸部族が伝える火の起源神話を仲立ちにする必要がある。
本書にはジェ系の火の起源神話の異文が六話収録されているが、その中からカヤポ族の神話を紹介しよう。
あるインディアンが岩山の頂にコンゴウインコの巣を見つけ、妻の弟のボトケを連れて雛鳥をつかまえにいく。梯子を登ったボトケは巣から卵を投げおろすが、卵は途中で石になり、義兄は怒って梯子をはずしてしまう。
ボトケは岩山の上で数日間立ち往生し、飢えと渇きで自分の糞便を食べる。
そこの弓矢と獲物をもったジャガーが通りかかる。ジャガーは地面に映っているボトケの影をとらえようとするがつかまらない。上を見て影だとわかると梯子を治し、ボトケに降りるように言う。
ボトケが降りてくるとジャガーは彼を背中に乗せ、住家に連れていって焼いた肉を食わせる。人は火を知らなかったので、火を通した肉を食べたのはボトケが最初である。
ジャガーはボトケを養子にするが、ジャガーの妻は彼をいじめるので森に逃げる。
ジャガーは彼に弓矢をあたえる。ボトケは継母を射殺すが、怖くなって弓矢と焼いた肉をもって村に逃げる。
ボトケは夜中に村に着き、母親の寝床を見つけ自分が死んでいないと納得させる。彼は出来事を語り、火を通した肉を配る。インディアンたちはジャガーから火を奪いとることにする。
インディアンたちはジャガーの留守宅を襲い火を持ち去る。村にはじめて灯りがともり、肉を焼き、竈で暖をとれるようになる。
ジャガーは火と弓矢を奪った養子の忘恩を怒り、人間に憎しみを抱く。ジャガーは牙で狩りをし、肉を生で食べることにする。
ボロロとジェの神話は内容こそ異なるが、構造がよく似ている。
どちらの神話の主人公も鳥の巣を荒らそうとして高いところに取り残され、飢える。臭気の原因は腐ったトカゲと自分の糞便と異なるが、悪臭を身にまとう点は同じである。
一方相違点もある。ボロロの主人公は実の父親に棒を倒されるが、ジェの方は姉の夫によって梯子をはずされる。ボロロの主人公は人間の実子だが、 ジェの方はジャガーの養子である。ボロロの主人公は母親に近づきすぎてインセストを犯し、父親を殺してしまう。ジェの主人公は養父の方から接近してきて母 親のように面倒をみてくれるが、恩知らずにも養母を殺してしまう。
さらに言えば、ジェの神話が火の起源神話だとするなら、ボロロの方は雨風の起源神話である。内容が真逆なのだ。二つの神話は単に相違するというより、対称性にもとづいた反転関係にあるといった方がいい。
部族から部族へ神話が伝播する際、神話素に何らかの変換がおこなわれる。変換の理由は部族の習俗の違いによる場合もある。たとえばジェ系の部族の 多くは母系で妻方居住なので、村にもどってきた主人公は母親か姉妹によって自分だと認めてもらうが、夫方居住のシェレンテ族の伝える異文では兄弟によって 認められるというように変換されている。
しかし現実だけが変換を左右するわけではない。ティンビラ族の伝える異文では父親によって認められるとなっているが、ティンビラ族は妻方居住なのである。
神話は蜘蛛の巣状に広がっており、今の言葉でいえばハイパーテキストを構成しているのだ。ただしハイパーテキストのノードからノードへ移る際に変換が起き、変換がくりかえされて元にもどることもある。
レヴィ=ストロースが『親族の基本構造』につづいて、本書でも群論に助けをもとめているのも決して根拠のないことではない。厳密な群を構成しているわけではないが、神話の網の目は群に似た閉じた構造をとっているらしいのである。
0 件のコメント:
コメントを投稿